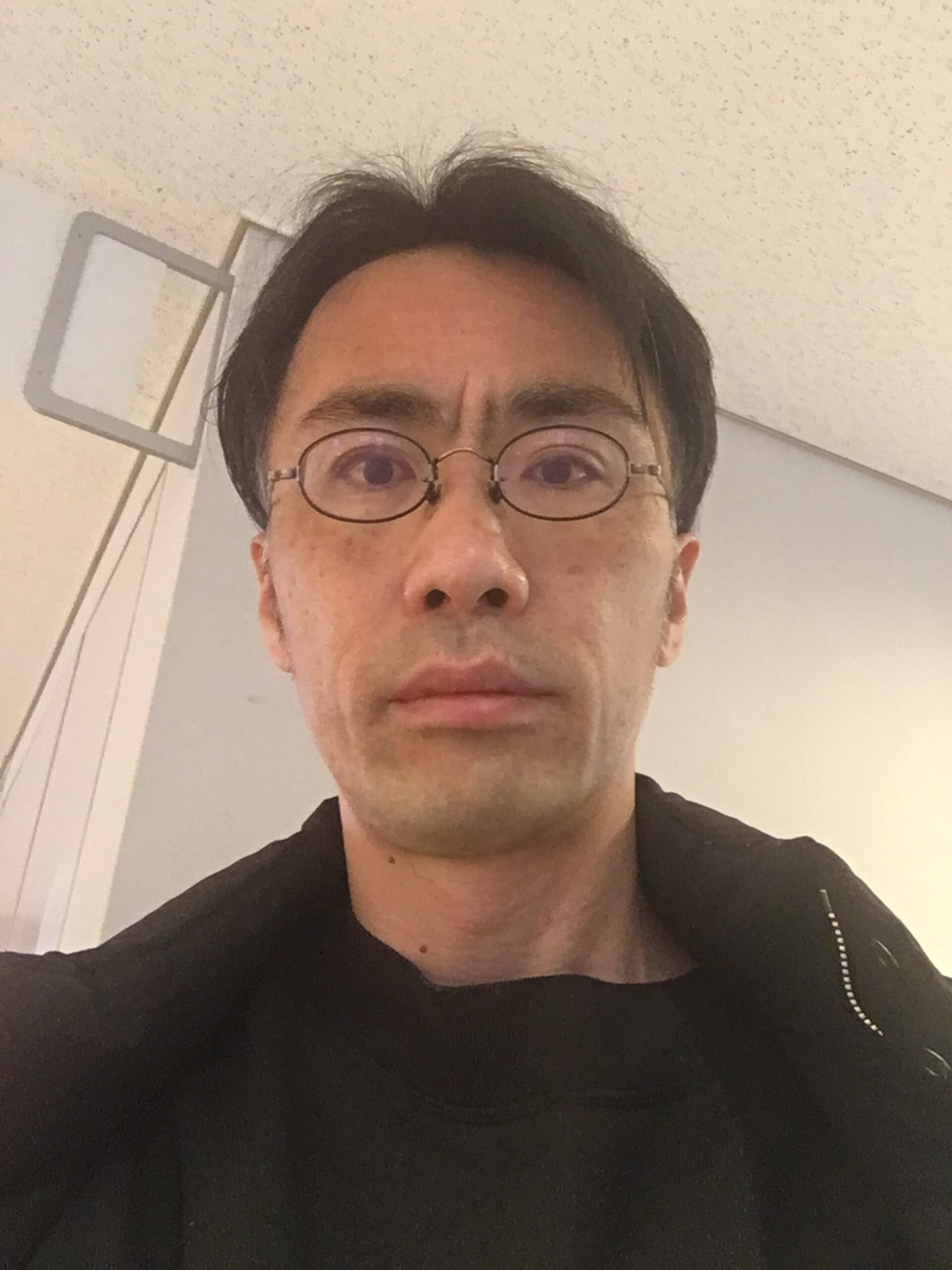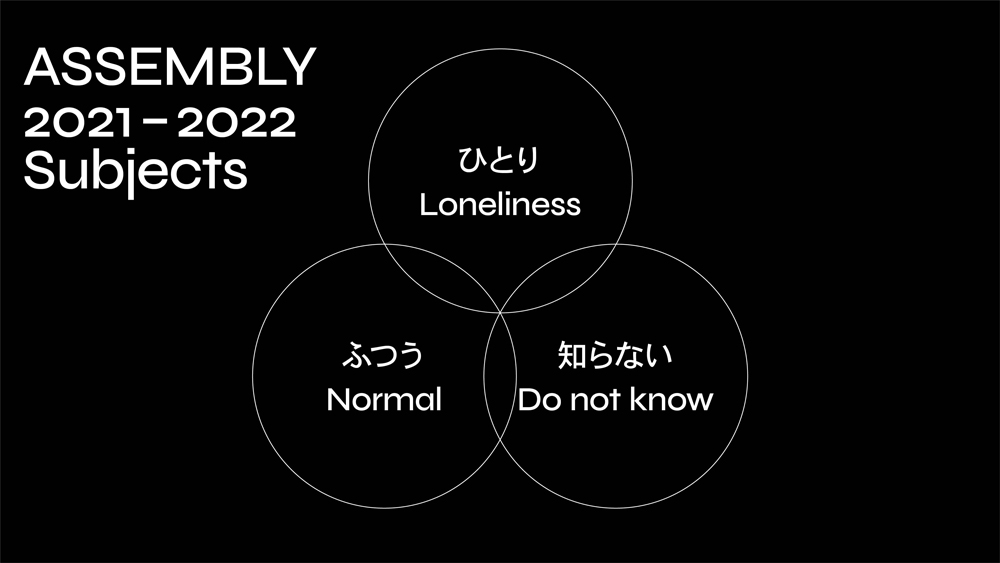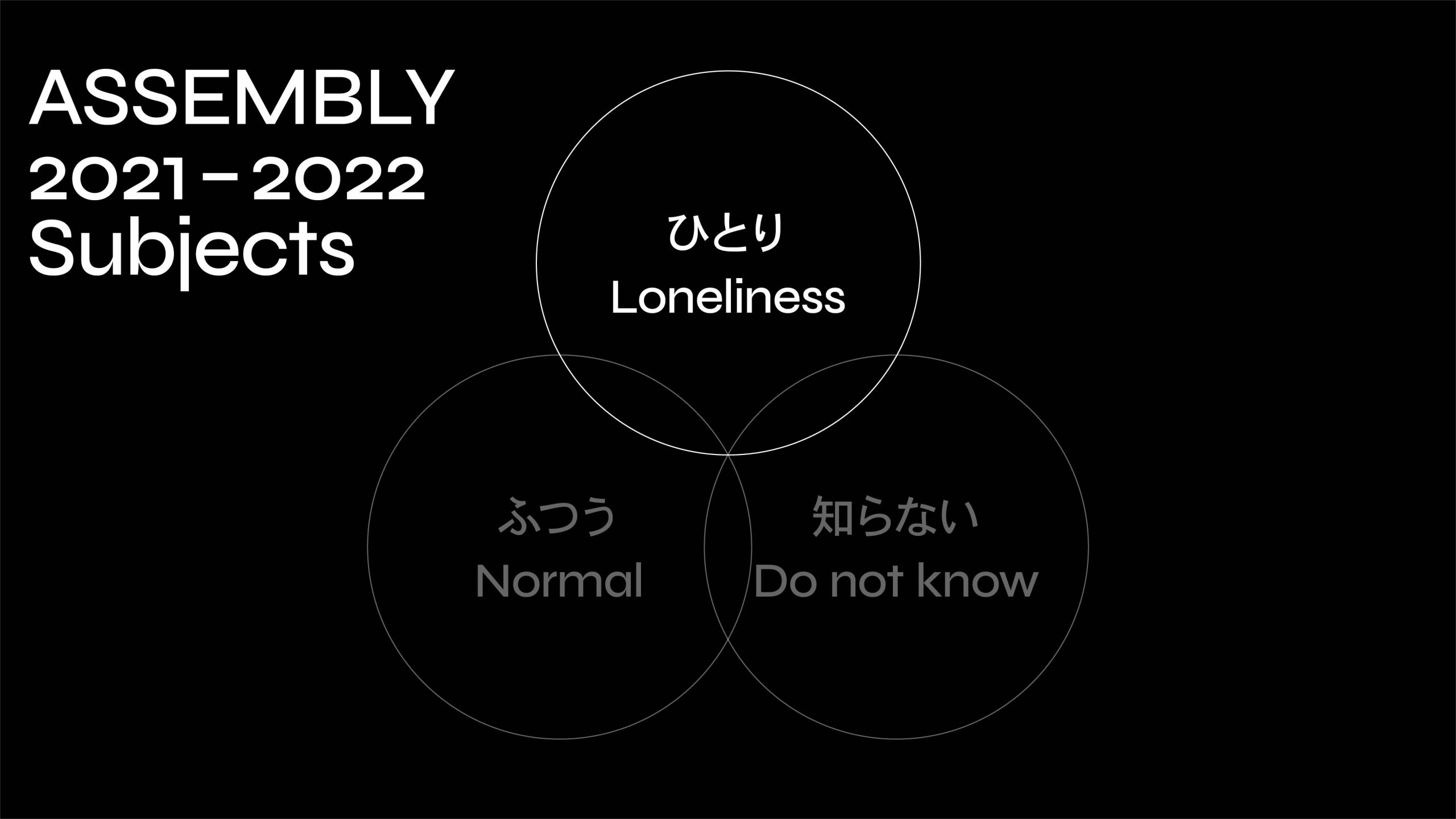「ちょっとわからなかったですね」
「自分の身体が自分でわからない」
「自分と対象の境界がわからなくなる」
「たぶん完全にはわからないんじゃないか」
「具体的になにがあったのかわからないけれど」
上記に書き出したのは、アーティスト・百瀬文氏と哲学者・篠原雅武氏をゲストに迎えた「“いま”を考えるトークシリーズ Vol.20 〈百瀬文映像作品上映+トーク〉 「痛み」を共有する——身体、芸術、エコロジー」での発言のうち、「わからない」ことについて語られた部分の一部だ。
ぼくはこれまで、編集者という仕事柄もあって、それなりの数のトークイベントに参加してきた。講師が聴衆に語りかけるレクチャータイプのものや、複数人が語り合いながらお題の答えを探るディスカッションタイプのものなど、トークイベントと言えどそこでの語られ方はさまざまだが、ここまで「わからない」ことに対峙したトークイベントははじめてだったかもしれない。
その理由は大きくふたつあると思う。ひとつは、ゲスト両者の真摯で正直な語りそのものにあるだろう。今回のイベントは、前半に百瀬氏の映像作品を観客とともに鑑賞したのち、後半にゲストによるトークがおこなわれる構成になっていた。聴衆の前で心のなかをさらけだすように作品の感想を語る篠原氏と、作者としてどのようなことを考え制作したかを篠原氏の感想に応答して話す百瀬氏の対話は、お互いの「わからない」を正直に提示しながらともに考える場になっていた。そしてそもそも、百瀬氏の作品の制作態度そのものが「わからない」ものにどう接近するかを問うものになっているように思う。
もうひとつ「わからない」が頻出した理由として、「痛みを共有する」というトークイベントのテーマがあげられる。イベントの告知文には、百瀬氏の紹介として下記のように書かれていた。
百瀬氏は、自他の身体をめぐるコミュニケーションにおける不均衡と、そこに生じるセクシュアリティやジェンダーの問題を扱っているアーティストです。昨今、自分/個人が所有するはずの身体が、社会の言説・制度・道徳といった通念に抑圧されていると訴える「痛み」の声は高まり続けています。氏の作品は、そうした「痛み」という個人的・身体的感覚は他者と共有可能であるのかという問い、そして異なるものへの想像力が孕む連帯の可能性と暴力性の両面性を鑑賞者に提示しています。
ぼくたちが「痛い」と感じるとき、その傷が身体的/心的にかかわらず、「痛さ」の程度は個別具体的だ。同じような傷がぼくとあなたについたとしても、どのくらい痛いかはその人によるだろう。だからこそ「痛みを共有する」というテーマには、つねに「わからない」がついて離れない。「わからない」からこそ、ていねいに解きほぐしながら語り合うしかない。

ディスカッションの様子
ところで、トーク中に語られた「わからない」の多くは篠原氏の発言であることが多く、これは女性である百瀬氏がセクシュアリティやジェンダーの問題をあつかった作品をつくり、その表現のニュアンスに対して男性である篠原氏の真摯な反応として現れているからだと考えられる。しかしこれは、篠原氏がセクシュアリティやジェンダーに対して無頓着であるのではない。むしろ、慎重に理解しようとするなかで、安易にわかったことにしないために「わからない」が現れる。そしてこの態度は、このレポートを書いているぼくが男性であることにも引き継がれている。
もしかしたら読者のなかには、この記事の「わからない」に対して、いやいやすごくわかるよ、とおっしゃる方も多いかもしれない。それは書き手であるぼくの限界であり、ある種の男性性の限界ととらえてほしい。でも同時に、これは「わからない」から/限界だからそれでいいと放り投げているのではないことも理解いただきたい。「わからない」からどうすればいいか、その方法を「わかる」人たちと「わからない」人たちで一緒に考える必要があるのだと思う。だから、横柄なお願いかもしれないが、「わかる」人たちは、篠原氏やぼくがなぜ「わからない」のかを考えながら読んでもらえたらうれしい。
では、どのような「わからない」について語られたのか。
「透明になる」がわからない
「透明になるって、どういう感覚なのかなって思ったんです」(篠原)
イベント冒頭の映像作品上映では、百瀬氏制作の2作品、《Flos Pavonis》(2021、東京都現代美術館蔵)と《Social Dance》(2019、大阪中之島美術館蔵)が上映された。上記の篠原氏の発言は、《Social Dance》に対してのものだ。
《Social Dance》は、ベッドに横たわったろう者の女性と、ディスプレイに向かってパソコン作業をしていた男性が、手話で会話している様子を定点カメラで撮影した映像作品だ。百瀬氏の友人でもあり実際にろう者でもある出演女性自身が語った言葉をもとに、百瀬氏が脚本を書いている。
女性は、前年に男性とともに訪れた旅行先で、男性に「もうちょっと普通にしてくれない?」と言われたことを回想し、そのとき私はこのように傷ついたのだ、といった内容を手話で語る。あのとき私はとても嫌だった。ごめん、そんなつもりはなかった、でもぼくも努力してる。あなたはいつも……。大丈夫だから。ときおり男性は女性をなだめるように手を握り、落ち着かせるような仕草をする。

《Social Dance》
2019 / single channel video / 10 min 33 sec / 大阪中之島美術館蔵
一見するとよくある痴話喧嘩だ。しかし女性はろう者で、手をふさがれることは、ほとんど唯一のコミュニケーション手段を奪われることと同じだろうし、だからこそ「もうちょっと普通にしてくれない?」という言葉に深く傷ついた。「あなたは何でも自分の都合で判断する」。そして作品の後半、男性はディスプレイの前にもどり、女性の手話によるひとり語りがはじまり、べつのエピソードも交えながら、次のように言う。
「なんか、私はあの日、あの瞬間
確かに自分の体が、透明になっていくのを感じていたんです」《Social Dance》(2019)
自分の体が、透明になっていく。この言葉は、百瀬氏の友人自身が実際に語った言葉なのだという。篠原氏は、先に書いた発言のとおりこうした感覚が「わからない」としながらも、「自分自身も、だれかを透明にしてしまうような言葉を語っているかもしれない」と、コミュニケーションにおける「透明にしてしまう」言葉の暴力性について危惧していた。
「透明になっていくというのは、自分が感じていることや言おうとしていることのニュアンスが相手の発する言葉によってかき消されていくようなことなのかもしれない、と思いました。そうであれば、いま自分がある種の理論的な言葉を用いることで感想を語ろうとすることそのものが、百瀬さんが本当に言いたいことを透明にしてしまう行為になっているかもしれない。この作品を前にして、自分が安易に語ってしまうことに躊躇するわけですが、そこにおいて問われているのは、自分の言葉が相手に「自分が透明にされてしまった」と思わせてしまう言葉になっていないかどうか、ということ。もしかしたら、そういう言葉の作用がどこか限界に突き当たるような瞬間と自分が出会っていて、にもかかわらずそれを発してしまっている自分自身の愚かさに気づくことができるか、ということなんですかね」(篠原)

百瀬文(左)、篠原雅武(右)
同様に、百瀬氏も《Social Dance》の制作過程で、友人である出演者の女性との対話のなかで多くの気付きがあったのだという。
「透明になっていくということもそうですが、いちばん自分に刺さったのは作品内にも出てくる次の部分でした。
「あなたはいつも、想像すればだいたいのことはわかるって言う
想像すれば、わかりあえるって思ってる
ただ、想像するだけで済ませてる」《Social Dance》(2019)
私はアーティストとして抑圧された状況に置かれた人たちを作品で扱うことが多いけれど、そのときの自分自身の態度にも跳ね返ってくるような言葉でした。脚本を書きながら、彼女の言葉についていろいろ考えましたね」(百瀬)
「創作行為がもっている暴力性」がわからない
「透明になる」ことの「痛み」は、はたしてどのくらい痛いのだろう。篠原氏の危惧からもうかがえるように、おそらくこの痛みは男性よりも女性のほうが感じる頻度が多いような気がする。男性優位の社会構造が一般化してしまっているこの国で、透明にされてしまうことの痛みを男性が感じる機会は少ないだろう。そうであれば、女性であることによって生じてしまった傷の痛みを、男性はどのように共感することができるのか。
百瀬氏は、どこまでも個別具体的な「痛み」のディテールを描写することで、社会通念によって抑圧され形成された不均衡そのものを映像化しようとしているのではないかとも思える。より単純に言い換えれば、そうした個別具体的な「痛み」を共有するために、百瀬氏は創作をつづけているのではないか。では、百瀬氏の創作手法を読み解くことで「痛み」の共有に近づけるかもしれない。
百瀬氏の映像作品では、「痛み」がしばしば「暴力」として描かれる。《Social Dance》においては、男性が女性の手を握る=ふさぐことによる暴力が女性の痛みを可視化していた。そしてイベントでの上映作品のもうひとつ《Flos Pavonis》は、より顕著に暴力性そのものが映像化されている。
《Flos Pavonis》は、同名のタイトルのブログを運営しているポーランド人女性のナタリアと百瀬氏が演じる女性アヤが、メールによる往復書簡を朗読しながら映像が展開する。2021年にポーランドで成立したほぼすべての人工妊娠中絶を禁止する法律やそれに対する抗議デモ[*1, *2]、日本の刑法による堕胎罪や母体保護法による男性側の中絶の拒否権[*3]、ナタリアとアヤそれぞれの私的な性関係などについて語られる。

《Flos Pavonis》
2021 / single channel video / 30 min / 東京都現代美術館蔵
作品の途中、薄暗い河川敷を歩いているアヤが、背後から近づいてきた男性に押し倒され、レイプされかけるシーンが映される。これも、男性によって女性が抑圧されることによる痛みを暴力によって表現したと解釈できるだろう。しかし実際のシーンでは、その後暴力構造が反転する。アヤは男性を跳ね返し、自分の唾液を手を介して男性の口のなかに入れる。コロナ禍において体液によるウイルス感染の危険性が高まった社会で、この行為はある種の権力構造をも反転し、国家権力による個人の身体の管理=抑圧への抵抗を意味しているのだろう。
「カッコに入れられた暴力が反転する可能性を、私はポジティブなものとして捉えていました。一方で最近では、暴力そのものが映ること自体への配慮が問われていて、どうすればいいかと悩みながら作品をつくっています。創作行為がもっている暴力性について考えるようになりましたね」(百瀬)
百瀬氏の「創作行為がもっている暴力性」という言葉は、「いま自分がある種の理論的な言葉を用いることで感想を語ろうとすることそのものが、百瀬さんが本当に言いたいことを透明にしてしまう行為になっているかもしれない」という篠原氏の言葉とある意味でつながっているように思う。痛みはまず「痛い」と言わなければ伝わらないし、どのくらい痛いか想像することもできない。《Flos Pavonis》は、暴力構造を反転させることで痛み自体への想像をうながしていると同時に、そもそも痛みを暴力として描くことで、共有の可能性を模索しているとも言えるだろう。
「だれかの死に安堵する」がわからない
《Flos Pavonis》は、暴力だけでなく「性」そのものへの言及も多い。タイトルの「Flos Pavonis」は、登場人物であるナタリアが自身のブログのタイトルにした熱帯性の植物の名前であり、その種子や樹皮はかつてヨーロッパの植民地だったカリブ海諸島に奴隷として連れてこられた黒人女性たちが白人領主たちからの性暴力に対して使用していた堕胎薬だったと作品中で説明される。ナタリアは、自国であるポーランドの人工妊娠中絶を禁止する法律に対するデモには参加せず、部屋のなかで年下のセックスフレンドとセックスばかりしていたと語る。こうした告白に対しアヤは、それは個人の身体を管理しようとする国家への抵抗であり、窓の外で講義デモをする女性たちと深く連帯していたはずだと言う。そして妊娠してしまったかもしれないと言うナタリアに、沖縄でいまでも栽培されているFlos Pavonis(オウコチョウ)の種を取って届けると告げる。
百瀬氏は、ナタリアのエピソードに関連して次のように話す。
「ナタリアはたぶん、不安なセックスをしてしまったあとで自分の生理の血を見て、よかったと安堵すると思います。でもそれって、産まれるはずだった誰かの死に安堵しているということでもある。これは私自身の実感でもあります。すこしトリッキーな発想かもしれませんが、自分の身体を介したねじれた回路をとおしてであれば、遠く離れた人とでも語りあうことができるんじゃないかって思ったんです」(百瀬)

百瀬文
対して篠原氏は「それってたぶんすごく個人的な感覚なのだと思うんだけど、やっぱり男性にはわからない感覚ですね」と話す。ぼくもいまこうして文字にして、あらためてわからない。篠原氏は次のようにつづけた。
「作品中で、作中人物のアヤはじつは母親の望まない妊娠によって産まれたというエピソードが語られていました。《Flos Pavonis》は人工妊娠中絶をテーマにしていますが、たとえば母親の望まない妊娠があって、それがもし堕胎ということになっていたら、作品中に存在しているアヤは、存在していないということになる。言い換えると、産まれたからこそアヤは存在できているわけですが、アヤの親が「堕胎」を決断していたら、存在することがなかった。この作品はそうした矛盾も描こうとしていたのかなと思いました」(篠原)
他人の感覚を素朴に共有してしまうことは、もしかしたらその人の生を否定することにもつながりかねない。「だれかの死に安堵する」ことを、ぼくたちは安易に共有してはいけない、とも言える。個別具体的な痛みをどのように共有するかと模索しながら、同時に素朴には共有しないよう、矛盾を内在化させる必要があるのだろう。百瀬氏は作品制作においてこそ、この矛盾を内在化させようとしている。
「矛盾が矛盾のままで存在させられるのがアートの良さなんだと思っています。私がこの作品のなかで言っていることを本当に実践したら、産まれるはずのなかった自分という人間がこの世に生まれてきたことを否定することになってしまうのか、それともそうではないのか。社会にある種のパラドックスが含まれているのと同じように、ひとつの揺るぎない意志に貫かれる身体というものはないんじゃないか。自己が解体されては形成されることを繰り返す状態を、矛盾しながらも同時に描くことが重要なんだと思います」(百瀬)
「わからない」を内包する連帯のしかた
トーク終盤、百瀬氏は自身の作品制作について、矛盾した状態をどうすれば存在させられるかを考えると同時に、「善悪の判断の手前で、あえて宙づりにされた状態を私たちはどのように見るのか?」という問いを投げかけるものとして捉えていると語った。悪を自分の外部にあると安直に判断してしまう現代社会において、自分の内部にも悪や暴力が潜んでいるかもしれないという視点が重要であると。
対して篠原氏は最後に、そうした現代社会について次のように投げかけた。
「自分と他者、自然と人間、男と女の区別、さらには国境、言語の違いのような「壁的なもの」に基づいて構築された近代的なシステムそのものが、世界の現実の変化を前にして、さまざまなところで次第に立ち行かなくなっているのが、現代なのかもしれません。そう考えると、どこまでが「人間」で、どこからが「人間でない」か、その区別のあり方を問うことも必要なんでしょうね」(篠原)
トークでは質疑も含め、作品制作やコミュニケーションにおいても矛盾や「わからない」をそのままに受け入れることの重要性が確認されていたように思う。判断の手前で立ち止まって考えることが重要であると理解したうえで、しかしここではあえて愚直に問うてみたい。現代社会でなぜ「どこまでが人間か」を考える必要があるのだろう? ここにきて男女の性差とは関係のない「わからない」が現れてしまった。最後の「わからない」を考えるために、篠原氏が翻訳を手掛けた書籍から次のテキストを引用して補助線にしてみよう。
……他者たちが何らかの強い意味で存在するのを許容し、それらも事物にアクセスするのに参加して、少なくとも事物を正しく識別するのを許容するのは、まさしく連帯そのものである。連帯は、何かを共有することを求める。だが、何かを共有するのは、文化主義が本質主義とみなし、反動的な原始主義とみなすものでもある。マルクス主義、反帝国主義、そして帝国主義の思考領域で幅を利かせる強い相関主義の向こう側にある連帯にどうやって到達するというのか。もしかして、何かを共有するというのは、うさんくさくて危険な概念なのか。もしかして、何をも共有しないで連帯を改めて想像することができるのか。……あるいはもしかしたら、「共有する」ということが何を意味するのかを改めて想像することもできるだろう。……私が『ヒューマンカインド』という表題を選んだのは、「共有する」ことが不謹慎なことであるのにもまして受け入れがたい思想にもとづくと考えている学者に対する、入念な挑発行為になるからである。(強調原文ママ)
ティモシー・モートン 著、篠原雅武 訳『ヒューマンカインド——人間ならざるものとの連帯』[*4]
百瀬氏と篠原氏の対話から見出した百瀬氏の作品理解を振り返ると次のように言える。百瀬氏の映像作品は、「透明になる」ことの痛みを個別具体的に描くことで社会の不均衡を可視化し、痛みをある種の暴力として表出させることで痛みの共有可能性を模索していた。そして同時に痛みを素朴には共有できないよう、作品に矛盾を内在化させている。
こうした理解を通して、あらためて今回のトークテーマである「「痛み」という個人的・身体的感覚は他者と共有可能であるのか」という問いへの答えについて考えてみる。痛みを描くこと——より単純化するなら、なにかを「つくる」ことによってある程度の痛みの共有は可能かもしれない。けれど同時に、共有できない部分も残る。
ぼくはこのトークを「痛みを他者と共有することでどのように連帯するか」を考えるための時間として聞いていた。けれど、ぼくたちにはどうしても共有できないなにかがある。もしかして、痛みを共有しないで連帯を改めて想像することができるのか。あるいはもしかしたら、「痛みを共有する」ということが何を意味するのかをあらためて想像することもできるのだろうか。
こう拡大解釈できるだろうか——ぼくたちは痛みを共有することによって連帯するのではなく、痛みを共有できないことによって連帯する必要があるのだ、と。つまりそれは、社会の連帯のなかに「わからない」がつねに内包されていることにほかならない。
ぼくたちにはどうしても共有できない痛みがあるけれど、だからこそ、ぼくたちは連帯を必要としている。そしてその共有することとはべつのところにかたちづくられる連帯には、おそらく「人間ならざるもの」との連帯も付随してくるだろう。そのために、ぼくたちは「どこまでが人間か」をあらためて考える必要があるのだ[*5]。
そのとき、おそらく男女の性差では規定されないべつの「わからない」が現れるはずだ。
*
ところで、ぼくはこのレポートを「わからない、わからない」と苦しみ、書き上げるのに時間をかけてしまった(ご迷惑をおかけしたみなさま申し訳ありません)。「すごい難産だよ」と妻に弱音を吐いたところ、「子どもを産むことがどれだけ痛いのかも知らないのに難産なんて使うな」と叱られた。ごもっともと反省しつつ、それでもぼくたちは連帯しているのだと、書き終えたいまは言える。「次からは難航するって使うようにするよ」「今度は船乗りの人に怒られないといいね」。