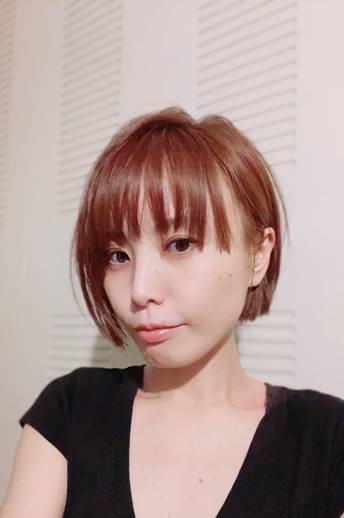「ポストフェミニズム」時代の「女らしさ」
木村 今回は『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど ポストフェミニズムと「女らしさ」のゆくえ』(晃洋書房、2020年6月)を出版された高橋幸さんに、市原佐都子/Q『妖精の問題』(の映像、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2018での上演)をご覧いただき、その上で、女性と表現の問題についてお話を聞かせてもらえたらと思っています。副題にあるように、高橋さんは「ポストフェミニズム」(フェミニズムがある程度浸透した時代)の「女らしさ」について考察されているわけですね。
高橋 はい、「ポストフェミニズム」と言っても、「フェミニズムが終わった」ということを主張するものではもちろんなく、20世紀後半の第二波フェミニズムとは異なってきている現代の女性の状況を捉えようとする立場のことを「ポストフェミニズム」と言います。
木村 ご著書の中では、「女らしさからの自由」という消極的自由だけではなく、「女らしさへの自由」という積極的自由を追求していく観点も提出されていますね。
高橋 「女らしさ」を重視するフェミニズムは、これまでも第一波フェミニズム期の「マタニティフェミニズム」(母性を重視するもの)や第二波フェミニズム期の「エコフェミニズム」(「女性」の立場から環境問題に取り組むもの)などがありました。1990年代以降には、女性のセクシーな魅力や女の子らしい「かわいらしさ」を肯定的に捉える側面を持つ第三波フェミニズムが出てきています。私の議論も、この第三波の流れを汲むものです。
木村 最近の論文で、モデルの水原希子が「最も美しい顔ランキング」に選ばれつつも、ルッキズムの助長に加わっているつもりはないと言ったことを受けて、そこに高橋さんは「一元的な美の尺度による人間の序列化への不当感」 を読み取っています。美の尺度が一元的である限りは、「女らしさへの自由」をポジティブに捉える方向へ女性たちは向いていけないと思うんです。

高橋幸
ジェンダー論の高橋さんが見る『妖精の問題』
[編集部注:これ以降、両氏により『妖精の問題』の演出についての言及が続きます。高橋氏に鑑賞いただいた映像は『妖精の問題』初演バージョンの竹中香子氏演じる一人芝居の形式のものであり、発言はその演出に対してのものになります。今回、ロームシアター京都で上演した『妖精の問題 デラックス』では、言及されている演出内容・役名の変更や、戯曲が改稿された箇所がありました。]
木村 そこで『妖精の問題』について話を始めたいのですが、第一部が「ブス」というタイトルです。「ブス」は、先に述べた「美の尺度」が一元的である時に出てくる概念という風に思うのですが、高橋さんはどのようにお考えですか。
高橋 「外見美をめぐる一元的な尺度」についてどう考えていけばいいのか、もう少し言うと、それを具体的にどう解体していくことができるのか?というのは重要な問題ですよね。美の基準に従って人間は一元的に序列化できるという発想が、外見をめぐる暴力を生む原理の一つになっているので、なるべくこの発想をゆるめていく方法を模索することが重要だというのが私の立場です(ちなみに、もう一つの外見をめぐる暴力を生む原理は、外見による人間のステレオタイプ化です)。
まず、誰かの美しさを褒めることと、誰かの外見を「ブス」として蔑むこととは、別のことです。これを区別しないと、ルッキズムをめぐる議論は混乱してきます。よく「ブスと言うことが良くないのであれば、誰かを美しいと評価することも良くないのか!?」「美しくなろうと自分が努力することも良くないのか!?」といった疑問を投げかけられます。しかし、誰かを美しいと評価することの反面に、誰かを「ブス」と蔑むことがあるという発想は、そもそも美を「ある一元的なもの」として考えているがゆえに出てくるものです。
実際の日常生活を振り返ってみると、私たちは美を多元的なものとして捉えているケースも多いことに気づきます。
例えば、自分の中での「理想的な美しさ」の基準があるからといって、それに合致しない人を全員「ブス」だとか「価値がない」とか思いながら生きているわけではありません。いや、中にはそういう強烈な美意識を持って生きている人もいるかもしれませんが、一般的には「外見の美しさにはさまざまな種類のものがあり、何を美しいと感じるかも人それぞれだ」という前提がある程度受け入れられています。こんな風に「美の多様性」を認める立場を取るのであれば、必ずしも「誰かを美しいと評価することが、誰かを抑圧することにつながる」とは限りません。その意味で、「自分にとっての理想の美」を称揚するのは問題のないふるまいだと言える場合もあるわけです。
水原希子さんが「最も美しい顔ランキング」に選ばれた時に困惑を示したのは、それが美の一元的序列化を連想させるような「ランキング」形式だったからでしょう。ルッキズムに批判的な彼女も、個性的な美しさを持つ人だと褒められること自体に異議申し立てするつもりはないだろうというのが、私の理解です。
木村 なるほど、高橋さんのお立場はよく理解できました。
高橋 さて、この前提を確認した上で、今日の主題は『妖精の問題』第一部のタイトルでもある「ブス」ですね。
「ブス」をめぐる最大の問題は、自分の「ブス」さにどうしようもなく苦しくなってしまうことにあります。他人に「ブス」という蔑称を投げつけられることで傷つくということもありますが、何より自分が自分のことを「ブス」と思うことで、自分の「人間としての価値」が低いように思われ、自分の存在意義を見いだせなくなってしまうような感覚に陥ることが、その苦しさの正体です。これをさしあたり「ブス問題」と名づけることができます。つまり、ブス問題とは、純粋な外見美の問題というよりも、むしろ劣等感の問題であり、自尊感情が削られていて自分に自信が持てないという問題だと、私は考えています。
『妖精の問題』第一部では、まさにこの問題が描かれています。登場人物の少女二人は「ブス」を自称し、「ブスだから仕方ない」という論理を内面化させられていますね。彼女たちが語るところによると、「平均からの逸脱」が「ブス」であり、それは「自然淘汰」によって「絶滅」する運命にあり、それはすべての生物を支配している「自然法則」に則した当然のことである、らしい。「ブス」という言葉の周りにエセ科学的な言葉が集められ、総体として「ブスが淘汰されるのは仕方のないこと」という言い回しが作り上げられています。恐ろしいのは、これが「ブス」というラベルを貼られた人たちを社会的に排除していく正当化の論理になっているところです。本人たちさえも、その論理にある部分で納得してしまっており、それゆえ苦しい状況に陥れられているところが、やるせなく悲しいところだなぁと観劇しながらしみじみと思いました。「ブス」という言葉が恐ろしいのは、こういうところです。
木村 「逆瀬川志賀子」という政治家による「政見放送」を通して、そのような考えが女の子たちの心を支配していきますね。
高橋 はい、『妖精の問題』に出てくるのは、何らかの障害を持つ特別支援学級の子なのかなと思わせるところがある二人ですが、彼女たちは「障害者」ではなく「ブス」というラベルを背負っています。これによって「自尊感情が削られ、自分の存在意義を見いだしにくくなるような社会的排除」というあり方に、より明瞭に光を当てることができているように思います。
先ほど、ブス問題とは劣等感の問題であり、自分の存在価値が見いだせなくなるという苦しさのことだと言いました。これまで、「自分に自信を持てないのはその人の責任」という形で、それらの問題は自己責任化されてきたところがあります。自分の存在価値は「自分」しか見いだせないのだから、自分一人で何とかすべきだと暗黙の裡に考えられてきました。
しかし、自尊感情を維持しやすいか、あるいは削られやすいかは、個人がどのような社会的位置に置かれているかによって異なります。「稼得能力や生殖能力などの『生産性』が高い人間こそ価値がある」(なんてことを現実社会で言うのは一部の保守政治家くらいのものですが)とする社会において、障害者や非正規雇用者、貧困者、セクシャル・マイノリティ、そしてこの『妖精の問題』でも排除の対象となっている「高齢者」などは、自分の存在意義を見いだしにくい。社会的排除とは、こんな風に特定の人を「存在価値のない人間だ」と思わせる状況に追いやり、当人の自尊感情を削っていくことで、存在そのものを抹消していくことを指すのではないか。外見をめぐる蔑称である「ブス」というカテゴリーで考えることで、こういうことが見えてきます。
木村 なるほど。もし彼女たちが「私たちの問題は社会的排除の問題だ」と認知できれば、解決の道というのは社会学的に見えてくるのかもしれません。しかし、彼女たちはその思考にたどり着けず「淘汰」に囚われていますね。私自身は、限定的な情報量の中で美人/ブス観を形成してしまった若者、しかも、その中で逆瀬川志賀子の「政見放送」のような歪な思考を摂取してしまった若者というイメージを持っています。情報が制約された中で〈ものの考え方にディストーション(歪み)がかかってしまった女の子たち〉という解釈です。そして、そのような思考の歪さ、狭さに彼女たちは苦しめられている。しかし、そうした境遇から起こる個人の心情を見つめるところに演劇というものの人文学的・芸術論的な意味があると私は考えています。
高橋 そうですね。第一部に登場する少女たち二人のことを、私はそれぞれ「ポジティブな方の子」と「ネガティブな方の子」と呼んでいるので、ここでもその呼称を使わせていただきたいのですが……いいですか?
木村 えぇ、どうぞ。
高橋 私は『妖精の問題』の第一部に関しては、もうとにかくこの「ブス」の子たちが「救われた」のかどうかが、最も気になっています。その点に関して言うと、もっぱら「ポジティブな方の子」が持つ「生命力」とでも言うべき圧倒的な自己肯定の力によって、彼女は自力で状況を打開していきます。個人的な力にのみ基づいて、社会的な不条理を乗り越えていく様は「英雄的」としか言いようがない、すばらしいものでした。特に最後の展開のところです。ネタバレOKということで、私が観せていただいたバージョン(2018年版)の流れを喋ってしまいますが、 「ポジティブな方の子」が次のように語ります。――お風呂上がりにじっとしていると、自分の身体からじわっと汗がにじむ。それが何とも言えない良いにおいだと気付き、その気付きをきっかけに自分の身体そのものがとても良いもののように感じられてくる。そして、この自分の身体に対する絶対的な肯定感に基づいて、「交尾したい」という欲求を爆発させる――。この流れが説得的でした。「ブス」と自称しつつも、揺るぎない自己肯定感に満たされた彼女の存在は、一つの救済の形だと思います。これによって「ネガティブな方の子」にも自己肯定感が伝染し、「自分のトークの才能」に目を向けるようになっている。この一連の展開は時間にすると短いのですが、感動的でした。
木村 あの部分をそう読み取ってもらえると、ありがたいです。
高橋 さらに、この少女たちのキャラクターづくりは、市原さんならではの良さが光っていました。ポジティブな方の子が「将来は、カネザで働きたい」と述べた後、「銀座じゃなくてカネザ。マネーじゃなくてゴールドの方」っていうお気に入りの決め台詞を言うんですよね。そこが私はものすごく好きです。世界に勝手に名前をつけて、呼んで、満足している感じが「万能感にあふれている少女らしさ」を見事に体現しているなと思いました。
木村 彼女の心の根底から湧き上がる前向きな力には、強く感動させられるところがありますね。

『妖精の問題』(2018年) Photo:Kai Maetani
高橋 2018年版の『妖精の問題』は、一人の役者が現代の女性キャラクターを演じ分けるという構成になっており、女性キャラクターでなければで浮かび上がってこないような論点が真正面から展開されています。「ブス」の問題はまさにそうですし、第二部では倦怠的な日常の性生活と生殖、第三部では「男性」にとってのエロいものとしてのみ表象されがちな女性器を、「女性」にとっての「自分のための性器」としてユーモラスに提示するものでした。このような全体構成の中で、現代日本ならではのさまざまな女性ステレオタイプが演じられ、時にひっくり返されており、そこもおもしろかったです。
木村 「ひっくり返し」とも言えると思いますが、私は「内破」と呼んでみたいところがあります。本作ではしばしば問題が浮き彫りになってきたところで、第一部の「ポジティブな方の子」の展開が典型的なように、不思議と問題を突き破る光明が見いだされます。
高橋 なるほど、「内破」と言うのが適切ですね。一人一人のキャラクターが内から破っていくだけの強さを持っています。私が特に「これはやられた!」と思ったのは、第三部の「淑子先生」です。2018年版で、淑子先生はステージ奥のスクリーンに投影される形で登場します。しかし、これは、第一部で暴力的な優生思想的主張を繰り返した女性政治家(「逆瀬川志賀子」)が登場した方法と同じです。逆瀬川もまたスクリーン上に投影される形で登場しました。そのメディアの共通性ゆえに、観客としては、第三部で「淑子先生」が投影された瞬間に、「あ、これは警戒した方がいいのではないか」と身構えることになります。3次元の演劇舞台上で2次元スクリーンを使う、というように、メディアを切り替えることでこのような身体反応が引き起こされるところがおもしろいですよね。しかも、この淑子先生は、シュールな雰囲気を醸し出しているセミナーの親玉という位置づけですから、観客は「自己同一化しにくい存在」として淑子先生を見ることになり、その結果、第三部の間ずっと淑子先生を、ある種のステレオタイプで見てしまうことになります。
木村 淑子先生の内部にある固有の視点は、すぐには明らかにされませんよね。
高橋 でも、最後の最後に「答え」らしきものを示してくれるのは、舞台上に登場する生身の淑子先生です。淑子先生が、ゆっくりゆっくり言葉を絞り出す。その音のつらなりを聞きながら、「ああ、私はこの人をステレオタイプ的にしか見ていなかったなぁ」と気づきました。後から冷静に分析してみると、いま述べたような仕掛けになっていたなとわかったのですが、ステレオタイプの呪縛を改めて体験しました。
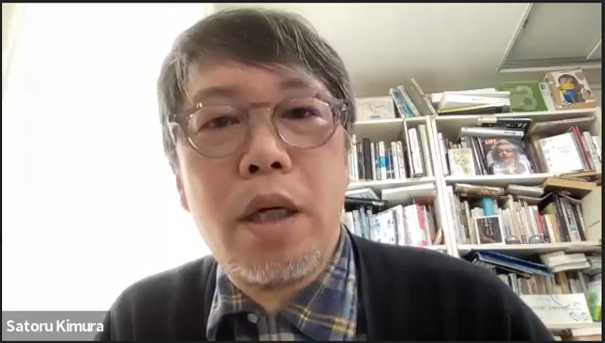
木村覚
「マイノリティ」と鑑賞する演劇であるために
高橋 このような意味で、『妖精の問題』は、フェミニズムの立場から見ても重要な作品だとは思っているのですが、ただ少し引っかかっていることもあります。それは、舞台上で優生思想に基づく言葉による暴力的な表現があれほどまでに繰り返されていることに関してです。この作品がディストピアを描いたものだということはわかります(例えば「歯のない老人たちが食事をするのは不自然だ」とする作中の設定が最後まで覆らないことからも、このことは明らかです)。ディストピアを見せられた観客は、このどうしようもない後味の悪い気持ちを抱えたまま、帰途につき、そして「ブス」という社会的排除の問題等を考え続けるのが重要なのだとも思います。
特に、マジョリティ社会(男性社会)に対して、身体や情動に訴えかける暴力表現を用いて問題提起をすることで、「彼ら」の意識をゆさぶろうとすることには意義があるのかもしれません。しかし、外見をめぐる深刻な生きづらさを抱えている当事者に、私個人としてこの作品を推せるかというと、少し難しいと感じます。こう言い換えられるかもしれません。この作品が向いている方向はあくまでもマジョリティであって、本当に「ブス」という自己意識で苦しんでいる当事者の方を向いているわけではない(ように解釈できてしまう)点に、何とも言えない一抹の悲しい気持ちを持ってしまうということです。これに関しては、これからご覧になる方や、すでにご覧になった方々のご意見も伺いながら、私自身、もう少し考え続けたいと思っている点でもあります。
木村 そこはまさに『妖精の問題』の「問題」に関わるところなんです。ポリティカル・コレクトネスと芸術、社会と芸術の問題ですね。社会において芸術が占めていた特別な地位というものが問い直されていて、そのことを自明視して構わないという考えは、近年では通用しなくなりつつあるということでしょう。
高橋 私は、芸術作品の完成度が高ければ高いほどポリティカルな批判に抗することができるのではないかと信じたい気持ちもあるのですが、他方で、2010年代以降のソーシャルメディア時代の中で、芸術と社会の関係が変化したことは認めざるを得ないとも思っています。芸術が完全にポリティカルコレクトネスを無視することは不可能になりました。特に市原作品は、フェミニズム的な思想を読み込みたくなる誘惑が随所にあるだけに、どうしてもフェミニズム・クィア理論の立場から見た時にどうなんだろうという分析視点を呼び込んでしまうところがあります。
木村 ポリティカルコレクトネスが是正を促し、誰かの自己肯定感を阻害しない「安全な空間」が社会に生まれるのは、暫定的には正しいことだと思います。でも、それはあくまでも暫定的な方法なのではないかと思っています。最終的には、すべての「欠陥」(と思われているもの)は各自の「特徴」にすぎず、その上で「特徴」をいくらいじっても「笑い」として解消されるような心の信頼状態こそ、私たちが目指すべき空間なのではないかと思うんです。その信頼さえあれば、いじりはむしろ楽しいことのはずなんです。
つまり、最終的な解決は、社会が「掟」によって私たちに課してくる劣等意識を、私たち自身が大したものではないと思えること、そして、劣等意識から自由になることによるのではないでしょうか。
私は拙著『笑いの哲学』でユーモアの笑いを、そうしたことを可能にする力と捉えていますが、そのようなユーモアを『妖精の問題』が充分に発揮できているかといえば、初演時の戯曲・演出では、まだそうではないと思っています。
高橋 なるほど! 先日『笑いの哲学』を拝読したところでした。そうですね、ユーモアの「笑い」によって「ブス」という自己意識をゆるめたり、劣等感を自分の中でコントロール可能なものにしたりしていくという戦略はありえるかもしれません。また、外見いじりを誰もが恐怖感なく楽しめるような「信頼状態」が成り立つといいなとも思います。
さらには、「私はブス!」とポジティブに自称するという「ブス・プライド」のような運動を立ち上げていくという方向性もあるかもしれません。過去にクィア系の雑誌でそのような特集が組まれたこともあるのですが(例えば、『クィア・ジャパン 魅惑のブス』Vol.3、勁草書房、2000年10月、編集長:伏見憲明)、現時点では「ボディ・ポジティブ」運動(ありのままの身体を肯定的に捉えることを目指すもの)の支持層が厚いという状況なのかなと考えています。『笑いの哲学』ではお笑い芸人の分析がなされており、そこもとても勉強になりました。「ブス」をユーモアな笑いにするという点に関しても、女性お笑い芸人が先陣を切って可能性を開拓してきたのだと思います。
木村 価値の序列(私はこれを社会の「掟」と呼んでいます)を相対化・無意味化していく力がユーモアにはあると思っています。この力の可能性をもっと個人が社会の中で展開できるようになったら、生きやすい世の中になるのではないでしょうか。確かに、ポリティカル・コレクトネスと芸術というのは難しい問題ですけれども、高橋さんやこれまでのインタビューシリーズでお話しさせてもらったゲストたちの意見を踏まえ、問題を語る際の「語り方」を新たなものにするべく試行錯誤していきたいと思います。
高橋 恐縮です。最後にもう一つ。これはジェンダー論を専門にする私でなくても多くの方が関心を持っている点だと思いますが、『妖精の問題』の初演は2017年で、その後、コロナ禍がありました。デーデルライン桿菌という「菌」を殺菌消毒するのではなく、うまく生かしながら共生するという方向性を一つの解として示していたこの作品は、パンデミックを経験した私たちにどう映るのか。ご覧になったみなさんがどのように受け取るのかも興味深い点です。再演が楽しみですね。
木村 まだまだ話し足りないですが、今回、高橋さんとお話しできなければなかなか見えてこなかった課題が見えてきた気がします。ありがとうございました。
高橋 どうもありがとうございました。