2021年度の「レパートリーの創造」で上演する市原佐都子 作・演出『妖精の問題 デラックス』。本作でドラマトゥルクを務める美学者の木村覚がインタビュアーとなり、さまざまなジャンルのゲストを迎えて、インタビューシリーズを全4回にわたって展開する。2017年の初演から5年の時を経て本作のリクリエーションをするにあたって、この作品が提起する問題を作者自身も含めてあらためて考え、創作に役立てていく試み。
インタビューの前に:木村覚のメッセージ
今回、市原佐都子『妖精の問題 デラックス』のドラマトゥルクを務めます、美学者の木村覚です。昨年刊行した『笑いの哲学』では、笑いは良いものか、悪しきものかを問いました。笑われたくない人間の意識を解明しながら、ポリティカルコレクトネスや自虐という現象を分析した上で、笑いの潜在的な可能性を開くユーモアへの道筋を探しました。
今回、インタビューシリーズを通して、表現する側(ex. アーティスト)とそれを受け取る側(ex. 観客)との有意義なつながりを生む「技」を見いだせたらと私は望んでおります。市原は本作を上演するに際して、表現というものがおびうる暴力性を意識しつつも、安易な「事なかれ主義」に陥ることなく、表現する側とそれを受け取る側とがしかるべき関係を結びうる「方法」を探しています。本作は、相模原障害者施設殺傷事件を発端にしており、この点に関連して市原 は「私も事件を起こし得る危うい人間なのかもしれない。事件によって、自分のなかにある優生思想や、自分が抱えている生きづらさを意識させられた。その正体を知りたい、その危うさを見つめなければいけない。そして、できるだけ偽善的ではない方法であらゆる生を肯定することを試みたいと思った」と述べています。ゲストの皆さんとの対話を通して、そのヒントが得られたら幸いです。
大前さんが見た『妖精の問題』という問題
木村 インタビューシリーズ第三回では、お笑い芸人が登場する『おもろい以外いらんねん』(河出書房新社、2021年1月刊)をお書きになった大前粟生さんと、表現と社会との関係についてお話しさせてもらえればと思います。今回、このインタビューのために、大前さんに『妖精の問題』(の映像、2018年KYOTO EXPERIMENTでの上演)をご覧いただいたと思うのですが、まずはその感想からお聞かせください。
大前 三部構成のそれぞれが落語だったり、歌だったり、セミナーだったりと、異なる形式が用いられていて、その形式とそれぞれで話されている内容とにギャップがあって、それが与えるもやもや感がおもしろいと思いました。特に第二部はゴキブリの話をするんだけど、演者がゴキブリについて歌う時に、ひときわ良い感じに歌っていて、ピアノの伴奏とあいまって、すごくリラックスして聴いてしまいました。私はゴキブリがすごく苦手なんです。でも、心地良い音色というだけで身体がリラックスしてきて、芝居の途中に寝ちゃいそうな気がしたくらいで。
木村 気持ち良くて?
大前 そうなんです。内容よりもムードに自分自身が左右されている状態で、もしこれが芝居じゃなかったら、無茶苦茶やばい気がしました。洗脳されるかのような状態に簡単になってしまった、といいますか。身体は気持ち良いのに、頭ではとても怖いことを体感させられているな、と。それがおもしろかったですね。
木村 上演の形式に心が押し流されている感覚ということでしょうか。
大前 例えば、私は言葉の意味を把握しないまま洋楽を聴くことができないんです。歌詞の内容がわからないのにメロディーに乗せられて聴いてしまうことに違和感があるんですよね。ひょっとしたら殺人を教唆するような歌詞だってあるかもしれないのに、なんてことを思ったりするんですけど。第二部は、普段、ただただ生きていることの気持ち悪さを見せつけてくれたという印象があります。
木村 「ただただ生きている」とは、どういう状態なんでしょう。
大前 (本人が意識している/いないに関わらず)生きているだけで何かに加担したり肯定したりしている状況が、多々あるんだと思うんです。存在しているだけでさまざまな対象に少しずつ暴力を働いている状態というか。そういった普段気づかずにいることを、(『妖精の問題』などの)「作品」というものに向き合うことで振り返ることができるんですよね。
木村 「作品」の形式そのものが持つ力、ということでしょうか。
大前 そうですね。上演の形式が内容の受容をフラットにしてくれるように思いますが、その分、その「形式」によって観客は「人を殺す」といったことまでもフラットに促されてしまうのではないか、とも思いました。第一部には「逆瀬川志賀子」の政見放送が出てきますが、あれがもし舞台上ではなくてリアルにYouTubeで流れていたら、本当に支持する人が結構出てくるだろうなと想像します。

大前粟生
木村 演劇作品は、普通であれば劇場に行かないと観ることができないものです。ライブで鑑賞し、そこで消費されるだけなんですが、でも映像に残された場合、YouTubeで公開されていたりすると、受け取られ方が変容するかもしれない。『妖精の問題』でいうと、その「政見放送」の形式に従って、それを本物の政見放送と誤解し、その誤解に乗じて逆瀬川の支持者が大量に出てきてしまうかもしれない――。つまり、そこで起きているのは、演劇が「演劇」として認知されずに「政見放送」として認知されてしまう「ズレ」であると。大前さんがおっしゃったのは、そんな“さまざまな境界のフラット化”が起きているのではないか、ということですね。これは「演劇」なんだと、目の前の出来事をメタレべルで認知できずに、いわばベタに「政見放送」として見てしまう。
大前 それが演出なのかどうかをあまり意識しない状況がありますよね。ショートムービーを投稿・シェアできるSNSアプリの「TikTok」を見ていると、最近ではドライブレコーダーの衝撃映像みたいな投稿がものすごくウケているんです。事故とか、エロいものとか、「あおり運転をしていたら、目の前の車からヤクザが降りてきた」みたいなものとか。そういった衝撃映像の中には「コント」として仕込んだものを製作している人たちも一定数います。「これはコントだ」ということが初見ではわかりづらかったりするようなものも多いんです。「本当に起きたこと」か「作られたこと」なのかを、配信する側は曖昧にしているし、それを受け取る側もその曖昧さにあまり頓着がないようなんです。刺激があることが何より重要なのかなとも思えて、怖い気がしますね。
木村 批評家の東浩紀のオタク文化論が出てきた20年くらい前だったら、ベタ/メタ/ネタといった位相の違いを的確に感知して、ポップカルチャーを受容することが若者の知性だといった認識が共有されていたと思うのですが、それが随分と変化してきたということなのかもしれません。ただただ、ショックや性の刺激に対して純粋に反応できる状態をTikTokのユーザーは求めている。そこにベタか、メタか、ネタかなんてことはあまり意味がないという行動様式が出てきているわけですね。
『おもろい以外いらんねん』と笑いと喧嘩
木村 さて、せっかくなので『おもろい以外いらんねん』のお話を聞かせてください。もちろん小説なのですが、登場人物たちの間でお笑いをめぐる見解が取り交わされているところがあり、お笑い論としてとても興味深いです。
例えば、この小説の語り手である「咲太」と彼の友人で漫才師の「滝場」(高校時代に転校生の「ユウキ」と漫才コンビを組む。代わりに咲太はそのチャンスを失う)の対話のシーンで「おもろい以外いらんねん」という言葉に二種類の意味が与えられるところを見てみたいのですが、
「いうてることはわかるけど、そういうの徹底して『傷つけない笑い』とかいわれても別にうれしくないやろ。傷つきを排除してるっていうことしか世間は見てくれへんやん。おもろいかおもろくないかだけがすべてやのにこいつらは『傷つけない笑いをしてるからすばらしい』とかいわれたら白けるやろ。おもろい以外いらんねん」〔滝場〕
「しゃあないやろそういう倫理観の変わってく時期なんやから」〔咲太〕
「ハッ。しゃあないとか仕方ないとか咲太けっこういうよな」〔滝場〕
「おまえもやんけ。なんかをあきらめることに順応しておれらふたりともダサいねん。それにおれは、おまえらのネタちゃんと見てるわ。ユウキくんが書いたネタおもろいやんけ。ネタと平場からきつめの言葉とかいじり笑いを取り除いたところでおもろいことには変わらんやろうが。おもろい以外いらんねん。おまえらの笑いをさあ、外野によごされたくないんやったら変な意地を張るなや。傷つけるとか傷つけないとかおまえどうでもいいやろ。笑えるかどうかにしか興味ないやろ。せやったら『傷つけない笑い』とかを前提にしてもうたらいいやん。早くそれやって早くみんながそれを当たり前やと思うようになったらわざわざ言及されることもなくなるやん」〔咲太〕
(大前粟生『おもろい以外いらんねん』河出書房新社、2021年、p. 152-153 下線強調と〔滝場〕〔咲太〕は木村による)

大前粟生『おもろい以外いらんねん』(河出書房新社)
木村 ここで大前さんが描いているのは、「傷つけない笑い」の時代にどうやって自分の笑いを見出すかというテーマなのですが、滝場は「傷つけない笑い」こそ「おもろい以外」であり「いらん」ものと考えます。一方、咲太は「きつめの言葉」や「いじり」こそ「おもろい以外」であり「いらん」ものと捉えています。この対比について、大前さんのお考えが聞きたいです。
大前 どっちかが正しいということを言いたいわけではないです。その上で、違う見解を持つ同士ではっきりと喧嘩させたかったということがあります。
木村 ああ、そうなんですね。
大前 立場の違う者たちが話し合っても、解決はなかなか難しいと思うんですけれど、別に解決しないまま、考えが違うままで、それぞれが協力したり協働したりすることはできるはずで。喧嘩もするけど仲が良いというのは、Twitterとか見ているととても難しくなっているけれども、その分、立場の違う者同士が喧嘩を経てスッキリするというのを見せたかったんです。
木村 なるほど。先日、大学で学生たちと議論している中で、Instagramのハッシュタグ(例えば「#隠しきれないヲタク」)はどのように活用されているかが話題になったんですが、するとある学生が、いくつも並んだハッシュタグは属性を示していて、それを手がかりに自分と強くマッチングする友人を探しているんだ、と教えてくれたんです。そうすると「最適解」の友人ができる。一方、リアルで集うゼミ生たちは、それぞれの研究したいことはバラバラで、だから多様性のある仲間ができるわけで、僕はそれがゼミの良さだと思っていたんだけれど、過不足のない「最適解」の友人ができる可能性によって、立場の違う人たちを〈喧嘩もするけど仲がいい〉仲間にする欲求が生まれにくくなる、なんてことが起きているのかもしれませんね。
大前 特にコロナ禍の中では「違い」が耐えられなくなっているのかもしれません。「違う人」=自分を告発するかもしれない人と捉える、みたいな。二項対立が加速していて、たとえば家族を守らなければいけないといった心情が他者への排斥とつながっていたりもするように感じます。
木村 なるほど。ところで、先ほどの引用部分に戻って、少し咲太の見解に注目してみたいのですが、咲太は「そういう倫理観の変わってく時期なんだから」とか、あるいは「それが時代遅れになったときに」(同上、p. 154)などと言います。ここにあるのはどのような意識なんでしょう。「優しさ」は重要だと倫理観に訴えているというよりは、ひょっとしたら「時流を見て漫才やれよ」といった、芸人としてのしたたかさを友人の芸人(滝場)に勧めている発言のようにも受け取れます。
大前 ここは、コンビにならなかった、外れた者としての咲太がもっている、滝場やユウキに対する嫉妬の気持ちが出ているところなんです。また、ある種の独占欲とでもいうか、滝場やユウキの漫才の客でもある咲太のプロデュース欲も出ていて、客として感じた「容姿いじりはもうおもしろくないよ」という気持ちもありつつ、咲太本人の欲も現れているところなんです。
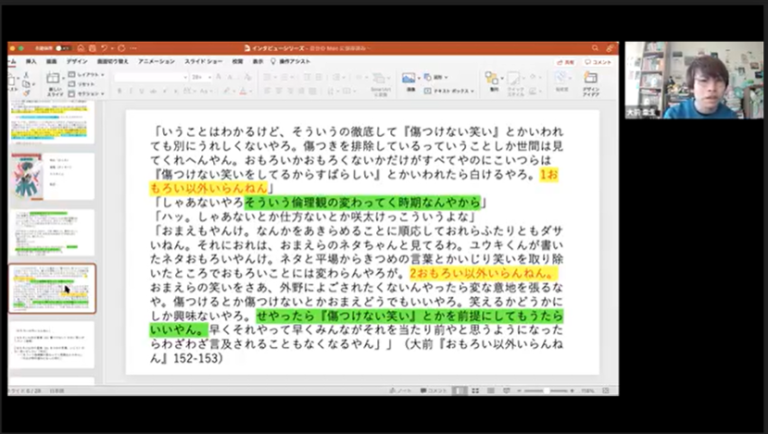
インタビューの様子
木村 これは著者ご本人からそういう言葉をもらえて、発見があります。確かに、読者として読みながら感じていたのは、まさにそうした咲太の揺れる心情ですね。ただ、仮に、そこに一種の芸人論があるとした場合、文中で示唆された「時流」への意識が気になるんです。
例えば先日の「キングオブコント2021」(2021年10月)は、まさに「傷つけない笑い」のオンパレードと感じる部分がありました。ただそれは、芸人が、自分の考える倫理的に正しいお笑いをやろうとした結果なのか、あるいはそうではなく、「傷つけない笑い」がいまはウケるといった仕方で時流を読んだ結果なのか。客に笑ってもらってなんぼな芸人にとって、当然、後者のようなしたたかさは求められるとも思いますが、それが芸人の限界なのかも、という気もします。
大前 そういえばコロナ禍の前、大阪の劇場へ行った時に、ワー、キャー言われることに(芸人が)イラつきながら漫才しているのかなと感じた場面があったんです。客席は圧倒的に女性が多いのですが、舞台上で芸人がわざと女性客を怖がらせるようなふるまいをボケとしてやっていることがあって。お客さんが笑ってくれないと成り立たないというのは、芸人にとってすごくもどかしいんじゃないでしょうか。また、お客さんの笑いに対する好みが以前よりとても複雑になっている現状だと、みんなにウケるようなネタが果たして正解なのか、という問題も出てきているでしょう。だから、いっそのこと誰もが笑える刺激重視の笑いに振り切ってしまう傾向も顕著で、傷つけないことも加味した上で、「パチンコみたいな笑い」が増えているのかなと思います。
木村 中身がなく、ただ刺激だけがある笑い?
大前 前提になるものを必要とせず反射で笑わせるような笑い、でしょうか。前提があると、それを知らない人を排除することになるので、前提そのものを取っ払ってしまおう、みたいな考えがあるのかもしれません。
ネットが浸透した社会と芸術表現のはざまで
木村 ただ、そうした状況は表現に携わる大前さんには受け入れ難いんじゃないですか。読者に一定のリテラシーや知的理解が期待できないという状況が、もし小説の世界で起こったら。
大前 小説の場合、表現形態が「本」なので、読んでくれる人と書き手の間に距離があって、読者の反応が執筆に反映されることはあまりなかったりします。「本」として隔離されていることに安心があるとか、生身の身体で人前に立たなくて良いとか、自分に閉じこもっていても良いとか、という面が本の場合はあると思うんです。
木村 なるほど確かに。でも、そういう隔離の空間って、いまの世の中でめずらしい空間ですよね。ただ、演劇も「劇場」という空間に隔離されていて、チケット代はそのバリアになっていたりしますね。
大前 本を読むことのできる余裕のある人にしか届かない、という問題もあると思います。
木村 閉じ方と開き方、そのバランスの問題でしょうか。それぞれの表現形態の持つ閉じ方と開き方のバランスの中で各自があるべきやり方を探す、ということなのかもしれません。
さて、最後に、小説と差別というテーマに触れてみたいと思います。例えば、1990年代に小説家の筒井康隆が断筆宣言するという出来事がありました。角川書店の発行する高校向け教科書に彼の小説『無人警察』を掲載することに、日本てんかん協会が反対し、一方、筒井はその過程で表現の自由を問題にしたり、ジャーナリズムの対応の不十分さを指摘したりしました。私は、当時これを取り上げた一連の書籍を読む中で、もしこうしたことが現在起きたとしたら、マスコミや出版業界は果たして巻き起こった論争を論争として整理し、議論の場を作るだろうかと考えると、そうはならないだろうと想像して不安になりました。断筆宣言がされた当時は、ポリティカルコレクトネスに対する疑義も噴出していたのですが、いまはそうした疑義も大声では言いにくくなってきています。

木村覚
大前 Twitterを見ていると、人に対して一貫性を求める空気が蔓延しているのかなと思います。人は、完全な善人にも完全な悪人にもなれないと思うんですね。だから多面性を持っているはずなのに、SNSではノイズになるものが剥ぎ取られて、一定の立場に区切られてしまう。差別は悪いことだし炎上して然るべきだけれど、批判と炎上と謝罪の間に、反射的ではない距離がちゃんとあったほうが良いと思うし、それぞれが自分の見解を言い合える場があると良いはずですよね。ちゃんと喧嘩できる場が。
木村 「友」か、さもなければ「敵」、ということで言えば、本当は各自に多面性や個別性があるのに、SNS上のやりとりでは「友」に対して「私たちは100%正しい」と言わざるを得なくなって、本来、友の内部にある多面性・個別性が見えなくなってしまう。
大前 一貫性を保持するために、自分たちのアイデンティティを良くも悪くも強化してしまって、その結果が、管理社会を強化することになっているかもしれません。TikTokなどの中でいうと、人が何かのキャラクターになりきることで、自分を消す快楽を得ているようにも見えます。広義の演技によって、自分という存在が楽になる、というのはあるかもしれません。
木村 小説では喧嘩のシーンも描けますよね。
大前 表現の多様性とポリティカルコレクトネスの考えを対等に語っていいものかどうかと葛藤することは多々あります。表現が規制されることよりも、誰か一人が差別を受けなくなることの方がずっと大事で、そのためには表現なんて重んじられなくても良いのではないか、とさえ思うことがあります。
木村 「表現」ってなんなんでしょうね。誰か悲しい思いをしている人がいたら、その人物とマンツーマンで私たちは接するでしょう。それに対して「表現」というものは、抽象度の高い「観客」「読者」なるものや、あるいは「芸術の神に捧げる」なんて人もいるかもしれませんが、いずれにしても個別的ではない、目の前の人に向けたものではないところがありますよね。そうした「表現」というものの限界に、私たちは向き合わざるを得なくなっているのかもしれませんね。
大前 表現とか文学と同じかそれ以上に、その日の晩ごはんだとか寝ることだとか、日々の糧が重要だと思うんです。
木村 文学は日常生活に比べて崇高なものといった発想を抱くよりも、むしろすべては等価なのではないかというポストモダンな思考の中にいる、ということなんですかね。
大前 だからと言って、誰もが表現者になれるとか、その結果、刺激だけを追求するといったTikTokのような状況は危うい気がして、悩みますね。それって平和な状況かもしれないけど、良くないものを生み出してしまうかもしれないですよね。
木村 わかります。でも、だからといって、例えば1990年代の文学者が言った「清濁併せ呑んだ無差別級こそが文学であり、それをあるがままに受け入れるのが市民社会の度量というものだろう」 というような発言も、いまではリアリティがないわけで。
大前 「清濁併せ呑む」的な作品をしんどいと思う人もたくさんいるんじゃないかなと思いますし、表現なのだから受容しろとは私自身には言えないですね。
木村 表現ではなく「痛み」として受け取ってしまう。まさにベタとメタとが区別できない状況に、いまはなっているということなんでしょうか。
大前 でも、痛み自体によって楽になってくれる人もいると思うので、そういう人の目に自分の表現が入ってくれたらと思います。
木村 なるほど、そう期待したいです。きわめて今日的な表現の問題をいくつも議論できたと思います。ありがとうございました。
大前 ありがとうございました。




