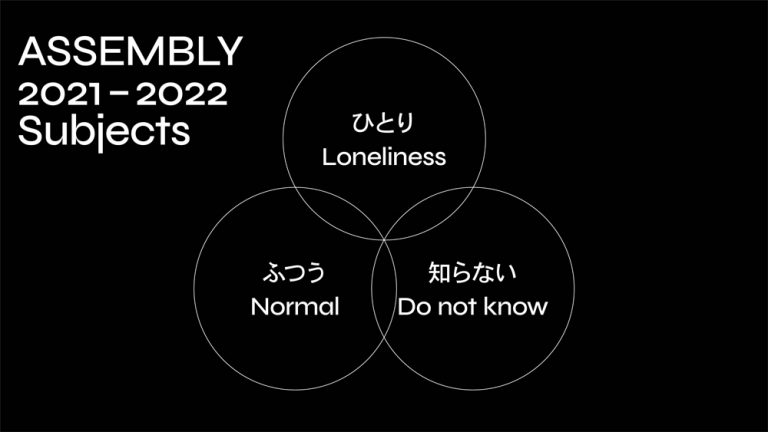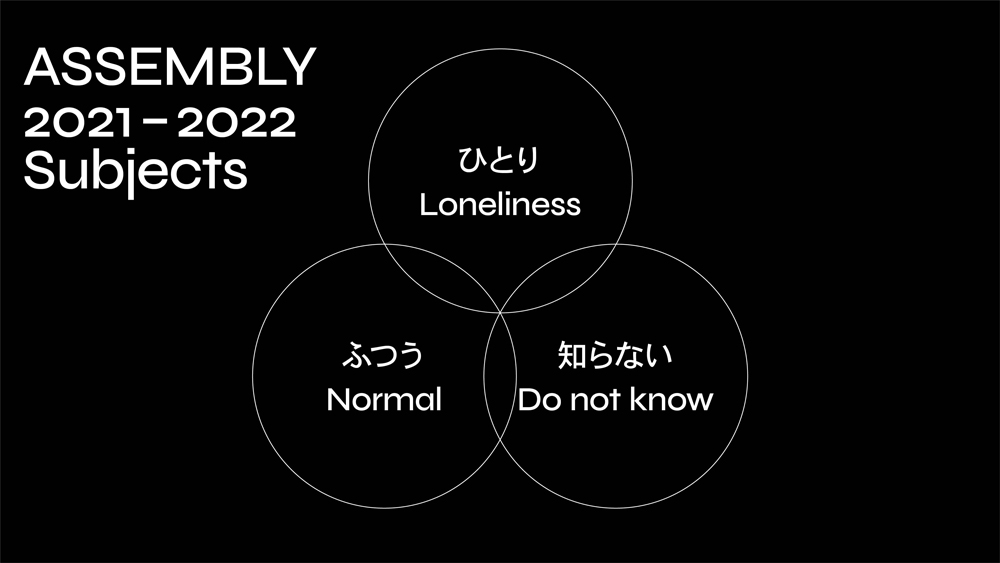私は仕事をする上で何か課題にぶつかった時、上司のあるアドバイスを思い出すようにしている。解決策を導くためには二つのアプローチで考えなさい。一つは現実的な制約を一旦全て忘れ、理想のあるべき姿を想像し、そこへの最短経路を探る方法。もう一つはスケジュールや予算といった現実的な制約から落としどころを探る方法。そしてもちろん大事なのは前者の理想から考える方法だと。このようなアドバイスは仕事では多くの場合、役に立つ。では、政治的な課題となるとどうだろうか。
本トークイベントは2022年1月8日、ロームシアター京都にて[「怒り」と「道徳」の時代に、表現者はどう向き合うのか?]と題し、批評家の綿野恵太、劇作家・演出家の神里雄大の二名がゲストとして招かれた。トークイベントの前半は綿野によるレクチャー、そして後半は綿野、神里による対話という形で展開された。
世界で起きている政治的な分断や対立について
綿野によるレクチャーは著書『みんな政治でバカになる』(晶文社、2021年)での議論を軸としながら、今、世界で起きている政治的な分断や対立について整理していく。
現在、世界中で分断・ヘイト・陰謀論などが後を絶たない。なぜだろうか。人間の認知システムによるものだと綿野は紹介する。二重過程理論と呼ばれる仮説がある。それは人間の認知には異なる二つのシステムがあるというものだ。一つは直観システムと呼ばれ、その特徴は怒りや恐怖など非言語的、感情的な認知の仕方である。もう一つは推論システムと呼ばれ、こちらは文章を書いたり計算をするなど、言語的、意識的であるという特徴を持つ。前者の直観的なシステムのメリットは判断の速さにある。しかし素早く判断してしまうゆえに感情や属性に惑わされ、合理的な判断ができないこともある。つまりバカになってしまう、というわけだ。また、そのような判断の誤りには幾つかのパターンがあり、その思考のパターンのことを認知バイアスと呼ぶ。たしかに、身近な例を考えてみても合理的な判断より道徳的な判断(嫌悪、不快、とっさに他者を助けるなど)が先立つことがある。そして、私たちの生活に直結するような政治の問題においてその認知バイアスから逃れることは、より難しくなるだろう。
その後、綿野は部族主義、道徳部族についての問題を紹介した。部族主義とは、私たちが自分の仲間かどうかを直観的に区別して仲間と認めたものをひいきする傾向のことをいう。この傾向は身内びいき・内集団バイアスと呼ばれる認知バイアスとしても知られる。このバイアスの問題点は「われわれ」(内集団)と「あいつら」(外集団)の差に敏感に反応してしまうことで、ステレオタイプに当てはめたり、敵対視してしまうことにある。また、部族主義の問題は道徳の面においても起こっている。それが道徳部族と呼ばれるものだ。自らが慣れ親しんだ道徳・文化を優先してしまい、他と激しく対立してしまう。哲学者ジョシュア・グリーンはアメリカのリベラル派と保守派の激しい対立を道徳部族の対立なのではないかと指摘した。また、このような道徳部族の対立が厄介なのは、立場に関わらず、事実の認識を歪めてしまうことにもある。例えば、気候変動の問題はフェイクではないかという保守派の主張、左派による放射能の過度な危険性の指摘などが挙げられる。
綿野は人間の認知システムだけでなく、環境について、ここではインターネットの問題についても指摘した。ひとつは集団分極化という問題だ。集団分極化とは同じ考えを持つ人が議論すると、極端な考えに先鋭化する現象のことである。インターネットでは同じ価値観の人たちが結び付きやすいため、過激になっていきやすい。他にも、綿野はSNSでは怒りや道徳に関する話題が拡散されやすいが、それが同じ道徳部族の中にとどまってしまうという問題。感情を動員するポピュリズムとSNSは相性が良いという問題についても指摘した。

綿野恵太
「対話ができる人としか話せない」というジレンマ
以上のような話を踏まえ、綿野と神里は様々な議論をおこなう。SNSにおける自身の著作や作品に対する反応をどう受け止めるかについて。マンスプレイニング(男性が女性に対し、見下した態度で説明すること)やルッキズム(外見至上主義)といった造語の濫用の危うさについて。また、創作環境におけるハラスメントの問題など。その中で私が印象的に感じたのは、コロナ禍における神里の活動の変化についてである。
近年深刻さを増す「分断」について、解決策のひとつは「交流」することにあると綿野は言う。たとえ異なる境遇の人でも実際に話し生活することで、しばしば他者に対するステレオタイプはなくなっていく。神里はペルー生まれという自身のルーツから南米に興味を抱き、親族やその知人を訪ねる旅をした。そのような経験と感じたことを元に演劇作品を発表したり、著書を出したりしている。ただ、現状のコロナ禍では直接現地に赴いて交流することができない。それについてどう考えているのかと綿野は問う。
神里は率直に困っていると答える。表現活動も制限を余儀なくされる状況であり、感情を押し殺した日々を過ごし、創作意欲も湧かないと言う。続けて、現在抱えている創作手法の問題意識についても語った。神里は直接現地に赴いて人の話を聞くという手法をとっていたが、その手法には「対話ができる人としか話せない」というジレンマを感じていたと言う。例えば、神里はスペイン語が流暢なわけではなく、南米での交流も日本語が話せる人に限定されてしまうことや、対話のためにはその場に参加しようという意志が前提として必要であることである。また、創作手法だけでなく、劇場に来る人という時点で観客にフィルターがかかってしまっているのではないか、という環境の面においてもジレンマを感じていたようだ。
神里はそのような問題意識から、別の価値観の人に届くような作品づくりを模索する時期があったそうだ。しかし、現在はそれらについて諦めのような感情があると語り、仲間内で盛り上がり過ぎないことを意識していると続けた。
神里の問題意識は表現活動に携わる者としてはあまりにシビアであるようにも思える。綿野も補足したが、交流によって、別の価値感を持つ人々との相互理解はそう簡単に起こるものではない。しかし、神里は問題に向き合い、葛藤しつづける。私たちは普段の生活でこのような葛藤を持ち続けるだろうか。多くの場合、そもそも問題を見逃してしまうか、気づかないふりをするのではないか。

神里雄大
「異化効果」を用いずフィクションの責任を引き受ける
綿野との対話において、神里はもう一つ別の葛藤についても語る。
綿野は異化効果とよばれる演劇手法が、私たちの無意識的な言動を意識的にさせるという点で、差別批判としても受け取ることができると著書のあとがきで書いている。異化効果とはドイツの劇作家ブレヒトが提唱した演劇手法である。西洋の伝統的な演劇では、観客に対し登場人物に感情移入をさせ、怒りや悲しみといった役が持つ感情を同化させようとする。だがブレヒトは、例えば劇中で内容を知らせるタイトルを出し、あえてネタバレをおこなうことで観客と役の同化を中断させ、眼前で起きていることに対する判断を観客自身に委ねるのである。ブレヒトは異化効果を交通事故の証言に喩えている。役者とは事故の目撃者であり、運転手や被害者の振る舞いを身振り手振りを交えて再現する。このことを踏まえて、綿野は、神里の作品には「目撃者」の証言=再現ではなく、「目撃者の証言」の演技=再現という二重の迂回があると指摘する。つまり、出来事を目撃した人々の証言をさらに役者が再現している、と。
綿野はこのように神里の演出をブレヒトと比較した上で、その手法への考えや背景について聞きたいと問う。神里はブレヒトを意識したことはないが、アルゼンチンの作家ボルヘスが短編集でおこなった、話の細部が作り話かもしれないと冒頭に提示してしまう手法が面白いと感じ、それに影響を受けたことを明かした。ただし、今はむしろ、異化効果に頼らない登場人物が登場人物の言葉を喋る、スタンダードな演劇をやりたいと考えているという。
そもそも神里は人前で俳優が演技をすることの「上手くいかなさ」に対して、観客に判断を委ねる異化効果に近い手法を用い、迂回することに可能性を見出していた。しかし、作品である以上そこには作者の何らかの誘導が存在し、完全に観客に判断を委ねられているわけではない。加えて、異化効果を狙った演出で頻出する、相手役ではなく観客に向かって喋る演技形式の説教臭さにも違和感を持っていたそうだ。だから迂回をせず、フィクションであることの責任を引き受けるスタンダードな演劇をやりたいと現在の神里は考えているのだという。

「解決」ではなく「納得」できるプロセスの重要性
冒頭で私は、政治課題において理想的なあるべき姿から解決策を考える方法、あるいは現実的な制約から解決策を探る方法のどちらが重要だろうかと問うた。先ほどの神里の表現に対する課題設定とそれに向き合う姿勢は、その問いへのヒントを私に与えた。政治的な課題において重要な点は、理想的な解決策というよりも、その課題を深く考えるプロセスにあるのではないかと。
政治的な課題の多くは様々な利害関係を持つことが多く、全員が理想とする結果を得ることは難しいはずだ。だからこそ大事なことは、全員がその問題に向き合い、納得を得ることなのではないか。
神里は自身の演劇手法の限界を考えることで、スタンダードな演劇をやりたいということに着地した。そこでの納得は着地点によるものではなく、葛藤を経たその思考過程から生まれたものであろう。
「プロセスに価値がある」と言われる時、結局のところ、そのプロセスがいずれより良い結果を導くことを前提としていることが多いように思う。しかし私が思うに、プロセスの価値と結果は必ずしもまっすぐに結びつかない。むしろ価値あるプロセスとは、どのような結果であっても納得できるもののことを言うのではないだろうか。
トークイベント全体を通して、活動するフィールドが異なる綿野、神里の視座の違いを感じたことは否めない。しかし、両者に共通する視点もあったように私は思う。それは私たちが見逃してしまいがちな「限界」や「制約」に着目する視点であり、政治的な課題においても有用なヒントとなるのではないだろうか。綿野は人間の本性に関わる認知バイアスという限界から世界の分断を考察することを試みた。一方で、神里は自身の創作手法や演劇手法の限界に向き合うことで、着地点はどうであれ責任を引き受けるという考えに至った。
現在の政治課題について考えを深める時、理想のあるべき姿を追うばかりでなく、限界や制約を見定めるところからスタートするのも肝要なのではないか。そのようなことを私は考えさせられた。