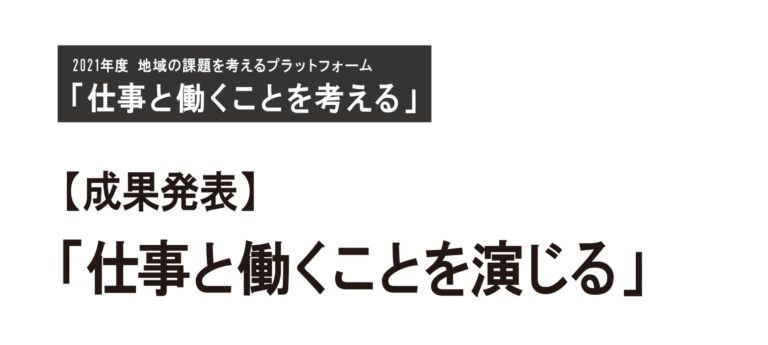「地域の課題を考えるプラットフォーム」は、地域と劇場の双方向的なコミュニケーションをはかることを目指し、ロームシアター京都が 2017 年度から実施しているプログラム。2021 年度は「仕事と働くことを考える」をテーマに、地域社会の中で誰もが関わる「仕事」と「働くこと」を取り上げ、2回のトークセッションと、演出家・映像作家の村川拓也氏による演劇ワークショップを開催した。
今回のレポートで取り上げるのは、2022年1月30日にロームシアター京都ノースホールで開催されたワークショップ成果発表『仕事と働くことを演じる』。ワークショップ参加者がそれぞれの「仕事」にまつわるエピソードを持ち寄って演劇小作品へと立ち上げ、最終日に発表を行った。京都を拠点に活動する文筆家の高橋マキ氏に観劇レポートを綴ってもらった。

撮影:金サジ(umiak)
自分の仕事を舞台上で再現する
「おはようございまーす!」
チン!とベルが鳴ると同時に、蛍光ピンクのスニーカーを履いた女性が舞台に飛び出してきた。足取りは軽やか。どこかに出勤したらしく、実際にはそこにいない同僚と、あいさつのような言葉を交わしながら、キビキビと髪を束ねてポニーテールに結ぶ。彼女は、フィットネスのトレーナーか何か、だろうか――。

撮影:金サジ(umiak)
この日観劇したのは、演出家の村川拓也さんによる1週間の演劇ワークショップの成果発表「仕事と働くことを演じる」。私みたいな「観るだけの人」は、たった数日のワークショップで人が舞台を演じられるようになるなんて到底信じられない、と変なことにドキドキしてしまったけれど、その心配は杞憂。手元に配られたパンフレットによると、ワークショップ参加者、つまり今日の登場人物は5人とも、役者もしくは身体を使う表現者であるらしい。演出家の村川さんからのお題は「今、もしくはかつての自分の仕事を舞台上で再現する」こと。
チン!とまたベルが鳴る。あのベルは、開始を告げる効果音ではなかったらしい。蛍光スニーカーの彼女は、不織布マスクの中でハキハキとセリフを喋りながら、相変わらずひとりでキビキビと動いている。あ、ここはフィットネススタジオではなく、流行りのパンケーキカフェなのか。
会場となったロームシアター京都のノースホールは、ブラックボックスというスタイルの黒いのっぺりとした空間で、今回は照明以外の舞台装置がひとつもない。つまり、彼女がいったい誰を演じているのか、ここはどこなのか、時間は朝なのか夜なのか、未来なのか過去なのか。その手がかりは、ただ彼女のマスクの中で発せられるセリフと身体表現のみ、ということだ。ほぼ1分かけて、私はその手がかりを得た。ここはパンケーキカフェ、彼女はよくできるアルバイト店員さん。
蛍光スニーカーの彼女が「お疲れさまです!」とバイトを終えたあと、入れ違いに登場するのはワンピースの女性。再び出勤シーンから始まる。でも、もちろん、もうここはパンケーキカフェではない。不織布のコート、髪をすっぽりと包んでしまう不織布の帽子を身につけたあと、念入りに手を洗っている。前をジッパーでとめるタイプの不織布のコートは、新型コロナパンデミックになってまもなく医療現場で「足りない」と騒がれたアレだが、ライターとして日々さまざまな現場に取材へ行く私にとっては、あと2つくらい、この装束を身につける職場候補が思い浮かぶ。正解は、食品製造の現場。工場の製造ラインに入った白づくめの彼女の今日の仕事は、ベルトコンベアで次々と流れてくるお節料理を詰めることらしいと、次第にわかる。

撮影:金サジ(umiak)
こうして5人の役者さんがひとりずつ順番に、何もない舞台に現れて、15分ぐらい(基本的に)ひとりで淡々と「働く人」を演じていく。私たち観客は毎回、役者たちが演じる「働く人」のヒントがゼロの状態でのスタートから、次第に状況を把握し、答え合わせができた時点でちょっとニヤリとし、そのあとはお能や落語のように、脳内で勝手に舞台装置を補い始める。
何もない舞台に浮かび上がるのは、カフェ、お節の製造ライン、お酢の製造ライン、図書館、ゴミ収集といった現場と、そこで働く人々。若者たちにとっての「憧れの職業」ではないかもしれないけれど、私たちの暮らしを支えてくれているエッセンシャルワーカーたち。私が月曜と木曜の生ゴミの日に路上に出すゴミ袋は、同じ20リットルサイズなのに、風に飛ばされそうに軽い日も、ずっしりと重い日もある。大掃除をした連休の後は5つも出してしまったりする。そんなどうでもいい日常のどうでもいいシーンが、目の前の空間に立ち上る。彼らは果たして再現しているか、演じているのか。観ている私にとって、それは限りなく、あいまいに思えた。
職場で、家庭で、人生を演じ続ける私たち
さて、このちょっとスリリングな感覚と「働く人」というキーワードを繰り返しているうち、私はぼんやりと懐かしく、20代の頃に何度も観に行った、イッセー尾形さんの一人芝居を思い出していた。イッセーさんが演じる市井の人はみなユーモラスでどこか切なくて、あたかもその人がどこかに実在しそうなほどのリアリティがあったけれど、たしか実際は、彼の鋭い人間観察力から生まれた架空の人物だった。それを思うと、今回の舞台がイッセーさんの一人芝居と一番異なるのは、「役者本人が、役者でない時間の本人を演じている」ということだ。
彼らの日常の中で毎日毎日、何度も何度も繰り返されたのであろうその動きは、舞台の上でもとてもシームレスで、美しいな、と感じる瞬間さえあった。

撮影:金サジ(umiak)
名優と称されるイッセー尾形さんのあの天才的な演技力、再現力を、彼らは舞台の外での経験と習慣で体得してしまっているともいえる。なんだろう、これ。すごいな。でも、皮肉だな、とも思う。なぜなら、もし彼らが舞台の上だけで生きられる役者であれば、経験も体得も、できなかったことだからだ。
案の定、アフタートークで、観覧者から忌憚のない質問が飛んだ。
「私がこの作品にタイトルをつけるとすれば『生きるって、マジ大変』。でも、このタイトルでは誰も観てくれないですよね。俳優さんたちにとって、それを演じるのは地獄ではなかったでしょうか?」

撮影:金サジ(umiak)
役者さんたちの回答は、こうだ。
・最高の仕事だと思っている
・このバイトをしていたから今日の舞台に出演することができた
・演じることを演じているような感覚だった
・嫌で忘れていた仕事を再現したことによって、あの10年が報われた気がした

撮影:金サジ(umiak)
興味深かったのは、「最高の仕事」と答えたのがゴミ収集作業員、「嫌で忘れたかった仕事」と答えたのは、元・図書館司書だったことだ。


撮影:金サジ(umiak)
夢のある仕事、夢のなさそうな仕事。
憧れの仕事、あんまり憧れてもらえなさそうな仕事。
やりたい仕事、向いてる仕事。
クリエイティビティが必要な仕事、クリエイティビティが必要ない仕事。
やり甲斐があるけど低賃金な仕事と、やり甲斐なんて感じないけど割りのいい仕事。
毎日が刺激的な仕事と、ルーチンワーク。
ライフワークとライスワーク。
子どもの頃、あるいは学生時代、仕事を選ぶときに私たちはそんなことを何度考えただろうか。そこに答えはあっただろうか。そして、この度の未曾有のパンデミックで「不要不急」の烙印が押された仕事と、エッセンシャルワークの境界線は、いったいどこにあるのだろう。そもそも、そんな境界線なんて、存在するのだろうか。
「仕事ってなんだろう」「働くってどういうことだろう」
誰もが一度は、あるいは何度も何度も考えるシンプルな問いの向こうで、揺らいだりねじれたりしながら、私たちの生きている社会は繋がっているのだ。

撮影:金サジ(umiak)