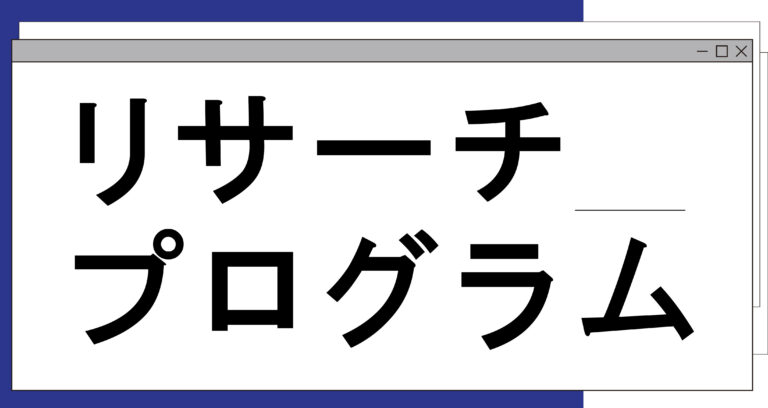初出:機関誌ASSEMBLY第三号 [特集]子ども/子供/コドモを考える(平成31年3月31日発行)
ロームシアター京都では、2016年のリニューアルオープン以前のオープニング・プレ事業から子どもを対象とした事業を行ってきた。本稿では、それらの紹介を通して、今後の劇場と子どもたち、そして周りの大人たちとの関わりを展望する。
「対話」と「双方向性」
子どもの声を聴くこと、
子どもと大人がともに考えること、
新たな発見をすること。
これは、ロームシアター京都リサーチプログラム、2017年度「子どもと舞台芸術」のリサーチャー、大野はな恵・浜上真琴・清水久莉子が報告書[*1]に記した劇場に対する提言である。
大野は、子どもにとっての「居心地のよさ」こそが劇場と子どもをつなぐ基盤になるのではないかとし、そのためには、子どもが何を求めているのかを正しく把握し、彼らの意見を取り入れること=「子どもの声を聴くこと」の必要性を述べた。
浜上は、子どもと大人という関係性に大きな変化を起こさせるには、「子どもと大人がともに考えること」と、自由な対話や議論によって関係性をつくる「社会的相互作用」が重要であるとした。
清水は、ロームシアター京都を訪れる人々へのインタビュー調査と「公共劇場の公共性議論」を参照することにより、「自分ではない誰かの環世界」で「新たな発見をすること」が、これからの劇場の役割の一つとした。
彼女たちのさまざまな角度からの言及により、「対話」と「双方向性」というキーワードを導き出すことができる。これからのロームシアター京都の子ども向けプログラムの目指すべき方向性を鮮やかに提示してくれたと思う。
本物との出会い、舞台芸術の入り口
「おーい、おーい!」と小澤征爾の軽やかな挨拶で始まった、ロームシアター京都オープニング・プレ事業、小澤征爾音楽塾による子どものためのオペラ『子どもと魔法』 [*2]。小澤征爾音楽塾は、小澤がオペラを通じて若手演奏家の育成を目的に立ち上げたプロジェクトで、現在の制作拠点であるロームシアター京都では、本公演を行うと同時に、2015年以降は、京都の小学生を毎年3,000人以上招待し、子どもたちのための特別版オペラを上演している。小澤の楽しいトークや楽器紹介から始まり、オペラの生の迫力を体験した子どもたちは、大きな歓声をあげる。
もう一つ、プレ事業から継続しているのが、高校生のためのオペラ音楽セレクションを皮切りに始まった「新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室」である。『蝶々夫人』(指揮:高関健、演出:栗山民也)や『魔笛』(指揮:園田隆一郎・演出:ウィリアム・ケントリッジ)といった、新国立劇場が第一線のアーティストと制作したオペラをそのままに、高校生が一般の観客と同じスタイルで鑑賞する機会を提供している。
このふたつの事業では、上演・制作団体と連携し、高い水準の上演をそのまま子どもたちに届けることによって、劇場だからこそ可能な本格的なステージと出会うことを大切にしている。彼らの大多数にとっては、これらが舞台芸術の入り口になっている。

ローム クラシック スペシャル 小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトⅩⅢ 子どものためのオペラ 歌劇「子どもと魔法」(2015年3月)|©大窪道治
とにかく一度、劇場へ
異なるアプローチで、「とにかく一度、劇場に来て欲しい」という思いを込めて立案してきたのが「プレイ!シアター in Summer」である。「劇場で遊ぼう!」を合言葉に、館内のほとんどを使用し、演劇仕立ての劇場ツアー、踊って飛び回れるこどもディスコ、楽器体験やマルシェなどを行う。客席に座って舞台を鑑賞するのとは違う、劇場の普段と異なる顔を発見し、家族や友だちと、あるいは、一人でも気軽に立ち寄ってもらうことを目指している。
子どもたちの元気な笑い声(時には叫び声や泣き声も……)が溢れるこの期間は、劇場にいつもとは違う風景が浮かびあがる。年を経るごとに来場者数は増え、我々の考える以上に、子どもと大人が一緒に楽しめる場への希求の強さを実感している。
2018年からは、京都市交響楽団によるコンサートやアクラム・カーン振付作品といった、鑑賞型プログラムも組み入れている。さらに19年は、ロームシアター京都だけでなく、当財団[*3]が管理運営する京都市内の5つの文化会館でも乳幼児向け舞台を上演する。ゆくゆくは、子ども向け作品をプロデュースし、京都発の
オリジナル作品を子どもたちに見てもらいたいと考えている。

プレイ!シアター in Summer ユリイカ百貨店による劇場ツアーの様子(2017年8月)©Takuya Matsumi
未来の舞台人 次のチャレンジへ
対象者[*4]は「子ども」の範囲を越えてはいるが、京都市東山青少年活動センターと共同企画・主催している劇場の仕事体験プログラム [*5]も紹介しておこう。この講座では、座学と現場での実習を織り交ぜ、観客席から見える部分だけでなく、劇場にはいろいろな仕事があり、多くの人たちが働いていることを知ってもらうことを企図している。ここから、将来自分たちと働くかもしれない仲間が出てくれることを期待している。
そして、2019年度からは中高生向けの事業「劇場の学校プロジェクト」が始動する。演劇/舞踊/メディア・パフォーマンスの3コースを擁し、俳優、ダンサー、演出などを予め細分化するのではなく、総合的な知識を学び、次第に専門性を高めていくようなカリキュラムをつくり上げる試みだ。19年は試験的にそれぞれ
のコースの短期ワークショップ、舞台芸術の人材育成に関する研究会を立ち上げ、次年度以降の本格的なスタートに備える。
このプロジェクトの趣旨や対象者を考えるなかで逡巡したのは、日本では幼少期のお稽古事として始める人の多い舞踊において、中高生の段階ですでに技術的な個人差が大きいことをどのように考え、募集内容を設定するかだった。講師の一人であるダンサーの木田真理子に相談したところ、彼女は迷いなく「『ダンス経験は問わない』がいい」と即答した。中高生が、技術面ではまだ追いつくことのできる年齢であることも理由であったが、それよりも経験や技術差も踏まえ、多様な人材が集まることには大きなメリットがある。そうすることで、それぞれが影響を与え合い、刺激的な場が生まれるだろう、というのが木田の考えだ。世界を舞台に活躍してきた彼女自身の経験から出た言葉には強い説得力があり、この言葉は我々の行き先を示す羅針盤にもなった。新しいプログラムを考えようとしていたにもかかわらず、やはり既存の枠組みにとらわれていたのかもしれない。学校や劇場、大きく言えば、社会に既に存在する価値観やフレームをどのように乗り越えていくことができるのか。我々にとってのチャレンジが始まる。
劇場が必要な存在となること
最初のリサーチャーの提言にあったように「対話」と「双方向性」を常に中心に据えて、これからの子ども向けのプログラムを試行していく。企画側で考えて、あらかじめ道筋をつくってしまうようなものではなく、アーティストや講師、そして何より参加してくれる子どもたち(できることならば、参加をしなかった子どもたちにも)、その周りの大人たちの意見を聞きながら……。子どもたちを一方的に「教育」「育成」するのではなく、大人たちも子どもたちに学び、お互いによい関係性を結んでいく場を保ちたい。
我々には、なにより、劇場という子どもたちと出会い、考えるための「現場」がある。立地や建物の開放性もあり、ロームシアター京都は日常的に人々が集まる場になりつつある。もちろん、子どもたちもやって来る。公演やプログラムに参加してくれる子もいれば、劇場とも知らずにやってくる子もいるが、ここに集う子どもたちに、どのような環境を準備することができるのだろうか。どのような接点を持つのか、あるいは、そっと見守るのか。これからどんなことを一緒にやっていくことができるのか。劇場は、慣習や既存の価値観、学校教育における基準以外の判断や評価を行うことのできる、あるいは、判断も評価も必要としない場所になり得る可能性がある。子どもたちに、いま見聞きしたり、味わったり、感じたりしている以上の、広い世界・深い日常があることを伝えたい。そして、子どもたちの世界や日常のことを彼ら彼女らから教えてもらいたいと思う。