演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当て、2021年に始動した講座シリーズである。2年目となる2022年度の最終回は、「宝塚歌劇」をテーマに2022年11月30日(水)にロームシアター京都サウスホールで開催された。ゲストに、宝塚歌劇屈指の脚本・演出家として、ロマンや哲学性に富んだ作品を手掛けてきた上田久美子氏、近代日本演劇歴史の研究者である松本俊樹氏を迎え、2024年に創設110年を迎える宝塚歌劇の歩みとその魅力、さらに、多くの観客を虜にしてきた上田作品の独創性に迫った。本講座初の3部形式で行われ、第1部は松本氏のレクチャー、第2部は上田氏と木ノ下氏の対談、第3部は三者によるクロストークが行われた。
第1部:松本俊樹氏レクチャー
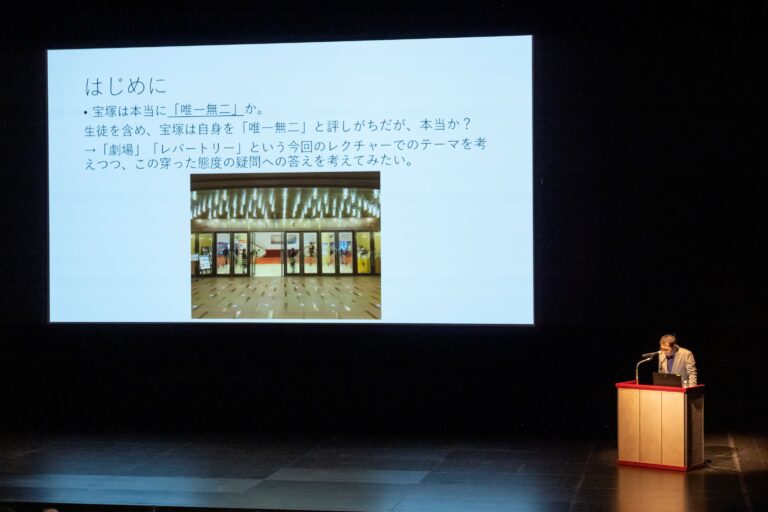
松本俊樹氏 撮影:桂秀也
『宝塚は「唯一無二」か ―同様の芸能の中の宝塚の位置付け―』
第1部では、戦前の宝塚少女歌劇を中心とする近代演劇史の研究に携わってきた松本俊樹氏のレクチャーを通して、宝塚の愛称で親しまれる「宝塚歌劇団」の歩みを、同時代の少女歌劇や宝塚の劇場構造、レパートリーの特徴をひもときながら振り返った。その上で「宝塚の独自性とは何か?」「当初から唯一無二の存在であったのか?」という問いに迫った。
まずは成り立ちだが、周知の通り、宝塚歌劇団は阪急電鉄の一部門である。創設者は阪急グループの創設者である小林一三。1913年(大正2)に「宝塚唱歌隊」という名で産声をあげた後、「宝塚少女歌劇養成会」と改名。翌年の1914年に箕面有馬電気鉄道(現在の阪急電鉄)の沿線開発によって誕生した「宝塚新温泉」の集客の一環として初公演が行われた。松本氏によれば、当時の団員は少女で構成され、家庭本位の娯楽であったという。また、これ以前から大手百貨店などが少年・少女の音楽隊を有しており、この時点では、宝塚の存在は決して珍しいものではなかった。
やがて、宝塚は本格的な学校制度に運営体制を変更し、1919年(大正8)に宝塚音楽歌劇学校を設立。この頃から小林一三は「少女歌劇を元にした“国民劇”の確立」を主張しはじめ、西洋音楽を取り入れた音楽劇を展開していく。さらに小林は、社会的使命として大人数を収容する巨大劇場を建設することで鑑賞料金を下げ、観劇を大衆化することを目指していた。
1924年(大正13)、満を持して4000人を収容できる宝塚大劇場(初代)が完成すると、現在の宝塚の代名詞ともいえる「レヴュー」が日本で初めて導入された。フランスを筆頭に当時の海外で大流行していたレヴューは、「歌や踊りに時事風刺劇を組み合わせたショー」のこと。日本初のレヴュー作品である岸田辰彌『モン・パリ』(1927)を皮切りに、白井鐵造の『パリゼット』(1930)などヒット作を連発し、日本の舞台芸術界に革新をもたらした。やがて、他の少女歌劇団(大阪松竹歌劇団[現OSK、大阪で1922年創設]、松竹少女歌劇団[東京で1928年創設など])もこれに倣うようになり、レヴュー全盛期に突入していった。
スターシステムを輝かせる専用劇場
続いて松本氏は、宝塚が自前の劇場を有していることで、劇団の特性を活かした公演ができることにふれた。現在の宝塚が運営する劇場は「宝塚大劇場」「東京宝塚劇場」「宝塚バウホール(小劇場)」の3館。構造上の特徴は大きく二つあり、①舞台の間口が広く、奥行きが狭いこと、②「銀橋(ぎんきょう)」と呼ばれるエプロンステージが存在すること(※宝塚大劇場、東京宝塚劇場のみ)。①の利点は、宝塚の特徴である大かがりなショーやレヴューを上演する際、きら星のようなスターの姿を客席から視認しやすい点にある。デメリットは、奥行きが短いため、大掛かりな舞台装置の転換に向かないこと。松本氏は「宝塚のミュージカルがどこかレヴュー的なのは、舞台装置の構造とも関わりがあるだろう」と指摘した。さらに、「間口が広い舞台は、歌舞伎の舞台を彷彿させる」と松本氏。これは創設当初の小林一三が、国民劇のありようとして歌舞伎を参照していたこととも関わると述べた。
②の銀橋は、オーケストラピットと客席の間に張り出した弓形のステージのこと。スターたちによるレヴューを特徴とする宝塚には必要不可欠な存在で、これによって観客は憧れのスターをより間近で鑑賞できる。さらに松本氏は、これら2つの特徴は今でこそ宝塚特有のものとされるが、①についてはレヴュー全盛期の1920〜30年代の日本で、②は同時代の世界の商業演劇やレヴューの現場で広く流行していた構造であったことに言及した。つまり、レヴュー劇場が時代と共に淘汰されるなか、宝塚だけがその構造を継承し続けてきたことで、ついには「宝塚ならでは」といえる特徴になったのである。

宝塚大劇場の銀橋 写真提供:松本俊樹氏
レパートリー:流行に敏感であり続けた宝塚歌劇団
「宝塚の公演システムも非常に特徴的である」と松本氏。そのひとつが、座付き演出家によるオリジナル作品の「新作主義」を基本に掲げていること。そして、宝塚と東京の主劇場で5組(花、月、雪、星、宙)が順番に公演していくため、各組の公演期間は約1か月と比較的短い期間となることも特徴だ。もちろん人気演目は何度も再演されているものの、専用劇場を持つ海外のカンパニーが「ロングラン」や「レパートリーシアター」の形式[*注1]を採用し、長期間上演することで少しずつ人気を博し、利益を上げていくビジネスモデルとは大きく異なっていることが分かる。
また、原作がある作品が比較的多いことも、初演以来の宝塚の傾向であると松本氏。その幅は広く、マンガや文学から、映画、海外ミュージカル、京劇まで(宝塚の金字塔となった『ベルサイユのばら』は最たる例)。強固なスターシステムが確立された現在は興行的な心配がないとはいえ、既に人気があるコンテンツに材をとる、流行に敏感な側面があることを指摘した。
さらに松本氏は、この「流行に敏感な傾向」は、戦時下のプロパガンダ作品の上演でも発揮されていたと指摘した。宝塚は海軍宣伝部の松島慶三と関係が深く、松島原作の国策協力作品を多く上演している。小林一三が第2次近衛内閣で商工大臣を務めていたことも影響していたであろう。松本氏は、他の少女歌劇団も一様に国策協力に積極的だったことにもふれ、「少女歌劇やレヴューは当時の最先端であったからこそ、時代の流れ、時局にも敏感であり続けたのだろう」と述べた。
最後に、「宝塚歌劇は本当に唯一無二のものか?」という問いに戻った松本氏。その答えには「宝塚の継承性」が大きく影響しており、1920〜30年代に流行した少女歌劇やレヴュー、劇場構造を、宝塚だけが部分的にアップデートしながら今日まで守り伝えてきたことで、ついには「独自性」となり、磨き上げられたと結論づけた。また、創設以来100年以上にわたり国民に愛されてきた宝塚歌劇は、「既に継承すべき伝統芸能になっているといえるだろう」と語った。
第2部:対談 上田久美子氏×木ノ下裕一氏

左から木ノ下氏、松本氏 撮影:桂秀也
『ここが胸熱、上田作品! —記憶に残る名作を徹底解説—』
第2部では、2022年3 月の宝塚退団まで珠玉の人間ドラマを次々と生み出し、ダイナミックな演出と感情を揺さぶるストーリー展開でファンを魅了し続けてきた上田久美子氏と、熱烈な上田ファンを自称する木ノ下裕一氏の対談が行われた。「ここが胸熱、上田作品!」と題し、木ノ下氏の専門である古典を題材にした3作品をピックアップし、その魅力を本人の前でプレゼンテーション。上田氏ご本人からも創作の裏話や、物語に秘めた真意を語っていただいた。
■『月雲の皇子(つきぐものみこ)』2013年 月組・バウホール公演
古事記の「衣通姫(そとおりひめ)伝説」を題材にした本作は、上田氏が宝塚演出家デビューを果たした作品でもある。原作で描かれるのは、允恭天皇の皇子と姫君(衣通姫)が禁断の愛を交わし、流刑地で心中するという悲劇。二人が交わした歌のなかで話が展開していく「歌物語」の形式をとるのも特徴だ。木ノ下氏はまず、原作が近親相姦というタブーを扱っており、かつ演劇に展開しづらい短い歌物語であるにも関わらず、上田氏の大胆な翻案と宝塚らしいミュージカル性によって、壮大な歴史物語として見事に昇華されていることに言及した。
また、本作の根底には歴史における「ことば(記述)の起源」というテーマがあると木ノ下氏。ことばや文字には2つの役割があり、ひとつは歴史の勝者が紡ぐ「正史」(国家の公式記録で、自らの権力を正当化するもの)、他方は、正史からこぼれ落ちた人々の感情や想いを描く「物語」。劇中ではこの2つと呼応するように、武力と文化、兄弟による皇位継承争い、ヤマト王権と先住民(土蜘蛛)との戦いが描かれていく。加えて「エンディングの演出が素晴らしい!」と木ノ下氏。ナレーションで古事記の衣通姫伝説が語られ、その編纂の物語として帰結していくのだが、「物語の誕生を物語で伝えるメタ的視点が面白い。古代史と現代を巧みに接続する効果もある」とうなった。
[上田氏への質問]
——原作が近親相姦を扱っている本作も含め、上田作品では臆せずタブーに飛び込んでいく印象があるが、偶然か意図的か?
上田:タブーと言われる原作を元にした作品があるのは、ただの偶然だと思っている。『月雲の皇子』についていえば、古事記のあらすじは知っていたものの、衣通姫伝説はインターネット上の物語要素辞典で見つけたものだった。台所を見せると夢がなくて申し訳ないのだが……。他の作品も偶然の出会いから興味を持ったものに過ぎない。ただし、自分は「タブーとされていること自体、そもそも疑わしい」と思っている人間。現代の価値観で禁忌とされているだけで、元はそうでもなかった可能性もある。日頃からこうしたスタンスでいるので、そもそもタブーであろうがなかろうが、あまり気にならないのかもしれない。

上田久美子氏 撮影:桂秀也
——タイトルの月雲には、ヤマト王権に蹂躙された「土蜘蛛(土着の豪族)」がかかっている。衣通姫を実の妹ではなく、土蜘蛛の血を引く戦争孤児の設定にしたのはなぜ?
上田:大きく2つあったと記憶しており、ひとつはヤマト王権と土蜘蛛の対立の話にしたので、恋に落ちる二人は別の種族がよいだろうと思ったこと。もう一つは、木ノ下さんがおっしゃる通り、この作品には「ことば」という主題がある。ことばや文字は、歴史上の権力の所在や政治経済について記すために生まれたが、いつしか人は、個人的な想いや愛、感傷を書きとめ、美しい歌や物語を紡ぐようになった。個人的に「一体誰がいつ、どんな瞬間に想いを文字で残そうとしたのか」ということに興味があり、その瞬間を作品にしたいと思った。ここに近親相姦が入ってくると複雑になるし、それが主題ではないので、自然と切り離すことにしたのだと思う。
——結果として古代史と恋物語、物語の起源が融合した、哲学的なストーリーになっているのが素晴らしい。
上田:感情にまつわる記録を残した歴史的な瞬間を描くため、日本に文字が伝来した5世紀頃の物語を探していたところに、運良く同時代が舞台の衣通姫伝説と出会えた。読んでいくと恋物語ではあるものの、兄弟が巻き込まれた権力争いの果ての話でもあった。ならば、兄は歌を詠む心やさしい人物に、弟は権力を追い求める合理的な人物にすれば、恋のライバルにも、臣下を二分する皇位継承争いの話にもなり、かつ物語の起源を描くことができるだろうと思った。2つの話の種がうまくドッキングしたおかげだと感じている。
■『星逢一夜(ほしあいひとよ)』2015年雪組公演
本作は、岐阜・郡上八幡で江戸中期に起きた百姓一揆(宝暦4年/1754)に着想を得た物語。主人公のモデルは、この一揆の責任を取り、お家断絶となった藩主・金森頼錦。頼錦は星好きで天文台を建てたことでも知られ、劇中でも「星」や「天体」は主人公・晴興が夢中になる対象として、晴興と身分なき里の娘との離別を宿命づける象徴として描かれる。
木ノ下氏は本作のテーマを「権力と民」とし、宝塚で華のない百姓一揆を描こうとした上田氏の度胸、そして劇中で「大きなもの(権力)」と「小さなもの(民)」を象徴するさまざまなモチーフが登場し、その対比が見事に効いていることを絶賛。時代や身分制度による断絶や哀切を、美しくも鮮やかに描き出す装置となっていることを示唆した。
具体的なモチーフの例として、「宇宙と人間」「中央と地方(江戸幕府/九州の小さな三日月藩)」「富士山と星見櫓(江戸から見える大きな山/里から見える高い存在)」などを挙げ、「星座と流星(規則性を持って動く存在/燃え尽きて消えていくもの)」には宿命に翻弄された登場人物たちのメタファーを感じたと木ノ下氏。さらに、藩による農民圧政の背景には享保の改革があり、実は「農民と国家の闘い」である点にもスケールの大きさを感じたと語った。

木ノ下裕一氏 撮影:桂秀也
[上田氏への質問]
——物語を着想したきっかけは?
上田:郡上の鍾乳洞を訪ねた際に、郡上八幡城に立ち寄ったこと。そこで天文学が好きな殿様がいたが、藩の足元まで見ることができず、ついに叛乱が起きた話を知った。特に「殿様が星を見ている」ということをロマンチックに感じ、彼ならリベラルな視点を持っているのではないか? 身分が違う農民とも仲良くなれそうだが、そこからどんな葛藤が生まれるだろう? と話を膨らませていった。宝塚で一揆を取り上げるのはどうかとも思ったが(笑)、タカラジェンヌならどんなテーマでもカッコよく演じてくれるだろうと思った。
——天体と人間、中央と地方などモチーフの対照的な描き方が素晴らしい。どのように創作していったのか?
上田:特に計算はしておらず、感覚的に湧き出たものを拾い上げていった記憶がある。江戸時代の人々は限られた世界で生きていると思っていたが、郡上のエピソードと出会い、より遠くの世界(宇宙)を見ようとした人がいることが素敵だと思った。だから、子ども時代の主人公たちなら、村に建てた小さい櫓から「山の向こうの星が見えるかも」「富士山も見えるのかも」と、遠くにある不確かなものを想像する心を持っていただろうと。現代の私たちも近視眼的な問題に囚われがちだが、あるかないかわからない「遠くのもの」を想像したり、見ようとする心を持っていたいと思う。こうしたことに自分自身の憧れがあり、作品につなげていった。
——上田さんの作品には、現代の私たちが共感できる接続点が必ず設けられている。この作品では、どのような意識をされていたか?
上田:作品を見た方に「まさに、中間管理職の悲哀だよね」と言われたが、実際にそこを意識して書いていた。この話は、たまたま出世してしまったおじさんの悲哀そのもの。私は宝塚入団以前、企業の人事部で給与に関する仕事していたが、そのときに会社の利益と社員の幸せを守ることは、相反するものだと悟ってしまった。こうした点に共感していただけたのかもしれない。
■『桜嵐記(おうらんき)』2021年 月組公演
本作は、南北朝時代を舞台にした軍記物『太平記』に取材した作品。南朝に仕えた楠木正成公の嫡男で、義と優にあふれた青年武将・楠木正行(まさつら)の刹那の恋と、北朝との戦いで散っていった最期を描いている。艶やかに舞い散る吉野の桜の情景が胸に沁み、ここに本作が退団公演となった月組トップ珠城りょうさんを重ねたファンも多かったことだろう。
2つの皇統が存在した南北朝時代とこの時代を描いた『太平記』は、一般的には扱いづらい印象があると木ノ下氏。事実、南朝に忠義を貫いた楠木一族の物語は戦時中に「忠君愛国の模範」とされたが、ここでも上田氏はひるむことなく、独自の翻案による正行像を描き出している。奇しくも紹介した3作品とも「戦い」を描いているが、前述の2作品は「戦う目的」が明確であるのに対し、「本作では主人公が戦って死ぬ意味を探し、苦悶する点が異色である」と木ノ下氏。その救いのなさが現代性を感じさせると語った。また、正行が「過去の負を清算し、南北朝を統一したい」と願いながらも、前世代の亡霊や呪めいた遺言に苛まれるシーンにも言及。過去の国家や天皇制をも問う作品として読み解くこともできるのではないか、と語った。
[上田氏への質問]
—『太平記』のエピソードを描いたきっかけは?
上田:自分が奈良出身なので、南朝があった吉野には幼い頃から何度も行っていて親しみがあり、名所で数々のエピソードを目にしていた。主人公に楠木正行を選んだのは、美男子と謳われ、宝塚にぴったりの悲恋の物語がある人だったから。もちろん、勝ち目がないと分かっていながら四條畷の戦に出陣した正行の真意を「忠義のため」と描くのは、プロパガンダや特攻隊を思い起こさせ、観る人も共感できないだろうと思った。だから、そうではない世界を描くために「当時の人々が何を思って生きていたのか?」「彼らが抱いたであろう葛藤のなかで、現代を生きる私たちに通じているものは何か?」 を掘り下げていった。ここから、今の世に提示して意味がある部分を掬い上げた結果がこの作品だと感じている。
木ノ下:劇中に登場する「大きな流れ」というキーワードが印象的だった。正行自身も「私は大きな流れのために死ぬ(自分の命を使う)」という意味のセリフによって、それは天皇への忠義でも家名のためでもなく、もっと違う大きなもののためだと語っている。それが何かは具体的には語られず、解釈の余地があるが、正行が「もはや流れに抗えない」と悟り、死に向かいながらも懸命に生きる姿には心を打つものがあった。一方、正行の故郷・千早赤坂に伝わる民謡の歌詞からは、強く現代性を感じた。「みんなで大きな楠の木の下に集まれば、地震も雨も怖くない」という意味だったと思うが、この歌詞と、理不尽な死を受け入れて突き進む正行の姿、さらには、現代でも避けては通れない災害に直面したときの私たちの姿が重なるような気がした。実際にこの作品はコロナ禍下で上演されており、「抗えない人生」という意味で多くのことを感じさせられたように思う。
上田:ご指摘の通り、主人公の正行には通常のヒーローとしての「戦う目的」がない。なぜかわからないのに、理不尽な死に向かっていく——。これを不条理と感じる人もいるだろうが、私には「人生とはそういうものだ」という思いがある。この世界の誰もが生きていくために仕事を得て、日々の暮らしを紡いでいる。そのなかで何かやりがいのようなものを見い出し、人生を終えていくのだと。正行の人生も同じで、運命に翻弄されているようで、実は普通のひとの普通の人生に近いのではないか。一般人の私たちには「自らの死で革命が達成される」ようなドラマは決して起こらない。死ぬまでに与えられた人生で、快楽を追い求めるのか、世のため人のために尽くすのかという選択肢があるなかで、正行は後者を選んだに過ぎないと捉えている。
——これまでの創作で「テーマ性と娯楽性のバランス」をどのように意識してきたか?
上田:基本的には、「宝塚としての娯楽」をつくる意識で制作してきた。ただし、娯楽といえども登場人物の言動にリアリティがないと、役者が納得して演じることができない。登場人物の行動には「こんな意味がある」「思いがある」と理解した上で、役者から出てくるエネルギーはすさまじい。そのための骨となるよう、人物の言動や動機にそれなりの意味やテーマを織り込んできたつもりでいる。
第3部:クロストーク 上田久美子氏×松本俊樹氏×木ノ下裕一

撮影:桂秀也
第3部では、第1部のレクチャー、第2部の対談を元にクロストークが行われた。この日語られたトピックやキーワードをさらに掘り下げ、宝塚のメンタリティ、表象、批評性にも話が広がる濃密なひとときとなった。
——『桜嵐記』の楠木正行の本心について:
松本先生はご自身の論文で、宝塚作品における楠木正成の描き方が、時代によって異なることを指摘されている。この流れのなかで『桜嵐記』を鑑賞した時、どんな感想を持たれたか?(木ノ下)
松本:『桜嵐記』で楠木正行が命を捧げた「大きな流れ」を、私は「公共性(みんなのために)」という意味に捉えた。だが、公共心は時として「共同体への忠誠(愛国心)」と紙一重の部分もあり、上田さんの創作意図を知りたいと思った。運良く打ち合わせ時にご本人から、正行が目指した公共性は「民のため(民がお腹を満たし、生きていくことのできる社会)」とお聞きでき、そうかと腑に落ちた。一本強い芯があって描かれると、同じ『太平記』でも新しい解釈ができるのだと感じた。
木ノ下:松本氏の視点は、「古典をどう読むか?」という問いに近い。『太平記』は時代によってさまざまな読まれ方がされており、忠義の物語、国のイデオロギー、愛国思想の模範とされた時代も。その上で、現代の文脈における「新しい読み方」を提示したのが『桜嵐記』であったと思う。
——戦時中の宝塚作品について:
松本先生にお聞きしたい。戦時中の宝塚は時局を色濃く反映した作品を多く上演していたが、これらの作品には娯楽性はあったのか?(木ノ下)
松本:当時の作品ラインナップを見ていると、国策協力作品から娯楽性が大きく切り離されることはなかったと感じている。1938年には座付作家の岸田辰彌による『満州から北支へ』という、レヴュー作品も発表されていた。国の要請もあっただろうが、大衆娯楽として「時局物が流行るから創作する」という能動的な側面もかなりあったのではないか。個人的には「宝塚は戦争に加担させられた被害者」という、一面的な見方は違うのではないかと感じている。

撮影:桂秀也
——宝塚におけるイノセンス:
普通のドラマでは泣けない演目が、宝塚だと「無性に泣ける」現象があるのはなぜだろうか?(木ノ下)
上田:確かに、普通の男女が演じる純愛ものより、宝塚の純愛ものを観た時の方が目頭が熱くなる。宝塚には「ピュアさがある」と評されることもあるが、一般に「ナイーブ(稚拙、幼稚)」と評されるものが、宝塚で演じた時に長所になるのは興味深い。
松本:実は、宝塚は黎明期の頃から「無邪気さ」を売りにしていた。「イノセンス(純真さ、無垢さ)こそが宝。それがなくなったら宝塚は滅びる」、「入団した頃は子どもらしくて良いが、在籍しているうちに大人になり、ケレン味が増すのはよくない」と評されたこともある。少女歌劇であった当初とスタイルは違うものの、現在の宝塚にもある種のイノセンスが継承されていることに驚かされる。
上田:創設時からイノセンスが重視されていたとお聞きし、なるほどと思った。宝塚の団員は、早くから親元を離れて女性だけの集団生活に入るので、独特のメンタリティを保ちやすいのかもしれない。この話は、今日の松本先生の講義とつながる気もしている。広い間口や奥行の狭さ、歌舞伎的であることなど、古い時代の様式美が宝塚でガラパゴス的に守られてきたことも、イノセンスを含めた宝塚の不思議な魅力に影響していると感じた。
——今後の宝塚について:
宝塚にいま課題があるとしたら、それは何か?(木ノ下)
松本:興行面でいえば、あまりに成功しすぎているため、チケットがすぐに即売してしまうこと。私設ファンクラブなどのルートもあるが、初心者が気軽にアクセスするのはむずかしい。ジェンダーなどの表象面でいえば、女性だけで男役と娘役を演じるため、ステレオタイプ的に性差を強調せざるを得ない点だろうか。仕方のない側面とはいえ、娘役をより女性らしく見せる表現手段が「古い価値観に基づく女性らしさ」一辺倒になりがちなのは気になるところである。外国人表象のステレオタイプ化も課題だが、こちらは時代と共に改善しつつあるように思う。
上田:一方で、女性が男性を演じることで、観客が得られるカタルシスもある。以前YouTubeで1970年代の宝塚の舞台裏を見たが、舞台上で百獣の王のごとく雄々しい輝きを放っていた男役のトップスターたちが、袖にはけた瞬間、男性演出家にへりくだるような挨拶をしていたことに驚いた。当時は女性への抑圧がかなり強かった時代であり、だからこそ観客の女性たちは『ベルサイユのばら』のオスカルの活躍に熱狂し、溜飲を下げていたのだろう。今なお女性は抑圧されているが、状況は変わってきている。現代の女性が宝塚に熱狂する理由が、カタルシスから別のものに変わりつつあるように感じ、興味を持っている。
木ノ下:宝塚と歌舞伎の女方が比較されることもあるが、歌舞伎の場合は「これは古典だから」という理由で、古いジェンダー感が許容されている側面がある。しかし宝塚は新作主義なので、揺れ動くジェンダー感を受け止めねばならない難しさがあるだろう。だが、女性が男性を演じることには、素晴らしい批評性もあると思う。『桜嵐記』でいえばマッチョになり過ぎない(男性性が強調され過ぎない)よさがあり、虚構度が高くなることで、新しい視点を獲得するきっかけにもなる。さらに深読みすれば、女性だけで演じることで、男性が主導してきた戦や日本の政治、歴史に対するアンチテーゼとして読み解くこともできるだろう。
![芸能の在る処~伝統芸能入門講座〜 宝塚歌劇編[ゲスト]上田 久美子 松本 俊樹 [案内人]木ノ下裕一](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20221130_J_takaradukakageki-1-768x432.png)
