
撮影:井上嘉和
高谷史郎は、テクノロジーに独自の観点から切り込むことで、精緻の中にノイズが滲み出すような世界を創り上げてきた。彼の原点の一つにあるのは「カメラ・ルシダ」という装置[1]であり、視覚世界の外部化(フレーム・アウト)や民生機器の異化的使用を通して、没入やスペクタクル化への批評的視座を一貫して提示してきた[2]。 本作のプレインタビュー(2021)では、カメラやラインセンサカメラを例に挙げ、 自身の意図を超えてテクノロジーが生み出す映像とそこに見出された「美」について述べている。
高谷名義で4作目となるパフォーマンス『Tangent』でも、それは一貫している。しかしこれまでとは作品のあり方が異っている。床は舞台の上にやや傾斜した白い面を客席に向け、中央にテーブルのように鉄板が置かれ、正面の壁はなだらかに影を映している。床、テーブル、壁という3つの平面と、それらを囲むようにアーチ状のトラスが渡されたシンメトリーの舞台。床には小石が散らばり、脚立、瓶、イスが配置されている。空間は、絶えず変化する光によってモノクロームを帯び、事物はしばしばシルエット状に浮上する。
唯一の出演者(細井美裕)は、行為によって現象を発生させていく[3] 。現象はリアルタイムでプロセスされ、映像や音として舞台上に現れる(複数の視点や音の併存)。時には上から降りてきたさまざまな事物、吊り下がる鉄板や振り子、既存の映像(高谷)や音(坂本龍一)[4] が加わりながら、終始静謐さとダイナミズムが接触しうる緊張感をたたえている。
かつてないほどミニマルな設 え、サウンド・アーティストの細井を起用したこと、光とそれに応じる影を軸としたモノクロームの世界。「極北」という言葉が浮かぶほどに削ぎ落とされた舞台は、「tangent」[5]、つまり高谷がイメージする「接線」や「触れる」こと(接触)をミクロ/マクロのレベルで起こしていく。それがとりわけ音、そして光においてなされていることは、重要である。視覚装置や映像を基軸としたこれまでと異なり、本作では、接触のプロセスが音や形態を生み出し、映像として出力されていく。

撮影:井上嘉和
以下全体の流れを俯瞰する。冒頭では暗闇に、何かを擦るような音が聞こえ始める。明るくなり、それが床を掃く動作だとわかる。ホウキ、テーブルに落ちる白砂など、音が耳に残る。トラス上の光源は、太陽の運行のようにアーチを移動し、空間の光と影を変容させつづける。
事物(鏡や瓶、天文学の古書、天体図、ラジオなど[6])がテーブルに置かれたシーンでは、テーブル上が「舞台内舞台」となり、細井の行為がライブで壁に投影される。黒シートに素早く線や円が描かれ(天体図に倣い)、鋭い摩擦音と発火が起きる。宇宙での爆発、人類の火の獲得と文化の発達—そして戦争までをも—を想起させる火は、人間にとっては危険と美を併せ持つ。ラジオのチューニングはノイズからシグナルを掬い出し、ノイズ音とともに掻き分けられた白砂は、星雲のように見える。テーブルは描かれる面であるとともに、一種の楽器と化している。
…と突然テーブルが傾き、大きなと音とともに描かれた世界が一瞬のうちに、ことごとく床に落下してしまう[7](人間が培った文明が一気に消滅したかのような喪失感…)。舞台はブラックアウトし、音のみが漂う。
テーブル板(鉄)はその後吊られ、暗闇の中、細井が接触(ドローイング)していくが、その都度ノイズ音と発火が起きる。ライブカメラが肉眼では捉えられない軌跡や光を可視化し、壁に映し出す。

撮影:井上嘉和
振り子(球体)のシーンでは、天体のような回転が円環的な時間へと誘 っていく。壁の映像は、自然や都市、人工物などへと変化し、デジタルのディソルブも加わり高速に切り替わっていく。床では細井が小石を(天文図に倣い)Xの形に並べ替えるが、ランダムから宇宙の秩序が発見されたかのようである。球体の回転、映像と音の強度がピークに向かう中、球体を細井が手で掴んだ瞬間にブラックアウトとなる(音のみが漂う)。
ラストシーンでは、吊られた4枚の鉄板それぞれを細井が軽く掻き(接触)、耳を寄せていく。板の記憶—精製され整形される前の状態、地中での生成や、遥か昔の宇宙における来歴—を遡ろうとするかのように。それまでのシーンを行為による現象の発動とするなら、リフレクション、つまり過去の深淵に人間のスケールを超えて向き合おうとするフェーズといえようか。最後に細井が一枚の板を軽く掻き、音が発生する中、ブラックアウトとなる。…暗闇の中、ベルのような響きが聞こえ、次第に減衰していく。音が沈黙へ向かうプロセスにおいて、作品の終了は聴く側に委ねられる。

撮影:井上嘉和
『Tangent』は、さまざまなものが出会う場であるだろう。それは知覚可能と不可能なもの—シグナル/ノイズ、高/低解像度、フォーカス/アウト・オブ・フォーカス—の境界領域をまたいでしまっている。
本作では、視覚的な遮断が何度も起こり、音が空間に漂い続ける経験をする。音は波として拡散し、観客の耳や身体に接触する。その意味で『Tangent』は、現象、音そして振動として空間に延長されることまでが「作品」だといえないか。そしてその上で、視覚的要素に目を向ける。事物、映像そして光は「視る対象」と思われている。聴覚と比べ、視覚は能動的で自ら遮断もできるからだ。しかし視るということは、(ゲーテを挙げるまでもなく)それぞれの眼で受容され、知覚される接触性をもっている(参考としてルクレーティウスを引用する)[8]。そして『Tangent』では、リアルタイムで起きる接触が、視覚的に重要な役割を担っている。接触による形態や映像を、接触的なものとして視覚に取り込むこと。本作は、聴覚の接触性を経た上で、あらためて視覚における接触性に向き合う場といえるだろう。
ライプニッツが「モナドロジー」において、接触が接触を生むことで連鎖的に世界がつながり、遠くのものへと到達していくと述べたことを思い出す。現象が残す痕跡や放つ波紋や影響は、現在起きている現象にとどまらず、未来へと派生していくのではないか。そしてまた、現象は過去の幾多の現象へと遡りうるのではないだろうか。
高谷が本作の起点の一つとするヨハン・ヨハンソンの映画『最後にして最初の人類』(2020)[9] では、空や建造物をミニマルにフレーミングしたモノクロ映像に、20億年後の人類からのメッセージが重ねられる。ある星が太陽と衝突しつつあることで滅亡の危機に瀕している彼らは、過去の人類に憑依したり、過去に影響を及ぼしうるという。そのような途方もない時間と空間を隔てた接触の可能性にまで、高谷の想像力は至っているのだろう。
『Tangent』は、さまざまな接触が起きる実験の場である。それは本作に接触した人々から多様な形で新たな接触を派生させていくだろう。バタフライ・エフェクトのように、地球史そして宇宙史にまで接続されうる現象として。
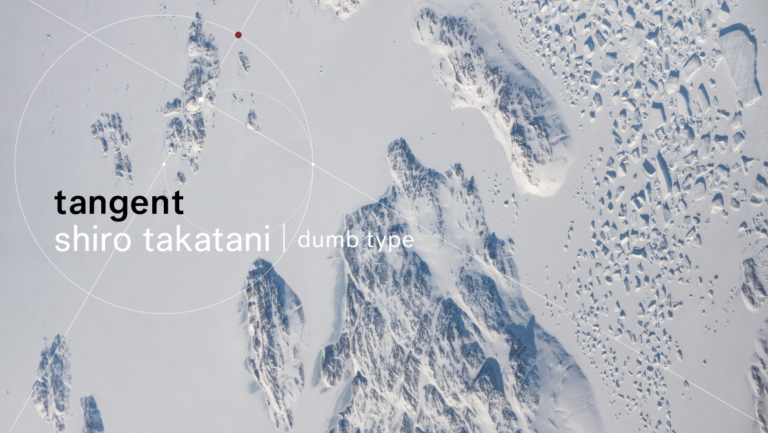



![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_2.Camera-Lucida.jpg)
![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_12.topograph_ShiroTakatani-scaled.jpg)


