人が劇場に向かうのはなぜか?日常を超えた、何か特別な世界を体験するためだろう。いつもとは違う、何かに対峙すること。日常的な認識にまとわりつく約束事を剥ぎ取り、世界と新しく接すること。舞台は、観客に対して、世界を新しく感知させ、認識させるよう仕向ける。そこでは、音楽や音響もまた、そんな異世界をつくる大きな要素になる。
『Tangent』は2023年2月にロームシアター京都で上演された、高谷史郎の8年ぶりの新作舞台だ。この作品名は、配布されたプログラムに記されているように、ラテン語のtanger、つまり「触れる」という言葉に由来し、英語ではtactileとなる。また、Tangentには「接線」という意味もある。異なる世界が交わり、触れ合う――「接線」はそんな境界を示唆し、そして観客を異なる世界に誘うのだ。
舞台上部には、半円を描くアーチ型のレールが設置されている。その存在によって、観客は天文学的な時間性をあらかじめ感じとることができる。はるか遠くから俯瞰するような視点も獲得する。上演中、このレールに沿って照明は、太陽の動きを模すように、ゆっくりと移動していく。舞台のものに光が当たり、影の長さは変化する。あるときは明け方や黄昏時のように、長く、どこまでも延びていく。あるときは真っ昼間のように影はほとんどなくなってしまう。
ここで、ただ一個の生命体として登場するのが、黒い服を着たパフォーマーだ。台詞を発することはない。ダンスも、派手な動きさえも、しない。ただ、何かしらの所作を行なっている。ものに触れ、動かし、それらに戯れる。そこで、比喩的な世界が展開されるのだ。
作品は複数のシークエンスで構成されていた。ここでは便宜上、4つに絞ってみてみよう。
最初のシークエンスでは、夜明けの月明かりのような柔らかな光が、舞台を照らし出す中、パフォーマーが床に散らばった石を箒でサーサーと掃く。そのあと、傍に置かれたボトルから小石を取り出し、舞台の中央にある机の上にジャラジャラとこぼす。この光景は、日本の寺院の早朝を思わせる。何かしらの信仰心を象徴しているように思われた。

撮影:井上嘉和
次に、パフォーマーは机の上の本をめくっている。背後にあるスクリーンにはその本のページが、大きく映し出されている。天体の軌道図や幾何学図形が見え、内容は中世の天文学や幾何学のようだ。パフォーマーは次に、机に広がった小石を手繰り寄せ、手でかき混ぜ始める。この行為は占星術を思わせる一方で、枯山水の庭を模したミニチュアを作っているようにも見える。ノイズを含みながら、男性の声が聴こえてくる。ラジオの放送だろう。遠くから響くようなその声は、不明瞭だがヨーロッパ言語のようでフランス語も混ざって聴こえた。本は、西洋近代科学のシンボルとも取れるだろう。声もまた、どこか権威的な響きがする。科学的思考を取り入れつつ、独自の文化も育んできた、近代日本のメタファーと感じられた。

撮影:井上嘉和
3番目のシークエンスでは、パフォーマーが、天井から吊り下げられた黒い鉄板を金属棒のようなものでこする。すると溶接作業で見られるような火花が、バチバチっと飛び散る。さらにその音は鉄板に取り付けられたマイクによって増幅される。舞台奥のスクリーンには、飛び散った火花がズームアップされる。大きな花火、あるいはマグマのような迫力だ。実際の火花は消えていくのに対し、スクリーンには火花の映像が、次々に重なる。映像は同じ画面上に上書き保存されるように、加えられていく。これは、人類が大きな火力を操り、金属を精錬してきた歴史のメタファーであるかのようだ。スクリーンに映し出された火花は、活火山を思わせる一方で、有史以来、人類が掘り出し、加工し、利用してきた地球のエネルギーの総体を示しているようにも思われた。

撮影:井上嘉和
4番目のシークエンスでは、舞台の中央にて糸で吊るされた球体が、ゆっくりと回転しだす。パフォーマーがその球体に手を近づけると、ハウリングのような音が発生する。球体は徐々に大きく弧を描いて回転を続ける。すると、会場のスピーカーからは、うなるでもなく、ささやくでもない、微妙な女性の声が聞こえてくる。複数の声が重なり合い、歪んだり電子音に加工されたりする中で、ピアノの音も加わる。音は混じり合い、その音量は徐々に増加していく。ついには、大きなノイズの音塊が会場を覆い尽くす。この音は、客席の四方に設置されたスピーカーから流れ、高速で回転するように移動する。パフォーマーが球体の動きを手で止めると音も鳴り止み、舞台は暗転する。この場面は現代に象徴的な人類の欲求を窺わせた。身近な自然のみならず、惑星全体をも支配しようとする支配欲に満ちた姿だ。軋むような音が発生する。しかし躊躇なく、パフォーマーは一気に動きを止めてしまう。果たして、どのような結末になったのだろう。突如として漆黒の闇が訪れる。

撮影:井上嘉和
『Tangent』における視覚的要素は、観客が終始安心して舞台を眺めることを拒絶する。日常生活ではあり得ないような視覚体験が、作品の目指す「リミナルスペース」、つまり超-現実的世界を志向する。たとえば天体の軌道を象徴するアーチに対し、舞台上のパフォーマーを同時に認識させる方法は、大小サイズの異なるものを並置する、伝統的な演出の延長線上とも言えるだろう。しかし、その上で、視覚に対して、錯綜を生じさせるような仕掛けが多く施されている。たとえば、パフォーマーが客席の方向に向きながら座り、読書をしているのであれば、その本の中身は、実際には観客から見えないはずだ。しかし、後方のスクリーンでパフォーマーの頭上からの映像が大きく映し出されている。やがてその視点は動きだす。視点の位置は変化し、机周辺を映し出す。これは一般のプロジェクターでは見られない動きである。観客は、無意識のうちに、複数の視点で進行する出来事を、脳内で補正しながら理解しようとするだろう。
同じく、聴覚によって捉えられる出来事も、その音量や音質、響きに至るまでが、超-現実的な性質を帯びている。冒頭に現れた、箒で掃く音や、机に撒かれた小石の出す音も、会場の空間で自然に反響して聴こえるような自然な音ではない。マイクが取り付けられ、拡張された少し硬質な音として、鼓膜に迫ってくる。また、2番目のシークエンスで挙げた男性の声は、ときに石の聖堂にいるような音響をともなっていた。エコーのような残響を伴う空間性は、舞台上の空間には本来存在しないものであり、不思議な感触を残すだろう。4番目のシークエンスでは、舞台中央の天井から糸で釣られた球体がまわる、音が客席の四方に設置されたスピーカーから流れ、音がパンニングするように移動する。それはまるで、球体の運動とリンクするようだが、本来は、舞台上のものから発生した音を、客席の左右から感じ取ることは決してできないはずなのだ。
このように視聴覚を錯綜させるような空間が仕掛けられている。ここであまりに自明だが、あえて指摘しておかねばならないことがある。それは『Tangent』においては、パフォーマーが「触れる」行為には、なんらかの音響が必ず発生し、その対応関係は常に真であったということだ。パフォーマーが何かに触れるとき、その音は、コンタクトマイクを通じて拡張される。その音響には不気味な要素が加わり、往々にして、音は鋭い印象を与える。たとえば、パフォーマーが鉄板を引っ掻き、火花を発生させたとき、ビリッビリッと、鋭利な物質性をともなった音が発生する。そして、このことは、音の触覚の特異性を示している。
「触れる」とは、単に何かを知覚し、「さわる」だけにとどまらない。世界を知覚し、思考するだけにとどまらない。日本の哲学者、坂部恵によれば、「触れる」とは単にさわるのではなくて、「自-他、内-外、能動-受動といった区別を超えたいわば相互浸透的な場に立ち会う」[1]のだ。言い換えるならば、「触れる」とき、主体と客体といった明確な区分はなくなり、ものへと浸透するような、身体性がものを媒介して拡張するような感覚が生じると同時に、主体と客体の分離が生じてくる地盤そのものを形作る。観客は、こうして、世界に対する認識をあらたに構成し直すのだ。
『Tangent』で演出された音、音響というのは、触覚的な物質性が存在している。観客の聴覚細胞を刺激する。それはあたかも、脳内にある電極に信号が送られるように、そして、虚構世界のアバターになるように、観客を誘導しているのではないだろうか。

撮影:井上嘉和
音に「触れる」ことで、想起されるのが、坂本龍一の存在だろう。近年の坂本は、ものに「触れる」というプリミティヴな行為を見せ、音を出すパフォーマンスを行なっていた。例えば高谷との仕事だった、『坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME』のパフォーマンス公演や、2016年のAlva Notoとのパフォーマンス『The Glass House』が挙げられる。前者では、調律の狂った「被災ピアノ」を弾き、ボウルのようなものを金属棒で擦ることもあった。また後者では、ガラスの壁にコンタクトマイクを取り付け、マレットで建物の窓ガラスの表面をこすり、音を発生させていた。高谷は、坂本との仕事から、多くのヒントを得たことだろう。
さらに坂本の楽曲自体も使用されている。『Tangent』では、ラストアルバム『12』から5曲が使用されていた。楽曲全体の使用ではなく、1トラックのみの抜粋や、曲の断片がサンプリングされたものなど、断片が使用されていた。ピアノ曲は、綺麗にサンプリングされていたが、特定のメロディーはほとんど強調されることなく、つまり音楽的に押し付けるわけではなく、劇場の空間へと、そして他の音と溶け込むような演出がなされていた。また、陶片がカタカタと鳴る物質音は、『12』の最後の楽曲「20220304」からだが、劇中で使用され、さらに終幕においても何度も繰り返された。ときに舞台上の鉄板と共鳴しながら、不思議なリバーブ感を生み出すこともあった。
『Tangent』は、視聴覚を使っての空間性の演出において、超-現実世界を構築していた。その核心に触覚性のアプローチがあった。たとえば高村が指摘する通り[2]、芸術表現における触覚のアプローチ自体は20世紀モダニズムからも見られ、その歴史は積み重なりつつある。しかし、高谷、そして坂本もだが、第一線でデジタルにおける芸術表現に長けている者が、総合芸術的な空間性の中で、極めて現代的な批評性を保ちつつ、触覚性へアプローチしているのだ。
超-現実的な異世界はそのような意識の中でうまれ、観客の意識を自然に導入するものとして、触覚的なアプローチが行われた、ということだろう。そして異世界を思わせる音響空間の中で、2023年3月に逝去した坂本の存在自体も、どこか身近なものへと感じさせたのだった。

撮影:井上嘉和

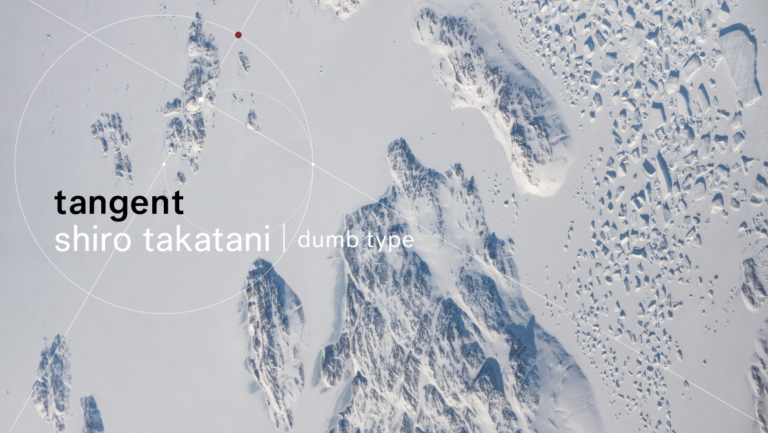



![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_2.Camera-Lucida.jpg)
![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_12.topograph_ShiroTakatani-scaled.jpg)


