幼いころ父の部屋によく行っていた。そこには本や、ハリウッド映画のフィギュア、ジーパン、サングラスや指輪、タバコなどが散乱していて、それらと戯れるのが楽しかった。わたしが四歳のころ、父は他界した。だからわたしには父の記憶がない。父と一緒にいた実感もない。そのとき自分にあったのは、周囲の人が語ってくれる父の話と、父が残したモノだけ。話を聞くのはあまり好きではなかった。死を身近に感じて怖かったから。だけど部屋にあるモノたちと遊ぶのは好きだった。それらは父の代わりに、生き生きとわたしに接してくれたから。
そんなことを高谷史郎の舞台作品「Tangent」を観たあとに思い出した。客席にむかって床面に斜めに据えられた、巨大な白い正方形の平面。奥にそびえる横長のスクリーン。それらを覆うアーチ型の鉄の骨組み。そのような舞台空間で本公演は行われる。その最後のシーンに、わたしは惹きつけられた。
暗闇のなかで風鈴の音だけが聞こえる。次第に明るくなると、椅子に座っているひとりの女性があらわれる。舞台上には四つの天板が吊り下げされている。彼女は椅子から立ち上がると、左端の天板のほうへ向かい、それをノックし耳を傾ける。するとラジオのような音声がこだまする。次に隣へ行き同様にノックし耳を傾けると、なにかを打ちつけたり、擦り付けたりする音が鳴っている。そして三つ目の天板では高域の音と女性の声が聞こえてくる。
天板が音を発する。その光景は奇妙である。それは単なる鉄の板にしか見えない。ましてやラジオのような音声再生装置ではない。にもかかわらず天板はみずから音を発している。実際に鉄板には振動子が取り付けられており、それが振動することで小さな音を発している。女性の耳のあたりに取り付けたマイクが音を拾い、スピーカーから聴こえるようにしているのだ[1]。しかし本作において、このようにモノがみずから駆動するありようは、何をあらわしているのだろうか?

撮影:井上嘉和
天板から聞こえる音を手がかりにしよう。本公演は暗転を指標として、およそ五つのシーンに分けることができるが、最終場面の吊り下げられた三つの天板が発していた音は、そのうちの三つの場面——以降それらのシーンを便宜上、第一から第三場面として扱うこととする——でスピーカーから出る音に対応している。本公演で唯一のパフォーマーである女性は、第一場面ではラジオを聴いたりノートを書いたりし、また第二場面では器具を打ち付けたりするのだが、そのときに生じる音が天板からも聞こえているのだ。そして第三場面では高音と女性の声があらわれる。ではそれらの音は天板にいかなる意味を与えているのか。具体的に見ていこう。

撮影:井上嘉和
まずは第一場面のラジオの音声から。最終場面では吊り下げられていた天板は、ここではテーブルとして扱われている。机上にはラジオや本、そして青いビンが置かれている。それらの前に座っている女性は、本を開き、おもむろに黒いノートを取り出し、直線と円をひたすら描いていく。ラジオの音声は、無機質な空間のなかで、もの寂しく反響する。女性がラジオに耳を近づけると音量が大きくなる。離すと小さくなっていく。そして天板に顔を伏せると、ふたたび音は大きくなる。
天板と音の関係に注目したい。第一場面では、天板がラジオと同じ音声再生装置として機能している。女性はラジオに耳を近づけていたが、同様に天板に顔を伏せた際にも音声が大きくなっていた。だがそれだけではない。最終場面の左端の天板は、ノートを書く音も発していたからだ。おそらく天板には女性が耳にした音が刻まれている。彼女が耳を傾けていたのは、自身の動きの痕跡ではないだろうか?
第二場面を見てみよう。暗闇のなか、天板が縦に吊り下げられているが、そこに女性が溶接機のようなものを打ち付け、火花が散る。同時にスクリーンでも火花が映される。だがその残像が消える時間は次第に遅くなり、光が残留する。最終的にスクリーン上には全面的な光の絵画が立ちあらわれる。そして天板は上昇し、女性は退場する。この場面では女性が器具を打ち付け、火花を散らし、光の絵画を描くといった行為によって発生する音がスピーカーから聞こえる。同じ音が最終場面における二番目の天板からも聞こえていたが、それは女性の行為が天板に記録されていることを意味する。ラジオを聴いたり、ノートを書いたり、絵を描いたりするといった、これまでの女性の動きから生じる音が、天板に刻まれているのである。

撮影:井上嘉和
しかし天板の音があらわしているのは、女性のパフォーマンスだけはない。そこにはもうひとつの側面がある。たとえば最終場面で、天板からラジオの音声を聞いたわたしたちは、女性がそれを聴く動作を思い出すが、同時に声を発していた「そこにはいない誰か」のことも想起するだろう。また何かを書いたりすることは、ありふれた行為であり、その意味で天板の音は女性の固有性から離れてもいる。実際に、これまで「女性」と表記してきたパフォーマーは俳優ではなく、サウンドアーティストの細井美裕であるが、細井は自身の立ち位置について、「作品のなかで「人類=ヒト」を代表するわけではないにせよ、作品の時間軸のなかで、ヒトのサンプルとして」舞台上にいたと語っている[2]。天板の音は、女性だけでなく、わたしたちの目には見えない匿名的な誰かの動きでもあるのだ。

撮影:井上嘉和
第三場面では、天板に刻まれた二重の痕跡が、ふたつの音であらわれている。薄暗い空間のなか、球体が天井から吊り下がっている。女性が横切ると高域の金属音のような音が響く。そして球体の下に手をかざすと、ふたたびその音が鳴る。球体は円錐を描くようにゆったりと回旋しはじめる。彼女は箒を使って、床の石を直線に並べていく。会場には女性の声が響く。遠くへ投げかけるような声。スクリーンに海岸や森といった自然の風景が映し出される。風景の映像にグリッチがかけられ、横に伸びていき、グラデュアルに別の風景へと移りかわる。女声にエフェクトがかけられテンポが速くなる。地響きのようなノイズが重なる。スクリーンでは、さまざまな都市の風景の断片が矢継ぎ早に展開していく。女性が退場し、無人の空間になる。ノイズを全面に押し出した高密度の音が、わたしたちを圧倒する。女性が戻ってくる。そして球体を止める。同時に音が止まり、暗転する。
最終場面における三つ目の天板が発していた音は、第三場面での高域の金属音と声であった。ここでは声と映像が呼応している。声のテンポが速くなると、大量の風景が高速で繋げられていく。声は細井によるものだが、その光景は、自身の声の属人性から離れ、あらゆる空間を瞬時に行き来する映像に融和しているかのようである。他方、金属音は球体が女性のそばを通過するときしか鳴らない。というのも球体はスピーカーであり、金属音は、マイクを身につけた女性がそれに近づくことで起こるハウリング現象によって生じる音だからだ。つまり女性と球体型スピーカーの運動がリアルタイムで呼応しているのだ。したがって第三場面のふたつの音は、現実のパフォーマンスと非現実的な空間の移行をそれぞれ表現する。現実と非現実が同居するその光景に、わたしたちは目がくらむだろう。そのような眩暈の感覚が、最終場面の三つ目の天板に音として刻まれている。
ところで本公演は「Liminal Space(リミナル・スペース)」という「2つの相反する要素が両立している奇妙な空間」をテーマのひとつにしているという[3]。リミナル・スペースという用語は、二〇一〇年代後半よりインターネットで見られるミームであるが、ショッピングモールや公園など、わたしたちにとってありふれた空間が無人の状態であるようなときに醸しだす、ある種の不気味さを示している。高谷自身もリミナルな空間に関心を寄せており、「もともと人がいない場所を撮った写真には興味はなくて、普通なら人がいるはずの場所なのに誰もいなくなった、人がイレイズ(消去)された写真に「意味」がある」と述べている[4]。
そのようなリミナリティを連想させるのが第三場面の光景だ。ここでの現実と非現実が同居するありようは、これまでの動きに対応している。一方でわたしたちは、女性がラジオを聴き(第一場面)、光の絵画を描く姿(第二場面)を見てきたが、他方でそれらには匿名的な他者の動きが潜んでいる。そして第三場面において、無人の風景が矢継ぎ早に繋げられる超現実的なありようと、球体が一定の速度で旋回する現実の運動のズレがあらわれることで、目に見える女性の動きと見えない他者の動きが宙吊りにされるのである。

撮影:井上嘉和
ところが最終場面において、わたしたちが見てきたパフォーマンスは、天板が発する音に縮約される。この場面でわたしたちは、吊り下げられた板に女性が耳を傾けている光景を目にしつつ、天板が発する音を聞いて、そこでは見えない他者の存在も思い浮かべるだろう。音は、単なる物体である板に、可視と不可視、ふたつの側面を付与している。本公演で描かれているのは、誰かが関わっていたはずなのに、今では誰も扱っていない「Liminal Object(リミナル・オブジェクト)」なのである。リミナルなモノには不可視な誰かが介在している。最終場面で女性が聞いていたのは、天板が発する他者のざわめきなのだ。父の部屋での記憶を思い出したのは、こうした天板のありようを見たからだ。わたしは父が残したモノたちから、父を感じ取っていたのかもしれない。
本公演では、天板以外にもうひとつ、リミナル・オブジェクトが扱われている。それは第一場面でテーブルに置かれていた青いビンである。それは、本公演で使用された『12』が最後のアルバムとなった坂本龍一から、高谷がもらったワインのボトルであったそうだ。『サウンド&レコーディング・マガジン』で細井が連載しているコラムでは、坂本のボトルに関するエピソードが語られている[5]。本公演の稽古場で、驚いた様子で高谷が細井を呼び寄せ、彼女が何かと見てみると、誰も触れていないのに、床の上で青いボトルがひとりでにカタカタと揺れていたそうだ。もちろんその現象には理由がある。本公演の床面と同様に、稽古場の床も傾いていため、ボトルがバランスを取れず揺れていただけだ。しかし原因がわかっているのにもかかわらず、そのように強い存在感をあらわにするモノから、わたしたちは何かを感じてしまう。リミナル・オブジェクトはわたしたちに働きかけている。わたしにとってそれは父の部屋にあったモノたちだった。

撮影:井上嘉和
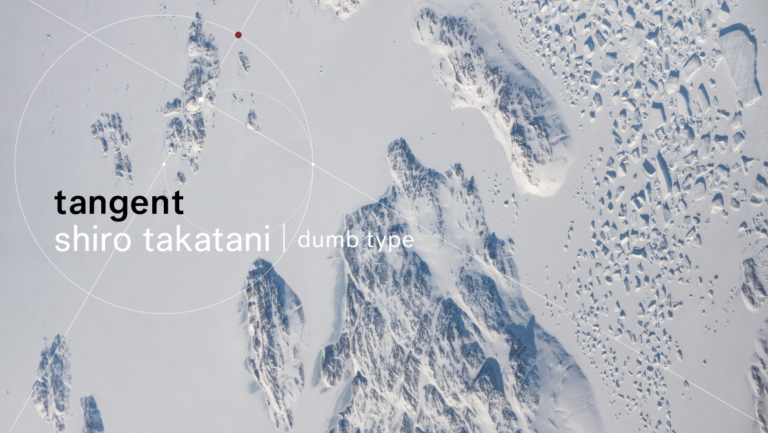

![高谷史郎ロングインタビュー[前編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_2.Camera-Lucida.jpg)
![高谷史郎ロングインタビュー[後編]](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20220309_J_takataniinterview_12.topograph_ShiroTakatani-scaled.jpg)



