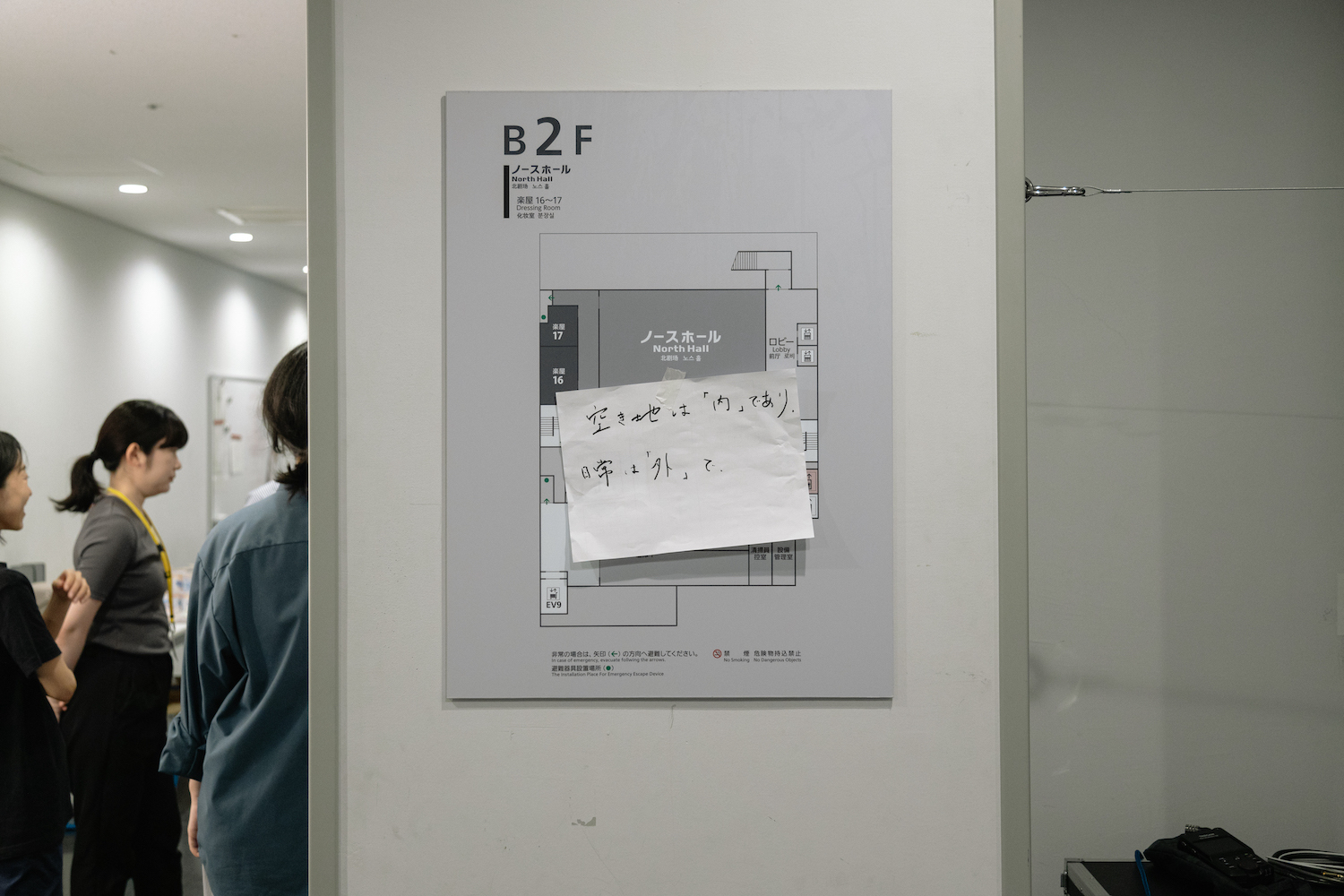先ほど、非常に強力だという台風10号が鹿児島に上陸したことをラジオが伝えていた。速度を緩めた台風は、金曜日に近畿地方に到来するだろうという当初の予測を大きく裏切り、およそゆっくりしたスピードで私の住む京都へ近づいてきている。台風上陸ランキング2位の場所に生まれ育ち、気圧の影響を敏感に受ける者にとって台風の接近とは、それが通過するのをただ待つという時間の始まりである。台風が迫っていると知ればその通過の受け入れ体制を整えることとなるが、それ以外にできることはない。都市部のように周囲が建物に囲まれた場所でないならば、雨戸や板で戸や窓を塞ぎ、それが通り過ぎる只中では、さまざまな種類の板とさまざまな物たちが衝突する音を聞きながら目を閉じる。あるいは交通機関が運休することを予想して、ラジオやネットで情報を得ながら家でDVDを観たり本を読む。何ごともし難い出来事が渦巻く中でそれにできるだけ接触しないように意識し、しかし静かに巻き込まれていく。
辞書的な意味で、他から作用を及ぼされることを受動とし自ら進んで行うことを能動とすれば、あるひとまとまりの行為の時間の中で両者は細かく関係し合っている。例えば車を運転するとき、私の身体の運用において微視的にみれば、受動が能動へ、そして能動が受動へ(車間距離の調整や交差点での停止、発車など)と連続的に接続される。そしてその接続は通常、行為する私にとってスムーズでなければならず、実際スムーズであることが多い。スムーズであるとき「車の運転」という行為の全体は能動的である。つまりある程度の時間的なイメージを予め持つことができ、行為の全体において緩やかに計画可能と言える。一方、台風が通り過ぎるのを待つという時間の中では、私の微細な能動と受動は目眩く交代しつつ同居している。ここまでこの原稿を書いていた48時間のうちに台風はだいぶ近づいてはきたが、ゆっくりとくねくねしながら今度は90度方向転換して北へ向かうという。台風の予測不能な動きによって私の動こうとしていた手足はまた止まり、ベッドに横たわることになったのであり、したがってこの文章の続きをタイピングしたりすることができている。そしてこの数時間後台風はついに到来前に消えてなくなり、私の待つという行為も唐突に終わったのだった。この一連の待ち時間の中で、台風と私は動いたり動かなかったりしていたわけだが、微視的に行為を辿れば台風情報という外部の情報、あるいは吹き込んできた湿った風や頭痛を受けてから次の行為の指針が変わっていく状態にあり、この待つという行為は全体において受動性が優位となる時間を伴う。そして待つ行為の時間内での微細な能動と受動の接続の機微は、外的な要因によってその都度リセットされうるため、都度の行為の完了は自らの意思によっては保証されず計画不可能になる。別の言い方をすれば偶然性に開かれていくと言うこともできるだろう。これは私の能動と受動の実感の話だ。
ところで、空間を用いる芸術作品はその特性として、時にその空間の内部にいる観客に能動的であるか受動的であるかを要請すると言われる。例えば美術批評家のクレア・ビショップによると「インスタレーション・アート」はそれを経験する観者の知覚する身体の「直接的な現前」を要求するという。それは積極的に見る、聴く、嗅ぐ、話す、触る、食べる身体だ。この場合「インスタレーション・アート」はそのような生き生きとした観者の能動的な身体の運用によって基礎付けられていることとなる。*1 一方、展示空間に映像や音声が投影/再生されている「ヴィデオ・インスタレーション」の場合はどうだろうか。素朴に考えてみると、椅子やクッションに座ったり靴を脱いでカーペットに居続ける行為はその全体において能動的だ。確かに、思い出に浸り、想像のイメージが広がり、寝てしまった時私は当初の能動性が破れて受動的な状態にあるだろう。*2 しかしその入り口において、「32分14秒」とキャプションに時間表記があり、映像や音声の前に椅子やクッションやカーペットもしくは何もない広がりがあり、既にそれを鑑賞する先客がいて、どこか他の空間からも別の音が聴こえてくるような現代的な空間、つまり見聴きする行為が相対的に標準化されるような空間では、私は観始めからその終わりをある程度予定しておかねばならない。観終える計画なしでそれを観ることはできない。そして展覧会は他のいくつもの行為への分散を要請する。私は次の行為へ流れるように、映像/音声が終わるかその前に鑑賞を完了させ立ち去る。そのような鑑賞のなかにあるのは時間的にあらかじめ固定され、予定された受動だ。このようにして受動は鑑賞という能動の全体の一部に計画され一つの機能-報酬へと貶められる。少なくとも、私の鑑賞経験ではこのような実感を覚えることが多い。
さて荒木優光による『Sound Around 004 げんし 空き地の TT』の3時間に及ぶ公演は一時的であれ、予定された受動とは異なる鑑賞の経験を誘発するものだった。まず、ロームシアター京都のノースホールへの階段を降ると、ホールとそのエントランスに加え、トイレやバックヤード、控室、モニターに至るまで、通常鑑賞の場としては非公開となる場所の戸口が開け放たれており、観客はこれらすべての場所で座ったり立ったりして鑑賞が可能になっている。実際、出演者はそこかしこで断続的にパフォーマンスを行う。トイレの中で歌の練習のような断続的発声を行う者。突然柱や壁に走り寄る者。スキップをする者。鼻歌で集う者たち。手を叩く者。準備運動のような動きを続ける者。観客は3時間の間どこにいてもいいようになっていて、階段を登って隣接するカフェやコンビニに行ってもいいし、家に帰って2時間後にまたきてもいいしこなくてもいいことになっている。

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴
ここで注目したいのは観客が鑑賞の時空において解放されていることではなく、20名の出演者が常に移動を続けながら地下の劇場とその周辺のアクセス可能なすべての場所で何事かを行なっていること、鑑賞の対象となる出来事が充満していることだ。この充満において音は極めて重要な要素となる。音は何かを経ていなければ聴くことができないものであり、さまざまな媒体を経由して到来する。そのため私がその行為から離れていてもそれは聴こえてくる。たまたま誰もいない控室では廊下を何者かが走ってくる音、廊下の反対側からは持続的な発声が近づくのが聴こえる。私はそれがここに辿り着くだろうと思って座って待っている。だが実際辿り着くかどうかは分からず、予測は次々に外れたり当たったりする。見えないが聴こえること。音の持つこの越境性を顕在化する上でバックルームを含むこの地下空間は適している。こうして出来事は地下の隅々まで充満する。このような空間の中で私は他の鑑賞者に混ざってなんとなく移動する。移動がどのような意味を持つのかもよく分からないままに。この移動の最中でも、移動した先でも何事かは起こっており、私は出来事たちに囲まれ続ける。継起する出来事たちに囲まれ続けること、その只中ではそれらと対峙する際の時間的なイメージを固定化して持つことは阻害される。つまり動作の計画ができない。また移動した先では、ある出来事からは遠ざかり別の出来事に接近している。移動によって認知できる行為ー出来事との時間、空間的距離のレイヤーは複雑に変化する。例えば、複数人の出演者が集まって、いくつかの石ころと砂利と1人の出演者が先ほどまで着ていたTシャツを足で蹴ったり押したりしながら劇場からバックルームの廊下へゆっくりと運ぶとき、その近くへ移動した私は複数の靴と石同士が接触し合う音と、砂利の残した白い痕跡の線を間近で見ていた。その出来事の向こう側でさっきまでサックスを吹いている人がいたが、今やどういう音なのかよく分からない。石たちとTシャツがほとんど劇場から出ていき、その音が徐々に聴こえなくなる。すると今度は目の前を「あーーー」と言いながら疾走する人が通り、すべてはかき消される。そして私は石たちが気になってまた移動する。この移動が及ぼす出来事との時間、空間的距離感の変化が、それらの充満をより徹底したものに、つまり3時間の絶え間ない継起の感覚を実感させる。「げんし」のなかで、私は無数の出来事たちが通り過ぎるのを移動しながら待っていた。

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴

撮影:片山達貴
ここにはさまざまな行為と、それが複数の観客に共有されるという意味においての出来事の充満があり、それらと隣り合わせの私は、人と人々、砂利や石、他人の食べるラーメンとその残り、カメラ、モニター、物音や声、バリケード、サックスやパーカッションの演奏などとの接触を避けつつ(耳を傾けつつ)それらが通過することを待つ。そして私は待ちつつ少しだけ移動する。そのことが微視的な行為ー出来事たちとの間の時空的距離感を複数化する。本公演の特筆すべき点はここにある。このようにして充満する出来事たちの中で、私は何かを細かく選択しようと移動しつつも予定不能な状態にあった。それは台風通過を待つそわそわと開放感を伴うあの受動的時間に似た、微細な能動と受動が目眩く交代しながら同居している時間の経験である。