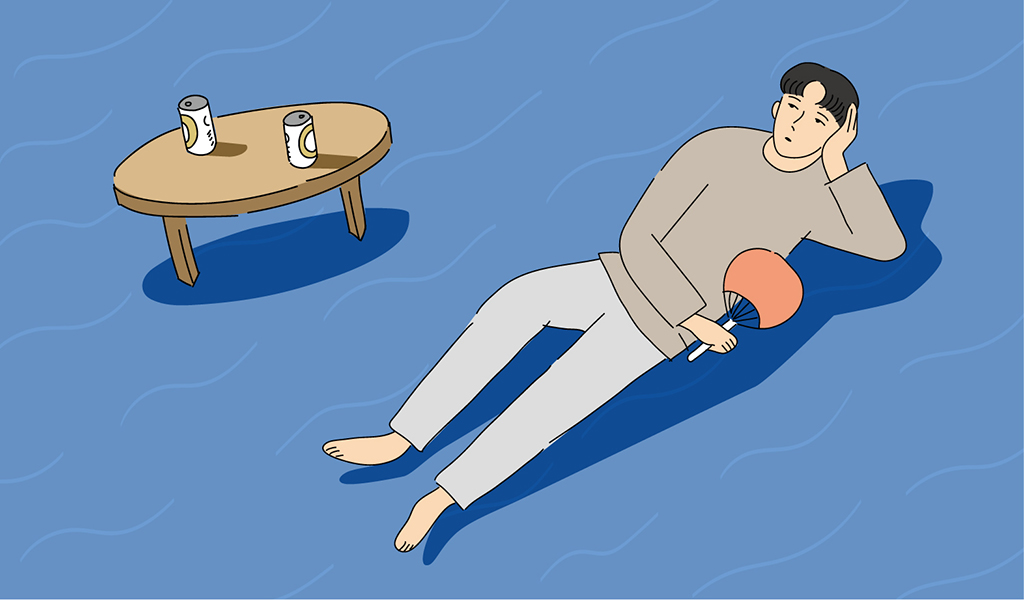 イラストレーション:カナイフユキ
イラストレーション:カナイフユキ「シーサイドタウン」は海辺の町と一軒の家についての演劇である。その家は空き家なのだが、そこに一人の人物が帰郷するというモチーフから戯曲を書く作業は始まった。 考えてみると私はこの帰郷のモチーフに取り憑かれ続けている。それは、しかし、生まれついた場所(ふるさと)に帰るというよりも、見知らぬ異境にたどり着くというイメージなのだ。だから、異境に帰郷するというのは、放浪者が故郷にもどって来るということでは割り切れないなにかがある。私にとっての帰郷という概念には、うまく定住と放浪が二つに分割できない「もどかしさ」が含まれている。旅をすみかにすることもできるし、住み続けながらもそこが旅のさなかになることもあるだろう。つまり、定住と放浪は互いに浸透し合っている。 人が「町」や「家」に住むということ。それはどういうことなのだろうか。町も家もある空間の拡がりをもった場所なのだから、「場所を占める」ことが「住む」ということなのだろう。「占める」というのは、ある空間的なテリトリーを確定させることなのかもしれない。確かに領域が定められると「住む」という感じが湧いてくる。そのとき領域を定めているのは誰なのか、何なのか。 私は昨年、ドイツのライプツッヒという町に一年ほど住んでいたのだが、住所を得て住人として登録されたことで市民感覚をえられたようには思えたが、その町に住みなす感覚というのは当然ながら登録の問題ではなかったように思う。そこに単に「いる」という感覚から「住む」感覚に移行したのは、毎日の習慣が生じてきた頃のことだった。たとえば、買い物や散歩のコースが次第に決まっていって、それがルーティンになったときに初めてその町に住んだ気になったのではなかったか。 「住む」ということには誰かが「いる」(あるいは何かが「ある」)ということとはいささか違う何かが滲んでいる。その「なんらかの滲み」は空間的には幅のような拡張性だし時間的には一種の不思議な持続性のことだ。私が、徐々にライプツッヒに住んだ感覚をえられた、あの買い物や散歩のルーティンという日常の発生は同時に一度として同じ出来事に感じることがなかった習慣のことでもある。つまり不思議な持続性というのは、ルーティンであるにもかかわらず、その広がりの枠や一定の間隔の時の刻みの内側に日々その時々の特異な場所性や時間性に出会い続けているということだった。簡単に言えば、今日の街路の日差しの加減は昨日のそれとはいささか違うということである。それを、住むようになると感じることができるようになる。それは当たり前のようでいて、びっくりすることなのではなかろうか。 住むべき人が住むべき場所を訪れて、そこにある期間を滞在することでそこが住むべき領域(住居)へと定められるとも言えるが、その人のほうもそこに留まることでその場所のほうからの働きかけを受容せねばならず、そこに留まるその人の身体も精神も同時に場所のほうからの磁力に支配されることになる。 ここで、「住む」の主体が再度問われなければならない。住む(住んでいる)のは誰なのか、何なのか。 人が場所に住みなす行為を何かの「滲み出し」のように捉えてみると、住むという主体のありようが、境界線を失うような感覚になる。住む場所に住む人が滲みゆくのと同時にそこを住みなす人に場所のほうからも何かが侵入して来る。このようにして「住むこと」はその領域である「町」や「家」とともに特異な個体化を遂げ、「住むこと」自体が主体化するのである。誰でもない何でもない、いくつかの要素からなる複合体の「住みなし」が行われるのである。 個体化と書いたが、住むことに滲むような拡散と収縮があるとすれば、そこには液体状・気体状のものへの生成変化も含まれるはずだ。そこには誰かが住んでいる気配がするという場合の「気配」も住むことが生み出す何かの放出である。まるで、葉脈という舞台で植物が日光とともに光合成を行うように住むこと。演劇の舞台へ人が現れることも、そのような「住みなし」であると考えてみたい。

