
Dr.Holiday Laboratory 集合写真 撮影:マコトオカザキ
若手アーティストのさらなる活躍を後押しするU35創造支援プログラムKIPPU。2024年度に選抜された2団体のうちのひとつが劇団「Dr.Holiday Laboratory(ドクター・ホリデー・ラボラトリー)」だ。
演劇における「代理性」や「役」の問題を現代社会に照射させ、死者や生者をふくみこむ多重な作品世界をくりひろげてきた「ドクホリ」。演劇というジャンルにとらわれない越境的な活動をつづけるかれらが、A.タルコフスキーの名作映画『サクリファイス』を原案に、新作に挑む。12月公演に向け稽古を進めるメンバー全員にインタビューを行った。
インタビュー:木原里佳、儀三武桐子、枡谷雄一郎(ロームシアター京都)、平居香子(京都芸術センター)
構成:儀三武桐子(ロームシアター京都)
インタビュー日時:2024年9月19日 ZOOMにて
Dr. Holiday Laboratoryメンバー
()内は今作での役割。
山本ジャスティン伊等(Dr. Holiday Laboratory主宰、作・演出)
石川朝日(出演)
小野寺里穂(制作)
油井文寧(出演)
ロビン・マナバット(出演)
結成から3年目
――劇団名の由来を教えてください。
ロビン:「ラボラトリー」は劇団結成当時、ぼくたち3人が小説家・劇作家の山下澄人さんが開いていた「ラボ」に影響を受けていたので入れました。「ホリデー」は、(山本)伊等が当時無職だったことや、ぼくが週6働き詰めで演劇をするためには 休日をとることになるから。
そして最後の「ドクター」はかっこいいから入れたいっていう、けっこう安直な理由ですね(笑)。
山本:当時ドクター・フィールグッドの曲を聞いていたりもしていたこともありました。
ロビン:Dr.ハインリッヒという漫才師にもはまっていたのもあって、語感もいいし入れようって。
小野寺:わたしはあとから聞いてびっくりしましたけどね、長いなと。
――主宰で劇作・演出の山本さん、俳優のロビンさん、制作の小野寺さんが立ちあげメンバーですね。
山本:そうですね。ロビンは高校の同級生で、おなじバスケ部だったんです。小野寺は大学院からの付き合いですね。ふたりとも、演劇をやるために集まったり知り合ったりしたわけじゃなく、元々友達や恋人だったのを、コロナ禍をきっかけに劇団を作ろうということで僕が誘った。だから三人とも、好きな作品の趣味指向は結構違ったりするんです。制作のためではなくて、個人的なつながりが集まることのはじまりになっている、そういう出発点も大切にしていたいと思ってます。
――そこに俳優の油井さんと石川さんが入られたと。
油井:わたしが入った当初は(山本)伊等くんが演劇を始めたばっかりで、俳優に助けを求めるようなスタンスでした。周りの意思を尊重しながらつくっていく姿勢がすごく衝撃で。全公演に俳優として参加しています。
石川:ぼくは最初、お客さんとして観に行きました。旗揚げ公演なのに錚々たる人たちをアフタートークに呼んでいて結構いきった団体だなと(笑)。前作『脱獄計画(仮)』から参加しています。
それぞれの活動の集合としての演劇制作
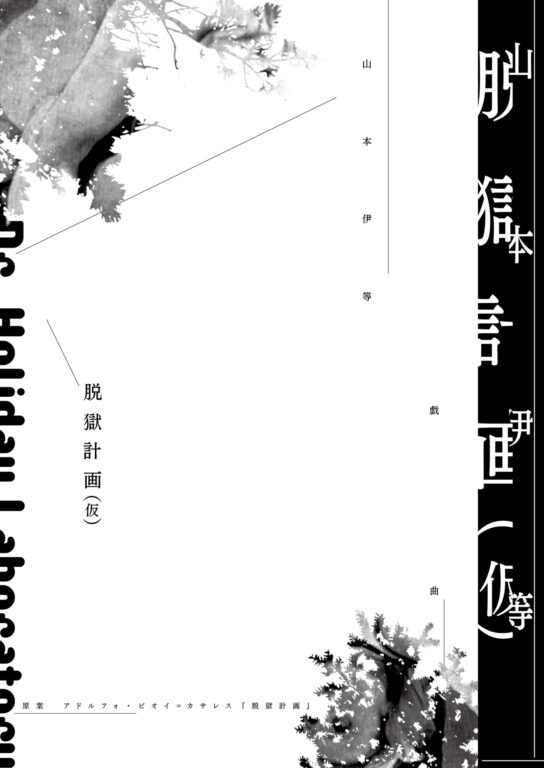
戯曲『脱獄計画(仮)』表紙
――演劇公演と並行して出版活動もされていますね。
小野寺:私と(山本)伊等くんが大学院で演劇研究していたこともあり、周りに本をつくる人が多かったんです。出版した戯曲には上演映像が観られるQRコードをつけていて、テキストと上演のセットで届けることを大事にしています。
――小野寺さんは川柳の活動もされているんですね。
小野寺:そうですね。数年かけて複数人でつくっていく演劇とはちがい、川柳は思いついたらひとりですぐつくれる手軽さがいいんです。メンバーそれぞれ背景や活動がちがうので、1年に1回集まって演劇をつくることが、それぞれの活動へのいい刺激になっています。

小野寺里穂『いきしにのまつきょうかいで』
山本:ぼく自身、学生の頃は小説家になりたいと思っていました。でもいわゆる純文学と呼ばれるジャンルで「小説家」と名乗って活動するためには、今はZINEや文学フリマなんかの流行で少し変わってきていますけど、基本的には文芸賞の新人賞を取らないといけない。つまりキャリアの出発点で、誰かからのお墨付きを得る必要があるわけですよね。当時は自分の小説の完成度がまだまだだということもあったけど、完成度がある程度の基準に到達しないと作家とみなされないというのも、おかしな話だと思うようになって。
でも演劇や音楽なら、劇場やライブハウスでお客さんを集めてしまえば、既存の権威からの承認を得ずともみずから名乗って活動をすることができます。アフタートークのゲストや広報戦略もぜんぶ自分たちでつくっていけることも、演劇を表現手段に選んだ大きな理由でした。
石川さんが言うように、はたから見ればイキってるカンパニーと思われているかもしれないけど(笑)、そうではなくて、ジャンルに関わらず自分が好きな方を呼ぶことで、同じものが好きなひとや、これまで本や映画には興味があったけど演劇を見てこなかったひとが、お客さんとして僕の演劇を見に来てくれる。「演劇ってバカにしてたけど、意外と面白いじゃん」と思ってくれたら、それ以上のことはない。もちろん、既存の演劇の文脈の中で、観劇がもともと好きなお客さんに見てもらうことも大切にしたいと思っています。
ちなみに今は、ロビンも小説を書いています。
ロビン:はい。役を演じていると、自分の書きたいことが出てくるんです。文章での、「だろう」や「していた」などの時制表現を、観客の目の前に体があるという演劇の場でどうあらわすかなど、小説と舞台との表現の違いがおもしろいです。
石川:ぼくも、パフォーマンスや現代美術に関わっています。
小野寺:わたしたちのつくる演劇自体、小説や映画から着想を得たりなど、他ジャンルと往還しながらつくっている感覚があります。
演劇と世界がつながる「代理性」と「役」の問題

――今作は、前作の『脱獄計画(仮)』と世界観を同じくし、共通する登場人物もでてくると伺いました。まずは前作についてお聞きします。原案をアドルフォ・ビオイ・カサーレスの小説『脱獄計画』にした決め手はなんだったんですか。
山本:『脱獄計画』は、「総督」と呼ばれる刑務官のトップが、囚人を使って身体感覚の人体実験をする話です。手術をされた囚人は五感の感覚が入れ換わって、見るという視覚から、触っているような触覚がうまれたり、痛みが音楽として聞こえたりする。しかしその様子を見ている主人公からすると、囚人が狂ってしまってなにか奇妙な行動や発言をしているように見えるわけです。たとえば、囚人自身は刑務所の外を歩き回っていると感じているのに、実際には狭い独房をゆっくり一周しているだけだったりする。これはまさに演劇で起こっていることのように感じたんです。
ただ、そのまま演劇にするのでは小説の表現には勝てません。物語の印象としては似ても似つかないものかもしれないけど、原案に対するある種の批評になるものとして作品を作っていく。それはタルコフスキーの映画『サクリファイス』を下地にした今作も同様ですね。
原案の論理や言葉を引き受けながら新しいものを書くという方法は、ここ数年かけて取りくんでいることです。
――今作ではA.タルコフスキーの映画『サクリファイス』が原案ですね。こちらにも演劇性が関わっているのでしょうか。
山本:はい。タルコフスキーには、「代理性」や「役」の問題がある。
「代理性」は、『サクリファイス』の前にタルコフスキーがつくった作品『ノスタルジア』に顕著です。 映画の後半で、核戦争が起きて世界が終焉するという妄想から何年もひきこもっていた男が、焼身自殺をしてしまうんです。そして、その男が信じていた「温泉の端から端までを蠟燭の火を消さずに渡りきることができれば世界は救われる」という儀式を、男の死後に主人公が代わりに実行する。つまり主人公自身ではなく、死んだ男の役として、温泉を渡っている。「誰かの代わりに何かをする」という行為は、もしかしたら彼自身の宗教観から来ていたりするのかもしれないけど、僕自身は演劇的だという印象を持ったんです。
今作の原案にした『サクリファイス』でも、「役」の問題が描かれています。たとえば、核戦争を避けるために、主人公アレクサンデルが女中のマリアと一夜を共にするシーンがあるんですが、マリアが魔女であることは、映画の中では明示されていません。むしろマリアはただの女性でしかなく、アレクサンデルもまた、ただの中年男性でしかない。しかしアレクサンデルは世界を救う救世主の役を引き受け、マリアは何が何だか分からないまま「魔女」の役を押しつけられる。なにかを成し遂げるために引き受ける「役」、そして他人から押しつけられる「役」の暴力性と、それによってある人間が「犠牲」となること。それは演劇においては俳優と観客の問題ですが、一方でそれは、社会で生きていくうえで押し付けられる「役割」の暴力性と重ねて考えることもできると思うんです。
――社会と演劇が、「役」を媒介にすることで重なって見えてきますね。
山本:はい。でも僕はいま、通りのいいことを言い過ぎたかもしれない。
今回の戯曲では、演劇を上演するために複数の人間が意志をもって集まる、そのことが主題のひとつです。このインタビューも含めて、どんなに社会的に意義のあることを発信しても、今の時代に、ひとつの演劇作品がもたらす社会的効果はわずかなものです。それでもどうして僕らは劇場に集まって、演劇をやったり見たりするのか。今僕が話したような、分かりやすい社会的な意義のようなもの、それ以上の何かが必要なように感じます。
いま、自分にとってそれを考えるための手立てとして中心にあるのが「役」なんだと思います。ぼくは「役」を「場」として捉えているんです。たとえば人がハムレットを演じるという行為は、ハムレットという「役=場」に、演者と観客が「集まる」ということなのではないかと。そしてその「役=場」に集まる人たちは、いま演じたり観たりしている人たちだけではない。「役=場」を介すことで、そこに関わる過去の死者たちや、そしてこれから関わるだろう未来の人たちも集まることができる抽象的な場だと思っているんです。
物理的な「場」とはちがう次元に、「役」を介すことで「集まる」ことができる。それによってはじめて、自分が生きている社会と演劇の接点を考えることができると感じています。
――今作で挑戦したいことはありますか。
石川:戯曲と比べて上演は一瞬で消えてしまいます。そのことについて俳優として考えていきたいですね。
ロビン:ぼくは見る・見られるという観客との距離を感じながら、演劇にしかない効果に挑戦したいです。たとえばト書きに「手を叩く」とあったとき、ト書きの指示に則すそのセリフを言いながら、違う動きをするほうが、なぜかリアリティが生まれたりするんです。
油井:わたしは俳優として何をしたいなどは正直あんまりありません。みんなと対話する時間を大切にしていきながら、ひとつのものをつくっていけたらと思います。
小野寺:今回、この規模で上演をするのは劇団としてはじめてです。拠点の東京以外の場所でももっと活動していきたいので、そのきっかけになれたらと思います。
戯曲の時間と上演の時間
山本:石川さんが戯曲は残ると言ってくれたけど、ぼくは上演のほうが残るのではないかと最近考えています。1000年後に僕の戯曲はきっと残らない。でも、上演がおこなわれるということそのもの、僕が書いているという行為そのものは残るのではないかと。
ぼくは、小説家の保坂和志さんから強い影響を受けています。保坂さんは自分が死んだ後もこの世界はあるということを実感するために芸術をやるんだと言われます。自分が生まれる前にも世界はあり、この私よりも世界は大きい。死んだら終わりという世界観とは別の考え方ですね。
戯曲が未来の上演に対する指示だとすれば、上演は過去に書かれた戯曲を組み替えることで、新しい現実をつくりつづけることが可能なのではないか。上演行為は、過去の上演、そしてその場に立ち会っていたお客さんを含む世界の現実を変えることができると思えてきました。
――過去、現在、未来、複数の時間軸の関係性は今作でも重要なものになりそうですね。
山本:さまざまな時間軸やレイヤーを共存させたいという思いがあり、ぼくの戯曲は様々な次元がいくつも折りたたまれた構造になっています。
今作でいうと、過去にロームシアター京都で1度きりで中止になった上演の記録があった。当時の出演者たちがその過去の記録にたいしてコメントをつけて増補版を出版した。それをもとに上演をする、という設定です。過去を現在につなぐ「記録」と、未来につなぐ「戯曲」の関係性が見えてきたらいいなと思います。

Dr. Holiday Laboratory 集合写真 撮影:マコトオカザキ
◆公演情報
2024年12月13日(金)、12月14日(土)、12月15日(日)
13日(金)19:00
14日(土)13:00★/18:00★
15日(日)13:00★
★上演後、アフタートークあり。
ゲスト
12/14(土)13:00公演 塚原悠也(アーティスト/contact Gonzo メンバー)
12/14(土)18:00公演 倉田翠(演出家•ダンサー•akakilike主宰)
12/15(日)13:00公演 保坂和志(作家)
会場:ノースホール
≪関連企画≫
詳細は公演ページをご覧ください。
・アンドレイ・タルコフスキー『サクリファイス』上映会&トーク(11月30日(土))
・スパイス料理店izon コラボレーションカレー(12月1日(日)〜15日(日))

