演目の定期的な上演から若手継承者の育成に至るまで、日本の伝統芸能にとって専門劇場が果たす役割は大きい。ロームシアター京都が主催し、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一氏が案内人を務める「伝統芸能入門講座〜芸能の在る処〜」は、こうした芸能を育む場としての専門劇場に光を当てた講座シリーズである。2022年度の2回目は「京舞」をテーマに、10月27日(木)にロームシアター京都ノースホールで開催された。京舞井上流の若き伝承者である井上安寿子氏、近世・近代の日本舞踊史研究者である岡田万里子氏(桜美林大学リベラルアーツ学群教授)をゲストに迎え、数ある日本舞踊のなかでもひときわ異彩を放つ「京舞井上流」の特色、拠点とする街や劇場との関わりがひもとかれ、時代を超えて愛される魅力に迫った。
唯一無二の特色をもつ「京舞井上流」
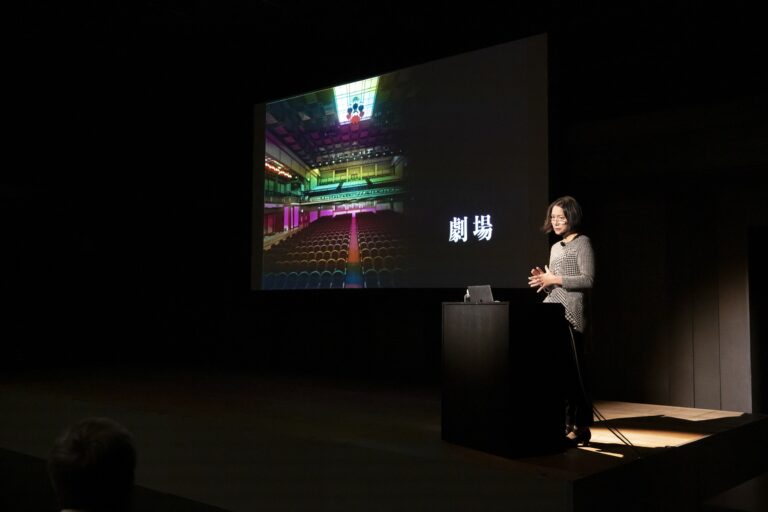
岡田万里子氏 撮影:桂秀也
講座前半は、『京舞井上流の誕生』(2013年発行、第35回サントリー学芸賞ほか受賞)を著した岡田万里子氏による講義が行われ、岡田氏が緻密な調査から得た新知見を交えながら、京舞井上流の歴史、劇場やレパートリーに見る特長などが紹介された。
「京舞」の名を冠す井上流は、200年前の京都で誕生した座敷舞の流派。その主な特徴として岡田氏は、①京都の祇園で伝承されてきた舞であること(花街・祇園甲部における唯一の流派)、②男性が率いる流派も多いなか、基本的に女性のみで受け継いできたこと、③歌舞伎の影響を受ける流派が多いなか、能や人形浄瑠璃の影響が多く見られること、④後ろ重心で舞う流派が多いなか、「前重心」で腰を落とした姿勢が基本になることを挙げた。実際に映像資料(講座では国際交流基金作成の動画が紹介された)で観ると、たおやかで品がある舞姿ながら、随所に能の型、人形浄瑠璃の振りを取り入れたキレや美しさ、独特の躍動感が息づいていることがよく分かる。
井上流の創始は江戸後期 、初世・井上八千代(1767-1854)が五摂家のひとつである近衛家に行儀見習として奉公した後、宿下がりの際に賜った「八千代」を名乗り、舞の稽古所を開いたと伝えられている。現存する最も古い 記録は、文政五年(1822)の京名物を紹介する書物に記された「舞ノ振付ノ八千代」という記載。二世は初世の姪が、三世、四世はそれぞれの弟子が継いでおり、現家元である五世は四世の孫 となる。
井上流が祇園町と深く関わるようになったのは、三世・井上八千代(1838-1938)の時代。明治5年(1872)、東京奠都の影響を受けた京都は「第一回京都博覧会」を開催し近代都市への道を歩み始めたが、この時の附博覧(余興)として行われたのが、三世の指南で誕生した「都をどり」であった。これが大成功を収めたことで、井上は祇園町の芸舞妓に舞を教えることとなり、やがて祇園町一帯を拠点とすることに。他流や他の花街にはない「一対一の結びつきを成し遂げた」流派は、その個性をさらに磨き上げていったという。なお、井上流が京都以外で一般向けの公演 を行ったのは、戦後に四世(1905-2004 人間国宝)が継承して以後のこと。「京都の外に舞が知られることで、その独創性がさらに珍重されるようになった」 と岡田氏。奇しくも、京舞の興隆は、戦後に「古都」としての京都のイメージが醸成され、京都ブームが巻き起こった時代と歩みを一にしていたという。
井上流における「劇場」を考える
「本講座のテーマである『劇場』と『レパートリー』は、井上流の大きな特色そのものである」と語った岡田氏。まず劇場についてだが、井上流が指導する花街・祇園甲部は「祇園甲部歌舞練場」という専用劇場を有しており、ここが流派にとっての実質的な本拠地となる。芸舞妓による春の「都をどり」、秋の「温習会」のほか、流派の襲名披露も行われており、「このような大きな劇場をホームとして持っている舞踊流派は他に類がない」と岡田氏は指摘した。
また、古き良き風情を残し、芸妓舞妓が行き来する祇園町そのものが、井上流の舞を守り育ててきた母胎のような存在であると岡田氏。その意味で「祇園町自体を、井上流の劇場と捉えることもできる」と語った。
なお、初代の歌舞練場は「都をどり」が始まった翌年、明治6年(1873)に開場 。元は建仁寺の広大な敷地であった祇園町南側が明治時代に花街に払い下げられ、計画的な街づくりが行われるなかでの誕生であった(花見小路が生まれたのもこの時)。その中心となったのが「婦女職工引立会社(八坂女工場)」。当初は芸娼妓解放令を受け、芸舞妓に手工芸を身につけさせる教育機関として誕生したが、次第に音楽や舞など芸の修業に関するカリキュラムが増え、現在のような芸舞妓の養成機関となったという。
歌舞練場は大正2年(1913)に現在地に移転・新築され、規模を大幅に拡大。昭和28年(1953)に一度目の大改修が行われ、2023年春には「令和の大改修(耐震改修)」が完了し新開場。なお、隣接して建つ「弥栄会館」は昭和12年(1937)の竣工で、当時の新しいニーズに応える劇場として誕生し、オーケストラピットも備えていた。
歌舞練場では舞台の両側に花道が設けられており、「これが劇場らしい高揚感を生み出す最高の装置となる」と語る岡田氏。都をどりではここから舞い手が登場し、両花道 の背後には地方・囃子方がずらり と並ぶため、三方から芸舞妓に囲まれるなかで華やかに演目が進行していく。

辻村多助 編『都をどり』大正2年刊,歌舞練場,大正2-3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2387737 (参照 2023-04-13)
伝承作品に見る、失われた上方芸能のDNA
流派の規模としては決して大きくない井上流だが、「過去3度にわたり、流派の歌詞集を出版し続けてきたことも特筆すべき点である」と岡田氏。 そこには、レパートリーを尊重しようとする彼らの明確な意思があり、流派の教科書としてだけでなく、伝承曲のアーカイブにもつながり、さらには鑑賞の手引き、邦舞・邦楽研究者の資料としても充分活用することができるからだ。刊行年は昭和16年、26年、40年で、最新刊は国会図書館のデジタルコレクションで閲覧が可能。昭和40年版の掲載曲数は廃曲も含めた289曲で、井上流独自の上方唄または義太夫は33曲を数え、「お七」「信乃」「伊達奴」「もさ順礼」「弓流し物語」など、現在もよく舞われる作品も多く含まれるという。
独自曲のなかには、「江戸時代には上方の複数流派で舞われていたが、いつしか他流では淘汰されてしまい、井上流にのみ残った」と考えられる曲があることを岡田氏は指摘する。また、文楽では途絶えてしまった演目の一部が形を変え、井上流の曲としてタイムカプセルのように保存されている例も。これが可能であった理由は、井上流が祇園町に長く根差し、花街と流派が一対一の関係を続けてきたため。「もしも他流のように複数 の花街で教授していれば、流行の影響を受けて、人気曲以外は伝承されなかったかもしれない」(岡田氏)。
さらに岡田氏は、井上流の「地方(じかた:唄と三味線)」の特殊性も指摘する。祇園甲部では立方(たちかた:舞手)と地方を同時に養成するため、地方もまた、舞とともに曲の保存を支える重要な存在。「音楽が途絶えることで、演目が上演できなくなる ことも多い」と岡田氏。今後の伝承を考える上で、地方の保護・育成も重要な課題となってくることだろう。
講義の最後に、あらためて京舞への想いを語った岡田氏。「流行が瞬く間に過ぎ去り、人のつながりも希薄になりがちな現代において、祇園町で育まれた井上流の舞には、時代を超越して心に響く美しさや味わいがある。今後もそうした良さを大切にしてほしい」と結んだ。昨今は「クールジャパン」として、新しいアートの売り出しに躍起な日本であるが、「日本が誇る伝統芸能である京舞は、世界からみれば『日本』を劇場とした芸術ともいえる。令和の現在において、新しい視点で京舞を論じ直すことも可能」とも語った。

令和5年 祇園新地甲部歌舞練場 新開場記念 第149回都をどり
撮影:カリテリンク 写真提供:八坂女紅場学園
【クロストーク】二百年のバトンを次世代につなぐために

左から木ノ下氏、安寿子氏、岡田氏 撮影:桂秀也
続いて岡田氏のレクチャーを振り返りながら、安寿子氏、岡田氏、木ノ下氏による鼎談が行われた。京舞の後継者である安寿子氏からは、舞の基礎となる「おいどをおろす(お尻を低く落とす姿勢)」の実演、井上流の紋の由来、これからの京舞への想いも明かされ、安寿子氏の若くみずみずしい感性にもふれられる機会となった。
江戸時代を生きた初世 と二世が築いた基礎を、三世が「都をどり」の創始によって一気に躍動させ、さらに四世が東京公演や新曲の創作を通して京都の外へと開きながら大成させ、現在を担う五代家元へと繋いできた井上流——。木ノ下氏は、講義を受けてあらためて「八坂女紅場での指導や出版事業に見られるように、井上流が“舞の教育や普及”で大きな役割を果たしてきたことを実感した」と語った。安寿子氏は、昭和40年刊の歌集には膨大なレパートリーが収録されているが、日常的に舞われているのは30曲ほどであること、ただし、音源や映像が残っているものもあるので「復曲にも挑戦してみたい」と語った 。
また、レパートリーの伝承で憂慮される点として、「立方(舞手)」と「地方(三味線+歌)」が分業されている祇園甲部において、地方の高齢化と減少を挙げた安寿子氏。他流派の地方で舞うこともあるが、「やはり舞っていて、安心感があるのが祇園甲部の地方。この文化を大切にしていきたい」と述べた。
今後の京舞の展望として、安寿子氏は「今の世代の方々は、『京舞を見ると懐かしい気がする』と多少なりとも共感してくださるが、今後は『見たこともない、古くさいもの』と思われてしまう可能性がある。将来の六世継承も見据えながら、京舞という古典が芸術作品と生き続けていくため道を模索していきたい」と力強く語った。木ノ下氏は、「京舞は能・浄瑠璃との関係も深く、昔の上方芸能のエッセンスが凝縮された宝箱のようでもある。舞や伝統芸能を学びたいという次世代の人にとって、教育的な意味でも重要な役割を果たしていくのではないか」と語った。

流儀の紋「井菱」を見せる安寿子氏 撮影:桂秀也
また、京舞の継承において「観客を育てる」ことも重要なポイントである。演目の知識や時代背景を知らずに鑑賞すると「つまらない」と感じてしまう可能性もあり、「観客が京舞を見る前、見た後に観客をどうサポートできるのか?」についての意見交換も行われた。
「京舞には圧倒的な身体性、アクロバチックな動きが あり、自分が出会った頃は知識がなかったが、ただただすごいと圧倒された。ぜひ、素直に感じて楽しむ良さも大切にしていただけたらうれしい。座敷のみならず、大舞台での舞や群舞も映えるのが井上流の魅力なので、ぜひ国際的な舞台でも演じていただきたい」と岡田氏。「子どもの頃から京舞に親しみを感じていただくため、不定期で保育園や小学校でワークショップを行っている。母校の京都芸術大学でも教えているが、現代の子は日本舞踊になじみがないので、『学んでみたい』と感じてもらうきっかけづくりも必要だと痛感している」と安寿子氏。
一方、「京舞を深く知るきっかけさえあれば、古典沼に一気にハマる人も増える可能性がある」と木ノ下氏。例えば京舞の「八島」は、能の屋島に取材した本行物。その背景にはドラマチックな平家物語の「屋島の合戦」があり、京舞にはこうした歴史や物語のエッセンスが巧みに凝縮されている。「ベースにある2つの物語を知った上で鑑賞すると全く異なる見え方、面白さに出会えるはず」(木ノ下氏)と語るように、現代を生きる人の視点で「エンターテインメント」としての魅力を紹介していく可能性も示唆された。
限られた時間ではあったが、数ある日本舞踊のなかで京舞だけが持つ豊かな魅力、上方舞や上方芸能との深い関わりが解き明かされた本講座。「実際に生の舞台を観てみたい」と感じた人も多いことだろう。2023年春の現在は、大改修を終えたばかりの新生・祇園甲部歌舞練場で初の「都をどり」が開催中。ぜひこの機会に、京舞の世界にどっぷりとひたってみてはいかがだろう。

岡田氏の著書『京舞井上流の誕生』を紹介する木ノ下氏 撮影:桂秀也
![芸能の在る処~伝統芸能入門講座〜 京舞編[ゲスト]井上安寿子 岡田万里子 [案内人]木ノ下裕一](https://rohmtheatrekyoto.jp/wp-content/uploads/20221027_J_kyoumai-768x432.jpg)
