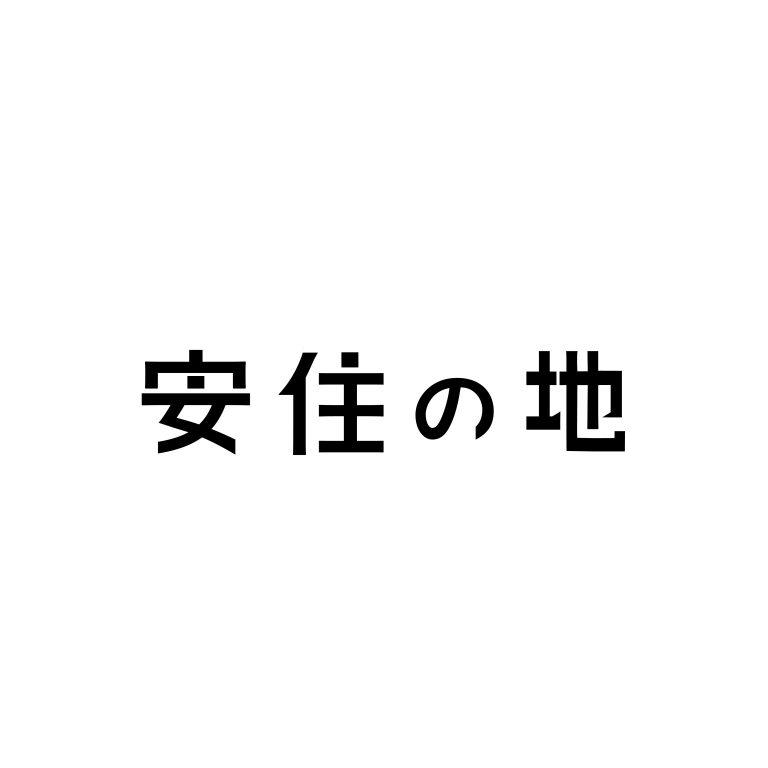撮影:山下裕英
演劇文化の更新に向けて
京都を拠点に活動する劇団・安住の地のメンバーで、劇作と演出を行う私道かぴ。書くという表現行為を通して、近年では演劇以外の分野にも活躍の場を広げている。
私道が戯曲を書くようになったのは、立命館大学の学生劇団・西一風に参加してからだが、すでに小学生の時に小説を書き始めていて、中学2年生の時には叔母に誘われて初めてプロの演劇を観たという。
「難しいと思っていた」という戯曲と小説の違いを、形式の問題だと考えていたが、自身の戯曲『丁寧なくらし』が最終候補にノミネートされた第20回AAF戯曲賞の公開審査会を経て、戯曲は演じる身体の可能性を内包していなくてはいけないことに気づいたという。演出も手掛ける私道にとって、それは戯曲を俳優に預け、共同作業で作品を創るということにつながる。
そのような共同での作品作りは、主宰者によるトップダウン的なリーダーシップを排し、劇団メンバーの対等な関係性を構築しようとする、安住の地の方向性とも軌を一にする。演出家が「謎を残したまま」俳優と一緒に考えていくことで、作品はおもしろくなるという。
安住の地はまた、岡本昌也と私道という二人の劇作家/演出家を擁している。そして、二人による共作にもこれまでに二回挑戦している。初めてこの試みを行ったのは、2018年度の「ロームシアター京都×京都芸術センター U35創造支援プログラム”KIPPU”」[*1]に採択され、ロームシアター京都ノースホールで上演した『ポスト・トゥルースクレッシェンド・ポリコレパッショナートフィナーレ!』。そして、二作目が、金沢21世紀美術館で先月上演された『¡play!』だ。二人での作業では、戯曲執筆から演出まで、互いに意見を交わしあい、強度を高めて行く。他分野から幅広いゲストを出演者やスタッフに迎えることも、共作公演の特徴だ。
このような試みに、より多くの、幅広い観客層に作品を届けようとする劇団の姿勢がうかがえる。そこには、私道自身の作家としての思いも重なる。最近は、「父親」をテーマに執筆を行うことが多いが、自身の体験が反映されながらも、その私的体験にいかに社会性を持たせられるかということを意識しているという。そして、自身が描くテーマが誰かに届く「打率」をあげるため、映像や美術といった演劇以外の分野にも足を踏み入れている。その背景には、演劇という枠に縛られることなく、演劇文化を更新していきたいという決意が潜む。
その一方で、私道の関心は、大都市以外の地方での活動にも向けられている。コロナ禍の中で、たまたま山形で1年間暮らすことになった体験からその関心は芽生え、その後、長野や愛媛でのアーティストインレジデンスを経験している。
演劇という土俵を中心に、私道がこれからどのような物語を書いていくのか。安住の地の今後の活動と合わせて、注目していきたい。