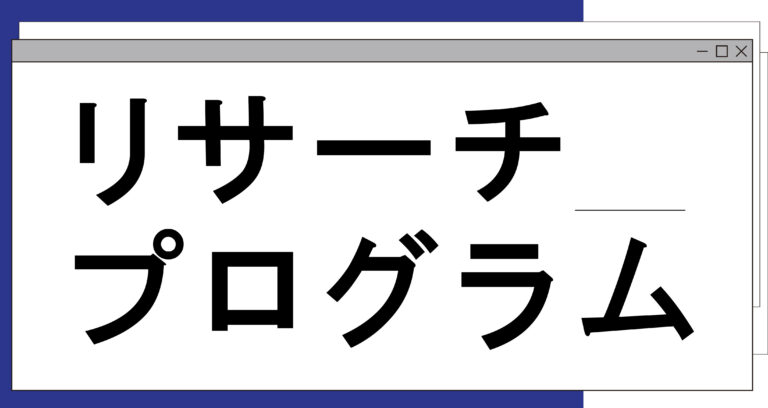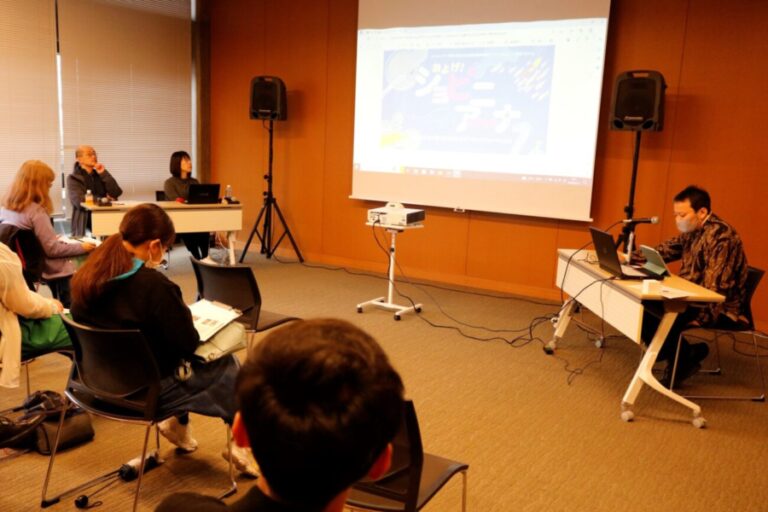開催日:2025年3月26日(水)
リサーチャー:(【】はテーマ、*は自由テーマ)
【自由テーマ:観客文化、対話型鑑賞、劇場におけるコミュニティ創成】中山佐代(なかやま さよ)
【自由テーマ:リサーチ・ベースド・アートの輪郭と社会的主題との関係】中山恵理那(なかやま えりな)
【テーマB:(子どもと舞台芸術)とC(舞台芸術のアーカイヴ)の横断型】橋爪 皓佐(はしづめ こうすけ)
【テーマA:現代における伝統芸能】奥田知叡(おくだ ともあき)
中山佐代「劇場における対話型鑑賞の実践」

数十年前から劇場の敷居は次第に高くなり、もはや観劇すること自体ニッチな趣味と言われるようになってしまった。そうした状況下で、演劇や劇場の公共性についてはどう考えれば良いのか? 多勢に開くばかりが公に資することではない。演劇と公共性の問題は、それがそもそも何を意味しているのかという、根本的な問いから始めないわけにはいかない。
中山は、美術分野で開拓されてきた「対話型鑑賞」にヒントを得て、舞台上演をめぐる対話を敢行した。少人数の参加者で、複数の作品の鑑賞後、何度か集まり、車座になって話すという建てつけだった。必然的にそこには親密さが生じる(発表を聞きながら、私は岡原正幸の「感情公共性」の議論を思い出していた)。同じ上演を観たという共通の体験が、参加者の共同性を大きく変えた。おそらく鑑賞中、対話メンバーの顔がちらついた人もいたはずだ。「あの人はこの上演をどう観ているかな、何て言うかな」云々。こうした鑑賞態度を不純だとみなす向きもあるだろう。ただ、そもそものはじめから劇場での鑑賞は共同のものだとも言える。観客席に座っていれば、必然的に隣の人の観劇態度も目に入ってくるのだから。
本リサーチでは、閉じることで開かれるという公共の可能性が垣間見えた。対話の場の建てつけ次第、構成メンバー次第で、他の関係にもなりえるはずなので、継続的な実践と探究が期待される。
橋爪皓佐「ワークショップをスコア化する:創造的リスクを受け入れるための実践的アプローチ」

橋爪は誰にでも利用可能な、ワークショップ(WS)のスコア作成を目論んだ。私も演劇WSにたずさわっていたからよく分かるが、指示書やルール設定だけあっても上手くはいかない。例えば子どもが「次は何を、どうすれば良いのか」と不安な表情をしているのを見るや、大人はつい声をかけてしまう。「ここはこうすると良いんじゃないかな」などと口を出す。そうした指導の場ではないとみんな分かっているにもかかわらず。あくまで善意から。結局のところ、WSの成否はファシリテーターの力量に依存するところが大きい。だが大人のそうした介入癖をも見越したスコアがあったとしたら、なんと素晴らしいことだろうか。
リサーチの過程で、橋爪は「創造的リスク・テイキング」に関する研究に出会った。アーティストは常に、完全な暗闇の中で第一歩を踏み出さなければならない。創作の始まりはリスク・テイキング以外ではありえない。したがって、創作WSに不安や当惑はつきものだが、自信をもって惑って良いのだ。この確信は、WSファシリテーターにとっては極めて大きい。
ただし。ふつうスコアとは、むしろリスクを軽減するためにある。リスクを担保するためのスコアというのは語義矛盾にすら聞こえるが、おそらくこの収まりの悪さこそが肝要。ひとまず完成したスコアのプロトタイプを改良していく作業それ自体に、大きなリスクのチャンスが潜んでいるに違いない。
中山恵理那「パフォーミングアーツの創作における「リサーチ」観の変遷—市原佐都子/Q『キティ』を事例に—」

「リサーチ・ベースド・アート(RBA)」という言葉を目にするようになって久しい。もともとは現代美術の文脈から出てきた言葉だが、近年では演劇その他パフォーミングアーツのまわりでも聞かれるようになった。しかしどんな芸術表現だって多かれ少なかれリサーチはしているだろう。RBAに単なる流行以上の意味があるのだろうか? ……と思っていたが、報告を聞いてよくわかった。現代の芸術/家をとりまく状況を理解するのに、「リサーチ」を経由するのは極めて重要だ。
とりわけ2011年の東日本大震災を境に、リサーチの位置づけが変わっていったという話には得心した。アーティストの多くは、震災を無視することはできなかったが、しかしそれを軽々に題材にするわけにはいかない。何かを、誰かを、なるべく毀損しないように、表現の倫理を担保するような態度のもと、地域のこと、人のこと、原発のことなどリサーチを進めるアーティストたちが登場したのである。
しかし無論、芸術は研究とは違う。リサーチが最大の目的になってしまっては、本末転倒だろう。あくまで世界との接し方の一つであるはずのリサーチは、どのように実行、活用されているのか。現代のアーティストたちは、リサーチとの距離の取り方を改めて誠実に模索し始めている。鑑賞者側もまた、こうした「リサーチ」のあり方に着目してみることで、芸術文化への理解が一層深まるのではないかと感じられた。
奥田知叡「能公演の劇場進出および能様式の現代化をめぐるリサーチ—戦後の「新様式能」から近年の「劇場能」まで―」

芸術文化をめぐる難題は多々あれど、「伝統芸能と現代」問題はその最たるもののうちの一つ。数百年続く芸能は、ジャンルとしての統一性を保ちながらも、各時代にあわせてつねに少しずつ形を変えてきた。しかし「無形文化遺産」などというラベルを貼られると、とにかく伝統を保存せねばという気にもさせられる。そうして保護の対象になったものを、はたして芸能と呼ぶことができるのだろうか?
奥田は現代における能表現の可能性を探るため、ひとまず戦後の「新様式能」に焦点をあてた。能受容のあり方の変化(財閥の解体などによる固定客の減少)、能楽堂の焼失/建立の動向、そういった状況における試行錯誤を詳細に調べ上げた。当時の試みのラディカルさには驚かされる。能舞台を離れ、橋がかりのない一般の劇場へと赴いたり、西洋的な思想内容を取り入れたり。行ききったものだと、「ヌード能」のようなものまであったらしい。
ただし、ラディカルであれば良いというのでもない。改良を目論んだ挙句、原型が何だったのか分からなくなるというのはよくある話。能を能たらしめるものは一体何なのか? 様式なのか、精神なのか、制度なのか、人なのか……奥田は自身でも現代能の実作を画策しているらしい。先人たちの様々なチャレンジを受けて、一体どんな創作に行き着くのか、興味をそそらないではおかない。
最後に、私の話を。
私もまた、2019、2020年度のリサーチャーであった。大学院での哲学研究に挫折し、しばらく右往左往した後、リサーチプログラムのうわさを聞きつけて、「子どもと舞台芸術」の枠に応募した。演劇と教育には強い関心があったものの、しかし問題意識は茫漠としていた。面接では「結局あなたは何がしたいのか」と問われ、確かにそれも明瞭でなかった私はその場で(実際に)泣きべそをかいたにもかかわらず、なぜだか拾ってもらえた。リサーチャーとしての2年間、演劇WSの調査の間も右往左往し続けて、しどろもどろに発表をどうにか乗り切ったのだった。しかし最終報告書の内容には、私自身いまだに触発されている。
メンターの吉岡さんに「渡辺くんは調査対象を外から研究するのではなく、自分もまさにその中に入っていって、内側からともに問題に取り組み、思い悩む、人類学的な参与観察をしている」といった旨の指摘を受けた記憶がある。そしてそれは必然的に「研究している「自分」とは何かを問うことになる。結局のところ渡辺くんは自分を研究対象にしているようで面白い」といったようなコメントだった、と思う。
実のところ、当時の私は人類学などほとんど知らなかったし、あまりピンときていなかった。とりとめのない私の話を無理矢理擁護するために優しいコメントをくれたのだと思っていた。しかしあのときの思索の歩みは稀有なものだったということが、今になってようやく分かってきた。
大学院などの研究機関では、ディシプリン(各学問に固有の体系的方法や考え方)がすでにあり、それにのっとった仕方で研究を進めないわけにはいかない。修士号をとるためには、基本的な学問の作法をマスターするのが必須である。これもまた間違いなく重要な歩みだが、しかし芸術について(ひいては人間について、世界について)理解を深めるのに、ディシプリンの習得が最優先だろうか、とも思う。訳も分からず駆け出し蹴つまずく、転んだ先の小石に想いを馳せる、そうしてようやく自分のまわりに広がる風景の彩りに気づき始める、そういったことの一つ一つが探求なのではないか、と思う(こうした態度については、人類学者、哲学者のブリュノ・ラトゥールが後押ししてくれた)。人文科学も煎じつめれば一つのなのだ。きっかり定められた指示書の通りに進むだけでは、大きな成果にはつながらない。
今年度のリサーチャーもまた、最初の目論見から結論まで一直線、というわけではなかったようだ。様々な問題に直面し、テーマや方法を度毎に検討し、最終報告にどうにかこぎつけた、その痕跡がはっきり見てとれた。そしてそのいずれもが、次なるリサーチを期待させるものだった。リサーチャーの誰一人、「最終報告会」で調査が終わったなどとは思っておらず、すでに次を見据えた構えをとっていた。
本リサーチプログラム自体が、創造的リスク・テイキングの場である。月並みに聞こえるかもしれないが、まさにそうなのだ。何かを修めることができたと証明できなくても構わない。闇のなかを確かに一歩踏み出したという事実は残る。その一歩が、次の創作をどれだけ鼓舞することか。効果のほどは、はかり知れない(それだけに、ここでの挑戦が、リサーチプログラムの中だけにとどまらず、いっそうの公共性を獲得していく姿にも期待したいところである)。
リサーチャープロフィールはこちらのページからご覧いただけます。