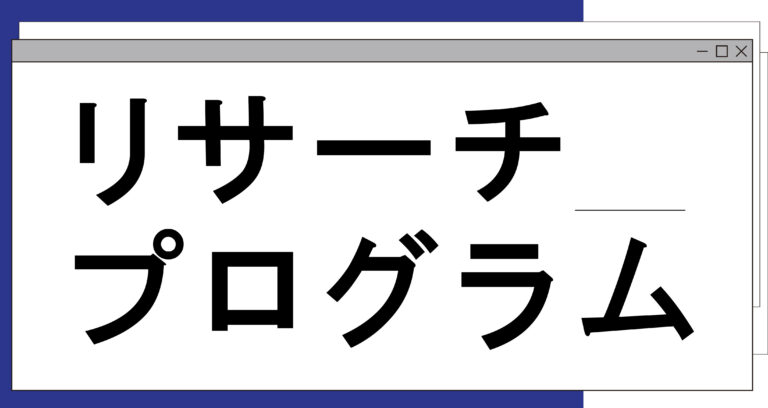はじめに:アカデミシャンを招き入れる
「リサーチプログラム」をご存知の方はどれほどいらっしゃるだろうか。実のところ、ロームシアター京都は研究活動にも力を入れている。「舞台芸術のアーカイヴ」、「現代における伝統芸能」、「子どもと舞台芸術」の3つを課題に挙げ、若手研究者・批評家を招き入れて研究と実践を繋げようとしている。アカデミックな人間が制作や文芸として創作に参加することはよく耳にするが、観客の代表として意見を交わすことはなかなかない。
劇場というと、つい舞台上で表現される作品を思い浮かべる。しかし劇場は創作者と観客が向き合う場所であり、「劇場文化」をより豊かにしようと考えた時、両者の声を聞くことが必要となる。しかし、表現する人たちの思いは創作や作品を通して伝わってくるが、観客の思いを知るのは難しい。劇場スタッフが観客の方へ積極的に意見を聞きにいかなくてはならない。アンケートや批評も貴重だが、この企画で、創作者、観客、劇場が互いに顔を合わせることで、より深い対話が生まれるのではないかと期待している。
以下、3月23日に開催された報告会と、提出された報告書の内容から受けた印象を記す。公開されたリサーチ資料に目を通される際の一助となればと思う。
「舞台芸術のアーカイヴ」:創作のプロセスを記録する
時間と共に流れすぎてしまう舞台芸術をいかに記録し、残すのか。アーカイブと聞くと、より学術的で遠い印象を受ける。しかし劇場に訪れる人であれば、日常的にアーカイブに触れているだろう。戯曲、CD、ビデオと、上演そのものは残らないが、その断片は意外と身近なものである。さらにインタビュー記事や劇評、歴史・理論書などもアーカイブの一部だ。
この課題に取り組んだのは朴建雄と松尾加奈の2名。いずれも1月27日-31日にノースホールで上演された松田正隆『シーサイドタウン』を研究対象とした。彼らのリサーチの特徴は、いずれも稽古場をアーカイブしようとしたことだ。先に挙げたテクスト、音源、映像はいずれも作品の記録がほとんどだ。稽古の様子というのは、多くの観客にとって想像もつかない。
まず、朴の報告書「ドラマトゥルギーを観察する—創作方法と上演空間の関連について」だが、これは『シーサイドタウン』の稽古場記録である。ドラマツルギーという言葉はドイツ語で、登場人物の「行動の文脈」をいかに表現するかを問う際に使われる。演劇史全体を見渡した時、作品をアーカイブするとなると、言葉が主な手段であった。その影響もあり、演劇は言葉によって成り立つ芸術だと思っている人が多い。しかし、それは違う。時代やジャンルによって、より重要とされる要素の比重は違えど、演劇というのは「やってみせる」芸術だ。創作の場にいる人たちにとっては当たり前だろうが、その輪の外にいる者にとっては新鮮な考え方だ。テクストを手がかりとして、どのように行動を構築し、物語が共有されるのか。そのプロセスを知ることで、上演の解釈に深みが増す。
とはいえ、誰でも稽古場に立ち会って分析できるわけではない。誰かが記録して持ち出す必要がある。その点に関心を寄せているのが、松尾の報告書「創作のプロセスの記録者」だ。特に第三者が立ち会うことについて記している。ただ、今回のリサーチで示された記録の意義は、制作やドラマトゥルク、文芸部がその役割を担うことができるように思う。外部の者としての記録者を立てる必要はあるのだろうか。第三者が稽古場に立ち会うことに抵抗を感じる創作者もいる。彼女もそれは意識してピーター・ブルックを挙げている。ただ、彼は創作のプロセスを公開したくないわけではない。稽古の様子を模擬的ではあるが映画にしてもいる。今回のリサーチで、松尾は創作者たちと良好な関係を築くことができたようだが、それは彼女が内部の者の一人であると認められたからでもある。客観的な内部者として、記録者がどう振る舞うべきかを考えていきたい。
「現代における伝統芸能」:現代に生きる私たちの視点
芸を伝承していることも、アーカイブの一手段だ。過去に演じられた「行動」を「型」として身体にうつしてゆく。和田真生もこの課題に取り組むにあたり、創作のプロセスに着目して考察している。対象としているのは、2020年11月2日-3日に上演された木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻』。和田は歴史研究をふまえ、興行形態から創作・表現方法に至るまで、江戸時代の江戸歌舞伎と現代の木ノ下歌舞伎を比較し、報告書「うつす・よみがえらせる—木ノ下歌舞伎と江戸歌舞伎の方法—」にまとめている。
演劇を翻案するとなると、一般的に戯曲を基として新しい作品を生み出すわけだが、木ノ下歌舞伎の場合はそうではない。俳優は役者の演技を「完コピ」することから始める。伝承されている行動を繰り返し、そこに含まれる心情を理解して行く作業へと移行する。そして最終的には、歌舞伎として伝承される行動が示すことを現代の観客に伝わるように仕立て直し、新たな作品となる。この木ノ下歌舞伎の創作プロセスは周知の事実だが、歴史資料と共に説明されることで、この翻案方法が正当なやり方なのだと納得する。
同時に、私たちの伝統芸能に対する固定されたイメージにも、注意を払わなければならない。報告書の結びに興味深い言及があった。この作品が観客にもたらした「不快感」についてである。『摂州合邦辻』には、差別用語やらい病の描写が含まれる。浄瑠璃や歌舞伎では伝統の一部として理解されるため、これらの点について問題提起する観客はほとんどいないだろうが、翻訳上演となると反応がある。観客が作品に対して疑問を持ち、創作者に意見することは誠実なことだが、古典作人の内容をめぐる対話は、伝統芸能の上演では起こりえない。それは、私たちが歌舞伎の型を単なる振り付けとして表面的にしか捉えておらず、行動に伴う心情を理解するにまで至っていないからではないだろうか。「歌舞伎は技を見に行くものだ」という言葉をよく耳にするが、木ノ下歌舞伎で作品の内容を理解した上で、歌舞伎を観ると新たな発見があるのかもしれない。
「子どもと舞台芸術」:子どもたちの自由と劇場
劇場は創作者にとっても観客にとっても自由な場所なのだが、子どもたちに対してもそれは守られているのだろうか。子どもを対象にした舞台芸術やその関連事業では、「自由」のほかに「豊かな感性」、「想像・創造」といった言葉を目にするが、渡辺健一郎と小山文加は、それぞれ研究対象は違えど、教育現場の厳しい現状を綴っている。
渡辺は演劇教育のしくみに着目し、報告書「演劇教育[の/で]力と自由を考える」で、自由になれない子どもたちに目を向けている。興味深いのは渡辺本人が固定観念に縛られている点である。演劇教育が教育である以上、ある程度の決まりが「先生」によって子どもたちに提示されるのだということを渡辺は意識していた。しかし、「それでも子どもたちのなすがままにさせるべき」といったメンターからの意見をきっかけに、混乱が生じている。具体的な事例を示さぬまま、議論を進めようとする渡辺の研究は、取りつく島がない。せめて調査対象となった「関西圏で行われた子ども向け演劇教育」の詳細を教えていただきたいところだ。厳しいことを言ったが、実のところ明治期より続く演劇教育の「自由」に関する記述の中に、簡潔なものを見たことがない。大人も子どももがんじがらめになっているケースをよく目にする。客観的な視点を取り戻すために、一度「自由」というテーマから離れてみてはどうだろうか。
一方、小山はまだ劇場に訪れたことのない子どもたち、特に貧困の中に生きる子どもに的を絞っている。報告書「子どもの貧困問題と劇場 参加機会の障壁の所在を探る」には、音楽教育を軸に、1990年代より盛んとなる文化公共施設のアウトリーチ事業と子どもの関係性についての考察が記されている。まだ具体的な解決には至っていないが、子どもたちの現状と、京都の支援団体や支援事業をまとめ、議論の基礎を築いている。
劇場は貧困にある子どもの居場所となれるかという問いだが、それには大胆な意識改革が必要だ。また歴史の話になるが、帝国劇場は設立当時から大衆的な内容を上演してきたにも関わらず、今も昔も高尚な存在として語られている。劇場は富の象徴として存在してきた。特に音楽文化は顕著で、教育ともなれば「一流音楽家による指導」や「一流の作品を鑑賞する」という内容が多く、歌を口ずさむことが好きな子どもさえ遠慮するような企画が目につく。小山は「子どもの劇場体験は大人に左右される」と述べているが、全くその通りである。劇場に子どもを連れて来る大人が少ないことも問題だが、芸術が不得意だと感じている人も思い切って足を運べるような企画が欲しい。
自由課題:人の行き交う場としての劇場
本年度よりロームシアター京都が提示した3課題に加え、自由課題の設定が可能になった。島貫泰介がテーマとしたのは「帰属」と「移動」だ。社会学、民俗学的なアプローチで劇場を起点とする人の動きを捉えようとしたようだ。
当初の予定では華人社会における「回葬」文化から新しい上演形態を模索するはずだったが、デモやCOVID-19の影響で香港での現地調査が叶わず、報告書の題目は「創造的な能動性を促すための『移動』の研究」となった。埋葬に伴う移動を糸口に、ギリシャ劇や伊勢参りなどの例を紹介し、最終的に劇場におけるアーティスト・イン・レジデンス制度に関する提言をロームシアター京都に宛てている。劇場はアーティストを「『滞在制作』という固定的で、それなりに長い期間を要する形態に留め置く」ことになるが、「より流動性の高い滞在のかたち、通り道の変奏としてのレジデンスを想定」するべきだという。これは、信仰拠点の持つ「帰属」とは異なる役割を劇場に求めていることになる。つまり、劇場は特定の思想を持たず、訪れる創作者や観客のなすがままにさせる場所として解放し、単なる通過点として存在するのも良いのではないかという考えである。
この提言から思い出したのは、東京のある大規模劇場での体験だ。海外アーティストに創作・上演の場を提供したが、劇場は取り組む内容をアーティストに委ねた。最終的に作品は完成せず、新作発表の場は報告会になった。数分ずつのエチュードを20分ほど見たが、解説はなく、何がなんだか分からなかった。さらに質疑応答では、ある観客が「これらが、新作の手がかりになりそうなのか」と尋ねたが、「これはほとんどボツになるでしょう、少しは形を変えて残りますが」と返ってきた。1年前から新作が観られると聞いていたのだが、私たちは何を見に来たのだろうか。報告会が進むにつれ複数の観客が離席していった。
果たして島貫の提言は観客をも納得させられるものだろうか。自由な表現ができることと、自由に居られることは異なる。レジデンス制度で何も生まれず、ただ資金だけが使われるようであれば、別の政策に回したいと感じるだろう。観客は何かが見たい。何も生まれなかったとしても、せめてそれに対する解釈が欲しい。多くの観客を抱える劇場には何かしらの評価基準、つまり「帰属」的な要素が必要になるのではないだろうか。
むすび:2021年度のラインアップをどう観るか
リサーチャーたちが共通して意識していたのは、自分自身の立ち位置だ。劇場では客席に座り受動的に振る舞っていた彼らが、創作者や劇場スタッフと対話し、現場に足を運ぶことによって、よりアクティブな観客の在り方に気づいた。創作者・観客・劇場の境界が曖昧になり、自分自身の存在を意識する新たな舞台芸術の楽しみ方である。
2021年度ロームシアター京都自主事業ラインアップには、3つの課題に関連した企画が並ぶ。中には昨年度から継続された企画や、報告書の内容を意識するとより面白く参加できるものもある。是非なにかテーマを持って劇場にお越しいただきたい。そして来年、同じ作品を見たリサーチャーたちが、何を考え、何を報告書に書き留めるのか比較するのも面白いだろう。